物語の概要
本作は歴史漫画である。室町時代後期、伊勢新九郎盛時(後の北条早雲)が自身の覚悟と家族の運命を賭け、一族の所領を取り戻すため行動を起こす。将軍・足利義材が近江攻めで京を離れる中、細川政元が新政権への不満を募らせる。政元と連携しつつ、新九郎は一族の頭領・貞宗に“ある約束”を迫る決意を固める。歴史の転換点が迫る中、勢力争いの局面が描かれる緊迫の第20巻である。
主要キャラクター
- 伊勢新九郎盛時(北条早雲):本作の主人公。名門伊勢一門の出身で、覚悟を胸に所領奪還へ動き出す中心人物。
- 細川政元:京を離れる義材に代わり政権内部に不満を抱える実力者。新九郎と接点を持ちつつ動きを見せる 。
- 伊勢貞宗:新九郎の一族の頭領。新九郎に覚悟を迫られる立場として描かれる。
物語の特徴
本作の魅力は、歴史学に基づいた精緻な考証と創作者による補完が織り込まれ、リアルとフィクションの融合が見事である。応仁の乱以降の室町末期、実在の政治家・武将を交えながら、新九郎が経験と葛藤、覚悟を胸に成長していく姿を描く。一族再興と戦国大名への転身を描いた壮大な大河として、他作品にない深みとリアリティを備える 。
書籍情報
新九郎、奔る! 20巻
著者:ゆうきまさみ 氏
出版社:小学館(ビッグコミックス)
発売日:2025年7月11日
ISBN:9784098635078
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
戦国”を始めたのは誰か!?
将軍・義材が近江攻めで京を不在にするなか、
新政権への不満が募る、細川政元。
伊勢貞宗と共に、清晃を将軍にする可能性を探るが
中々、光明は見えない。
そんな中、伊豆の所領を取り戻したい新九郎は、
覚悟を決め、一族の頭領・貞宗に、とある約束を迫るーーー!
己の、家の、一族の……
それぞれの事情と欲望で動かざるを得ない時代を生きる室町後期の人々。
戦乱の世を始めたのは誰か。
歴史の局面はもうすぐそこーーーー
感想
読み終えて、まず感じたのは、室町後期の世の移り変わりの激しさである。
今回の巻では、新九郎自身は伊豆の所領を取り戻すために動き出す決意を固めるものの、京では将軍の座を巡る大きな動きが繰り広げられていた。
新九郎は、所領である荏原を手放し、残るは茶々丸に奪われた伊豆の所領のみとなる。
将軍・義材に仲裁を嘆願しようとするも、戦に夢中な義材にはなかなか届かない。
その間に、京では細川政元が暗躍し、義材を将軍の座から引きずり降ろそうと画策する。
その裏で糸を引く伊勢家の存在もあり、呆気なく将軍が交代してしまう展開には、目を見張るものがあった。
天皇が反対しても、武家の援助なしでは生きていけない状況が、将軍の地位の軽さを物語っている。
読んでいて痛感したのは、将軍というトップの地位に就いていても、大名たちを掌握できなければ、簡単に引きずり下ろされてしまうという現実だ。
それはまるで、椅子の足を蹴飛ばされるようなものだ。もちろん、これは日本だけの話ではなく、諸外国でも貴族の方が力を持っていたりする。
新九郎は、ついに自力で領地を取り戻すことを決意する。迷いはないものの、手段は限られている。
そんな中、巻末には新たなキーマンが登場し、今後の展開が非常に楽しみになった。
本当に、この時代は人々がそれぞれの思惑で動き回り、目まぐるしい日々を送っていたのだろうと感じさせられる。
今回の巻では、新九郎自身の動きは少なかったものの、将軍の挿げ替え劇を通して、室町時代の政治情勢や人間関係の複雑さを深く理解することができた。
いつの時代も、年配の人々の影響力は大きいものだと改めて感じさせられた。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
展開まとめ
第百二十九話「蓬断」
新九郎の多忙と年越し
延徳四年正月、新九郎は所領売却に関する業務に追われ、慌ただしく年を越していた。政務に没頭するあまり、子どもたちの誘いにも応じられず、静かに執務を続けていた。
子どもたちとの交流
子どもたちは新九郎に遊びをねだり、最初は険しい表情に怯えるが、新九郎は怒っているのではなく元々の顔つきだと釈明し、一緒に遊ぶことを承諾する。遊びの内容は弓遊びであった。
弓遊びと回想
子どもが弓を引いて的に挑戦するがうまくいかず、新九郎は過去に自らも常徳院から弓をもらって遊んだことを思い出す。弓の扱いに苦戦する子どもに対し、新九郎は助言を与える。老臣は、常徳院のような高貴な立場の者との父子関係は稀であると述べ、新九郎はその恵まれた環境にあることを示唆する。
かつての記憶と思案
新九郎は木の上から様子を見ていた青年を見つけ、彼がかつてのある人物たちと同様に、触れ合うことのない立場にあったのではないかと考えを巡らせる。
陣中での嘆願
近江国大津、園城寺光浄院の将軍・足利義材の本陣に、新九郎は私用として訪れる。実家の兄からの嘆願を自ら陳情すべく申し出る。陣中は混雑していたが、書状を提出し返答を得る。
御所からの返答と待機
新九郎の申し出に対し、「今回はありがたく頂戴するが、返答は不要」との返答が御所から届く。音沙汰がないまま二ヶ月が経過する。
嘆願の重みと弁明
新九郎は老臣に対し、自らの嘆願が小さな案件として扱われていることに疑問を呈する。しかし老臣は、御所の状況を鑑みれば些細に見えることもあると諭す。新九郎は所領の経済的事情が死活問題であると強調し、自身の立場と責任を強く訴える。
年始も政務に明け暮れる日々
延徳四年の正月を迎えても、新九郎は所領売却に関する業務に追われていた。家中の整理もままならず、机に向かう日々が続いていた。
弓遊びに誘う子どもたち
子どもたちは外で遊んでいる最中、新九郎のもとへ訪れ、「あそんでー」と声をかけるが、新九郎は作業を止めず背を向けたままだった。
家族との距離と関係の変化
千代丸が新九郎に懐く様子に対し、周囲は不思議がっていた。留守がちな新九郎に代わり、遊びを通じて接することが進められる。
木工に没頭する理由
新九郎は伊勢家が鍛冶や木工に従事していることを語り、自身も気晴らしのために木細工に取り組んでいた。
道具を欲しがる子と父の対応
娘が細工に興味を示し「ちょまるもしたい」と頼むが、新九郎は刃物を使う作業であることから「もう少し大きくなったら」と制した。
おもちゃで気を紛らわせる
新九郎は木製の馬を渡し「犬若と遊んでおれ」と言い含め、自身は仕事のため出かける準備を進めた。
新たな訪問先の土倉
新九郎は姉小路烏丸にある宇野又太郎の土倉を訪問し、伊勢家の紹介を受けたことを伝える。丁重に迎えられ、奥座敷へと案内された。
献上酒と応対の開始
香りのよい酒が振る舞われ、宇野は「将軍家に献上する酒」と説明した。新九郎はその酒を「うまい」と評し、場が和やかになる。
本題に入る新九郎
新九郎は、酒の評価のために来たわけではないと前置きし、備中の所領を750貫文で売却した件について切り出した。
支払いに関する取り決め
750貫文のうち、150貫文をすでに準備したことが伝えられ、残額については割符を使っての分割払いが提示された。
金策に動く人脈の活用
宇野は、業界のネットワークを使い、残りの100貫文は小川の長谷川から直接受け取るよう手配することを申し出た。
東国での酒造計画への関心
新九郎は東国の水質に注目しており、酒造の拠点を考えていることを明かす。宇野はその構想に関心を示した。
酒販網拡大の可能性
東国での酒造と販路拡大が成功すれば、土地価格は安価に抑えられるとの試算が語られ、新九郎はその価値に納得を示した。
750貫文の意味と返答待ち
掃部助殿は伊勢家への最低限の誠意として750貫文を提示したと伝え、あとは御所からの正式な返答を待つのみとなった。
京兆家の失態
新九郎が訪れた政元は、不機嫌な様子で近江守護代に任せていた安富が六角勢の襲撃に遭い敗北したことを語った。政元は京兆家の面目が潰れたと厳しい評価を下した。
戦局への懸念と打開
政元は御所本陣の安全には問題ないとしたが、名誉を傷つけられたことに憤っていた。三日後には六角勢を打ち破ったと報告しつつも、名指しでの功績認定に対しては苦い思いを吐露した。
新たな動きへの提案
政元は、新たに右京大夫の上原元秀と面会。元秀は河内の尾張守家の分国であるにもかかわらず、これなら河内も掌握できると発言し、政元にとっては重要な布石と映った。
三管家体制の再編構想
元秀は、尾張守家の家督が弱体化している今こそ機会であるとし、細川・斯波・畠山の三管家を再び統一的に立て直す意向を語った。その背景には家格と威光の回復を狙う意図があった。
意見の分裂と動揺
政元の発言に対して、周囲からは「軽いのでは」との反応が出る一方で、三管家再建の動きが現実味を帯びる中、新九郎もまた慎重に情勢を見つめていた。
返答の遅延と疑念
話題は新九郎が待つ御所からの嘆願返答に移る。政元らは「すでに意見書は出している」と述べるが、返答が届かないことについては「伝わっていないかもしれぬ」と疑念を口にした。
妨害の存在
政元は御所への嘆願が届かぬ理由について、葉室中納言・光忠が介在していると指摘。彼が常徳院の時代の側近であり、現体制の意図を妨害しているのではと語った。
障害を取り除く決意
政元は「このままでは常徳院様の一の舞になってしまう」とし、光忠を取り除かなければ御所に意思が届かぬと判断。具体的行動を視野に入れて決意を固めていた。
第百三十話 明応の政変 その1
出産の報告と新たな命の誕生
明応四年四月下旬、ぬいが第二子を出産し、男子であった。家臣たちはこの報告を新九郎に伝え、安産であったことも報告された。新九郎は安産かどうかを気にかけていたが、実際に母子ともに無事であることを確認して安堵した。
周囲の祝福と新九郎の内心
家中は新たな命の誕生を祝福する雰囲気に包まれた。ぬいの側近たちも元気な様子を見せ、新九郎にも明るく接した。一方で新九郎は、喜ばしい出来事であると感じながらも、先々のことを考えると心が重くなると吐露した。家臣は「悪いことではない」と励まし、気に病まず喜べと諭した。
弥八郎の行動と叱責
笠原弥八郎が新九郎の元に上洛したが、到着してすぐに残り物の食事を求めるなど、無遠慮な態度をとった。新九郎はその行動を咎め、「皆を桂原に帰したのだから、残り物を食べぬように」と厳しく注意した。
家中の事情と新九郎の現状
弥八郎は、次男・三男・四男が桂原に帰っても分け与えられる田畑がなく、家督を継いだ長男が仕官先から呼び戻されているという現実を語った。また、家督争いの例として自分の親戚の話も挙げ、新九郎の理解を得ようとした。
新九郎家の変化と上洛の背景
弥助らが新九郎に家の変化を伝える中、新九郎が上洛して以降、かつてのような桂原ではなくなったことが語られた。弥助一家が上洛してきたのも、食事の援助を受けるためであった。新九郎はその現実に動揺を隠せなかった。
駿河への出立命令
新九郎は、弥八郎と太郎を連れて一足先に駿河へ戻るよう命じた。殿の名が地に落ちると家臣から忠告されたことを受け、行動に出たものである。交渉が手詰まりとなった堀越との対応についても指示が出され、太郎には伊豆行きを命じた。
伊豆の状況確認と今後の意図
伊豆方面への船の使用についても指示され、駿河と伊豆を何度も往来していたことが語られた。新九郎は、茶々丸の知行に問題があれば付け入る余地があると考え、伊豆の実情や困りごとの把握、領民の声の収集を命じた。
領地奪還への興味と戦略意識
新九郎は、戦略的観点からも伊豆領地の再奪還を視野に入れていた。弥八郎からは「面白そう」との感想が述べられ、新九郎自身も「面白くなってきた」と感じていた。容易に返ってこぬ領地をどう取り戻すか、その策を練ることに興味を抱き始めていた。
領地経営の苦労と意欲の芽生え
新九郎は北日野の伊勢貞宗と対話し、自身の領地経営に対する思いを語った。駿河の土地改良に取り組んでいるが、場所の悪さや距離の遠さが負担となっていた。それでも貞宗は、新九郎が所領の話をする際の楽しげな様子から、新たな意欲を見て取っていた。
修行願望と世情の不穏
新九郎のもとに右京大夫が現れ、自らは領地を捨てて修行に出たいと語った。新九郎は五か国の守護職が安定していない現状を指摘し、近江の守護職を返上する者もいることを知った。右京大夫は不機嫌そうな表情を見せながらも、酒を酌み交わすことで対話の場が和やかに進んだ。
御所と将軍職の行方
酒の席では、宇野の酒が供され、かつて大御台所様に贈られた品であることが判明した。新九郎は大御台所様の様子を気にかけ、彼女が未だに隠居しているのかを尋ねた。右京大夫は、大御台所が表向きの政治には関与しない姿勢を示していると語りつつも、将軍職への思惑が絡む複雑な背景をにじませた。
御所の影響力と将軍の評価
将軍義材の軍は常徳院時代に比べて士気が高く、近江方面での軍事行動でも順調な進展を見せていた。兵たちは大御所様の名のもとに戦うことに誇りを感じており、現地ではその人気も高まっていた。右京大夫は、成功すれば大義名分を失い、失敗すれば責任を問われるという将軍の立場の難しさにも言及した。
御親征の決定と将軍の在り方
新九郎らは、将軍義材が今後の近江への御親征を独断で決定したことを知らされた。その判断力を評価する声がある一方で、将軍が自らの意志で動いてしまうことに対する懸念も示された。新九郎は、機関としての幕府の役割を守るべきであり、将軍はその意見に耳を傾ける存在であるべきだと語った。
桂原の家族と新たな年号「明応」
六月、新九郎はぬいや子供たちと団らんの時間を過ごしていた。家計が苦しいなかでも、ぬいは化粧料から原料費を出し続けていた。一方で、子供たちの大半が桂原へ戻ることが寂しさを募らせていた。その後、疫病の流行を契機として新たな元号「明応」が制定され、七月十九日に改元が実施された。
伊豆帰還の意向と周囲の反応
伊勢貞宗は、新九郎がこの重要な時期に駿河に戻るという話を聞き、驚きを示した。新九郎は、姉からの帰駿の催促があったことと、甲斐国の内乱によって今川家に出兵の要請が届いていることを理由に挙げた。貞宗は、新九郎の行動が御所様の降ろし奉りと関係するのではないかと警戒を示した。
「見て見ぬふり」の示唆
新九郎は、伊豆の所領問題について現在の御所様から裁定が下ることは望めないと語り、伊豆で起こることには見て見ぬふりをしてほしいと懇願した。また、見事清晃を将軍の座に就けた暁には、その忠誠を報いる姿勢を明言した。
第百三十一話 明応の政変 その2
今川館への帰還と父の現状
明応元年八月下旬、新九郎は駿河の今川館に帰還した。今川家当主・龍王丸や側近らは、新九郎の帰還を喜び、父・盛定の様子について尋ねた。新九郎は父が元気であることを報告し、頭脳明晰で足腰も丈夫だと語った。
祖父の呼び寄せと所領問題の再燃
新九郎の姉は、父とぬいを駿河へ呼び寄せる案を提案し、駿河の気候の良さを理由に挙げた。新九郎はその申し出に感謝を示しつつも、京を引き払えば自らの立場を失うことを懸念した。所領の整理の件に関しても、姉が積極的に提案し、宇治田原の扱いや名義について意見を述べた。
甲斐の出兵要請と応対
甲斐の武田家では内紛が起きており、武田刑部大輔から出兵の要請が届いていた。新九郎は、それを受けて駿河からの対応を議論しつつ、姉からは「総大将にしてやるから行ってこい」と背中を押されたが、本人は即答で断った。
出兵と短期決着
明応元年九月中旬、新九郎は甲斐国河内の陣中にいた。武田五郎勢との交戦はすでに終盤に差し掛かっており、新九郎の役目は後詰めと兵糧輸送に限られていた。そのため戦果を挙げることなく、甲斐出陣は短期間で終結した。
一方、京では
九郎の出奔と盛定の下への預け
備中大合戦の折、盛瀬の子である九郎は、「守護方に付く」と宣言し、継承とは無関係であるはずの荏原から勝手に出奔した。本来荏原は盛瀬の嫡男が継ぐ予定であり、九郎は家の後継ぎではなかった。
出奔後、九郎は盛瀬の妻、すなわち自身の母に匿われていたが、盛瀬に発見される。盛瀬は、家の秩序を乱した九郎を本来ならば斬るべき立場にあったが、情けをかけて「勘当」で済ませた。
さらに、盛瀬は過去に兄・入道によって嫡男を殺された経緯を持ち、再び子を失うことを避けるため、九郎を入道の手が届かない盛定のもとへ預ける決断をした。盛定は「入道に頭を下げて許しを請うべき」と助言するが、九郎はこれを固辞する。
盛瀬は「好きにせよ」とだけ告げて去り、九郎は盛定の庇護下に置かれることとなった。
幕府の財政難と御所(将軍家)の出陣計画
細川政元は、二ヶ月前に終えたばかりの御親征(将軍の自らの出陣)を再び行おうとする将軍義材の意向に対し、強い懸念を示していた。政元は、将軍家に仕える諸将たちが疲弊しており、再度の出陣に耐えられる状況ではないと冷静に分析していた。
また、幕府の財政状況も厳しく、御所の出費が重なれば、支える京兆家(細川家)にも大きな負担がのしかかると見ていた。政元は「どこも厳しい」と言いながらも、特に京兆家と幕府の財政逼迫を重く受け止め、慎重に行動する必要があると判断する。
御所の意向と政元の戦略的思惑
しかし政元は、それでも御所が強引に出陣しようとするのであれば、「これは最後のチャンス」と捉え、逆に御所を止める役割こそが京兆家の責任であると語る。ここで政元は、「愚かな諸将が駆け出す前に、こちらが食い止めるのだ」と冷静に述べ、将軍家を補佐する役割を果たす姿勢を強調する。
また、「この助け舟に乗ってこないのであれば……」という発言から、出陣の是非をめぐる将軍家との関係性の再編成を視野に入れていることが読み取れる。
上原元秀への指示
細川政元は、上原元秀に対し「工作を急げ」と命じる。これは、将軍義材の出陣を止めるための政治的調整・根回しを意味しており、家中を通じた具体的な動きの開始を指示した形である。
さらに、「御屋形様にも急いでいただかねば困りますぞ」と付け加えることで、将軍の後見人である清晃(義綱)への対応も急務であるという認識を示し、政治・軍事両面での主導権掌握を狙う姿勢が表れていた。
洞松院との再会
政元は龍安寺にいる姉・洞松院を訪ね、丁重に挨拶を述べた。洞松院は政元の無沙汰を咎めることなく、相変わらずの振る舞いで応じる。政元の装束や態度が格式ばっていないことを、洞松院は微笑ましく受け入れていた。
突然の還俗の申し出
洞松院は、齢三十を過ぎた自らを「還俗させてほしい」と切り出す。政元は一瞬たじろぎながらも、「誰に嫁ぐつもりか」と尋ねる。洞松院は名指しこそしないものの、相手は大名の守護職にある人物で、すでに後家となった者だと示唆する。政元は赤松長門少輔(=赤松政則)ではないかと見抜き、言質を取る。
政略結婚の提案に戸惑う政元
洞松院は、御家のために強い関係を結ぶことが目的であると強調し、政元に準備を進めるよう促す。政元は困惑しながらも、「正室ではなく後妻としてなら」と念押しした上で、洞松院の再婚を受け入れる姿勢を見せる。
洞松院の真意としたたかさ
洞松院は「武家の妻を一度やってみたかった」と語り、明確な政治的意図と個人的好奇心を交えた決断であることを明かす。そして、もし赤松政則側が正式に申し出てくるなら、すぐに法衣を脱ぎ、婚儀の準備に入ると宣言する。その強い意志に、政元は押し切られる形となった。
第百三十二話 応の政変その3
伊豆の情勢と新九郎の沈思
明応二年二月。新九郎は数ヶ月にわたり、伊豆を遠く望みながら沈思していた。彼の視線の先には、駿河・焼津の代官所から見える伊豆半島があった。
将軍の出陣と緊急の知らせ
近江から帰還した将軍・足利義稙が、再び二月中に河内へ出陣すると知らせが入る。新九郎は急ぎ家臣や縁者を招集し、情勢の確認と対策を講じる。
石脇城館での協議と堀越残党の登場
新九郎は、自身の居城・石脇城館で軍議を開く。招かれたのは、かつて堀越公方家に仕えた奉公衆である松田弥次郎と遠山隼人佑の二名。彼らは堀越公方のクーデター時、姫君を保護して伊豆を脱出し、駿府へ落ち延びていた。
伊豆の現状と支配率の内訳
茶々丸による堀越御所襲撃から約一年半。伊豆国内の国人衆の動向は以下のように報告された。
- 茶々丸に積極的に従っている者:五分
- 成り行きで従っている者:三分
- 反抗的で抵抗を続けている者:二分
関東管領の影響と茶々丸の後ろ盾
伊豆は元々関東管領の分国であり、現在でもその影響力が残る。茶々丸の背後には関東管領の後援があるとされ、国人衆もそれに連なる形で支配構造が続いていた。
年貢の増徴と混乱する支配体制
伊豆では、年貢が重くなっているとの報告があった。理由は、支配層の茶々丸と抵抗勢力との戦闘が長引き、軍事費や徴発の増加により農村が圧迫されているためであると見られていた。
新九郎の所感と将軍の無関心
これらの報告を受けた新九郎は、「公方様の御知行よろしからず……」と呟き、将軍が東国(伊豆)情勢に無関心であること、そして自身の嘆願が届いていない可能性を悟る。
自主行動への方針転換
新九郎は「次の手段を考えるほかない」と語り、奪われた所領は「奪い返す」と明言。将軍の支援を待つのではなく、自ら行動を起こすことを決意する。
自立への決意と所領への思い
新九郎は、過去に手放した荏原を惜しむ気持ちを回想しつつも、他人の顔色に依存するような所領を望まないと断言した。親の遺産や恩恵に頼るのではなく、自身の力で経営できる領地を求め、たとえ相手が公方家であっても取りに行く覚悟を語った。
将軍・義材の出陣と京の留守体制
二月十日、将軍義材は後土御門天皇に暇乞いを行い、河内出征の許可を得た。京の治安維持のために細川京兆家の石京大夫を残し、将軍自ら出陣する体制が整えられた。これにより、義材の遠征は後戻りのできない事業となった。
右京兆家への処遇と細川義春の対応
一条御所では、細川義春が御所様の決定に反対した右京兆家に対して、何らかの懲罰を検討すべきとの意見を述べた。従わなければ出仕を拒むとの強硬姿勢であり、右京大夫が近江で痛い目に遭っているとの指摘もなされた。
河内遠征を巡る武家たちの思惑
各地の守護職たちは河内遠征を機に自身の立場を強化しようとしていた。畠山政長は、「お手柄の独占は許さぬ」と発言し、功績の奪い合いを警戒していた。斯波義寛も「変わり者だが頼もしい」と評された新九郎に期待を寄せた。
赤松政則の酩酊と策謀
赤松政則は酔った様子で帰宅し、家臣の別所則治が主の意思を確認しようとするが、政則は明言を避けた。則治は今回の出陣には何の益もないと考え、出陣に否定的であった。
河内遠征の実益のなさと兵糧難
則治は、遠征が成功しても河内を取り戻せる保証はなく、収穫の多かった前年に比べ、兵糧もほとんど残っていないと説明した。出陣の費用も火の車であり、実益が伴わないと冷静に分析した。
越前朝倉攻めと御所様の意図
太蔵は河内遠征の結果次第で、次は越前朝倉攻めが予定されていると述べた。御所様は功績を認め、報いる意志を持っているとし、赤松政則の反対意見が御所様の不興を買った可能性についても示唆された。
京兆家との縁談と御所様の将軍位
縁談を安易に受け入れることは御所様の御不興を買う恐れがあると警戒される一方、斯波・畠山らにとっては好機とも捉えられていた。また、御所様を将軍の座から降ろすことは現実的でないとされ、清晃殿の将軍位を朝廷に認めさせる必要が指摘された。
朝廷工作と清晃殿擁立の布石
将軍交代を実現するには、まず大御台様の説得が不可欠であるとされた。伊勢貞宗が人脈と義材の足場を切り崩すために動き、貞宗は伊都郡の繋がりを活かして朝廷工作に協力する意志を示した。
将軍義材の出陣と細川政元の不在
二月十五日、将軍足利義材が河内遠征に出陣した。若狭武田・能登畠山・京極・大内など有力大名が名を連ねる中、細川政元の名はなかった。義材は河内国の正覚寺に本陣を設け、出陣の事実が朝廷にも伝えられた。
軍勢の進展と情勢の緊迫
義材軍は勢いを増し、畠山義就の拠点に迫る動きを見せた。一方、義就軍側も備えを整え、対抗姿勢を強めていた。河内攻めは順調であるとの報告がもたらされ、義材の勝利が目前とされた。
財政逼迫と越前出陣の可能性
河内遠征により参陣した諸将の幕府財政は疲弊していたにもかかわらず、義材は次なる越前への出陣をも視野に入れていた。これに対し、朝廷関係者からはさらなる疲弊を招くとの懸念が示された。
清晃擁立への動きと朝廷の意志
将軍交代を画策する側は、朝廷に対し清晃殿の将軍擁立を働きかけていた。これに関し、伊勢貞宗が御台所に「子である清晃を代わりに立てよ」と進言した。御台所は一度は断るも、最終的に「妾が許します」と承諾した。
第百三十三話 明応の政変 その4
清晃擁立の好機と覚悟
駿河国にいる人物のもとに、京や河内から状況を伝える文が届く。京兆家は今度の河内遠征に加わっておらず、戦力は京に残されている状況であった。この機を活かして清晃殿を擁立しようとする意見が出され、明応の政変の例も引き合いに出された。御所様の地位が固定化する前に動くべきとの意見も強調された。
河内戦線の停滞と出陣命令
河内国内での戦いにおいて、斯波義寛は物資不足と徴発困難を訴えた。戦況は膠着し、弾正少弼(畠山政長)も疲弊していたが、御所様は陣を引くつもりがない様子であった。越前攻めのためには、この戦いで勝利することが不可欠であるとされ、出陣の号令が発せられた。
幕府軍の進軍と膠着戦
幕府軍は敵の数倍の兵力で攻勢を仕掛けていたが、士気の問題や補給の負担などが影響し、戦況は思うように進まなかった。各将は将軍の目前で武功を上げようと意欲を燃やしていたが、敵軍の抵抗も激しかった。
古市古墳周辺の戦況と布陣
戦場は大阪府羽曳野の古市古墳群周辺で、敵軍は北から押し寄せる幕府軍に対して堤防を防衛線として活用していた。前線では平地の部隊が疲弊し、撤退命令が出される事態に至っていた。
混乱する前線と撤退命令
前線の部隊には撤退命令が下され、弾正少弼は「案ずるな、敵はここまで押し寄せることはない」と部下を励ました。一方、伊勢貞陸らは将軍の命で撤退を支持し、戦線の整理が進められた。
本陣での軍議
将軍本陣の正覚寺では、政所執事の伊勢貞陸が軍装を解いた姿で迎えられた。兵庫助(義兄)との会談を予定しつつ、他の諸将の考えを先に確認したい意向を示した。弥次郎・弥八郎らが順に入室し、軍議の体制が整えられた。
大御台の決断と清晃擁立の表明
伊勢守からの報せにより、大御台が香嚴院清晃殿の支持を表明したことが明らかとなった。この決定により、近い将来、将軍が交代する可能性が浮上し、近臣衆の対応が問われた。一同はその変化を受け入れ、動揺せぬよう心構えを求められた。
政変への呼応と兵庫助の到着
兵庫助が遅れて宴席に到着した頃、都では赤松政則の陣屋に異変があり、上原左衛門大夫から「釘を刺す」内容の使者が訪れていた。上原は御台の動きに従って清晃擁立に動くよう促していた。
赤松家の判断と決断の圧力
赤松政則の家臣たちは、清晃を支持するか否かを巡って意見を交わし、最終的に「御決断を」と政則に迫った。浦上美作守は、かつての守護職を取り戻すための機会としてこの動きを肯定的に捉え、京兆家との関係を深めようとした。
清晃擁立の縁談成立と婚姻
赤松政則と細川政元の姉との縁談が成立し、清晃擁立への布石が打たれた。出陣中の政則の陣中で婚礼が執り行われるという異例の事態となり、これにより赤松家と京兆家の結びつきが一層強化された。
将軍交代の怪文書と動揺の広がり
伊勢守の名を冠した怪文書が各地の陣に出回り、香嚴院清晃殿を新将軍として推す決議がなされたという情報が広まった。幕府軍本陣の正覚寺でも、この怪文書への対応を巡って緊張が高まった。
信憑性を疑う声と京の動静
越前国の大和守らは、この怪文書を信じられないと評し、「花押がない」「小細工である」と断じた。一方で、一部は「京で何かが起きている」との予感を抱き、動揺を隠せなかった。
怪文書への対応と将軍位奪取の動き
幕府軍の陣中では、諸将に対し「怪しい情報に惑わされず目前の戦いに集中せよ」との方針が示された。将軍の座を揺るがす怪文書の流布を受けて、新将軍候補である清晃の身柄確保の必要性も指摘された。
清晃の身柄確保と将軍交代の通告
四月二十二日深夜、京の天龍寺にいた香嚴院清晃のもとへ使者が現れ、「本日より将軍となる」と告げて同行を求めた。清晃は右京大夫の関与に驚きつつも、事態を受け入れた様子を見せた。
正覚寺本陣と出立
一方、正覚寺で若武者が家族の様子を確認するため一時帰郷を許された。出発に際し、政所執事から「困ったことがあれば正鎮入道に相談せよ」と助言された。
因みに”正鎮入道”とは新九郎の父・盛定である。
第百三十四話 明応の政変その5
明応の政変、激化
京で政敵掃討の動きが開始され、葉室光忠に連なる者が一斉に捕縛され始めた。清晃らも行方をくらませており、城中は混乱に包まれていた。政敵である細川政元は、敵対勢力の討伐を命じており、武士団が出動した。
慈照寺をはじめ、三宝院や東山山荘など各地に葉室派と目される僧や貴族が滞在していたが、これらも襲撃の対象となった。政元の配下は、河内御所と葉室光忠の縁者をすべて捕えるよう命令していた。
清晃の覚悟と行動
清晃は一時身を隠していたが、情勢を見極めたうえで香蔵院殿(=義材天皇)に付き従う決意を固める。彼は香蔵院殿が室町殿に入ることを宣言し、出征中の諸将に対しても帰還と合流を指示した。
一方で斯波義寛や織田敏定らは堺方面の軍事行動を注視しており、赤松軍の動静を警戒していた。敏定は戦機の不自然さを指摘し、赤松の動きを利用して武家としての存在感を示すよう主張した。
急報と撤収命令
そこへ京から急使が到着し、御屋形様に急ぎの報告を伝える。内容は、政元のクーデターと香蔵院殿の動きであった。御所の親征が軍の力になると判断し、「急ぎ撤収の支度を!」と命じた。
政元の傲慢と天皇の怒り
河内国の正覚寺に滞在する足利義材本陣では、政元が清晃を将軍に立てるとの噂が流れていた。政元自身は自らの将軍位は主上も認めたと発言していたが、それは半ば事実に過ぎなかった。
この政変に対し、後土御門天皇は激怒し、「朕が任命した将軍を廃立するとは何事か!」と怒声を上げ、ついには「退位する!」と宣言した。政元はこれに冷静に応じ、「御退位されればよろしかろう。何か不都合があるか?」と返していた。
経済的事情による天皇退位の制約
朝廷側では、天皇の退位に必要な儀式費用が宮中に存在しないことを理由に退位は不可能との見解を示していた。御譲位に関しても、資金が伴わなければ始まらないという現実を共有しつつ、武家の申し出には従うのが慣例であるとし、朝廷側はそれ以上の発言を控えることとした。
河内守護職罷免に対する驚愕と動揺
河内国守護である畠山政長のもとに、河内守護職の罷免を告げる文書が届き、政長は激しく動揺した。文書には伊勢守花押が添えられており、政長はそれが伊勢真宗の意志であると激怒し、「真宗えぇっ!!」と叫んだ。
小将軍の策略と政長の懸念
正覚寺にて、小将軍側の軍議が開かれ、政長の軍が京に出払っている隙を突く策が進められていた。政長はこれを「参陣せずに裏をかく策」と看破し、怒りをあらわにした。裏をかかれれば出陣中の軍勢が敵に回るという懸念も述べられた。
軍勢の再集結と京進軍への意向
政長は、敵に背を向けずに後退するよう、全軍を正覚寺に一度集結させて京に向けて進軍させる策を提示し、重臣たちもこれに同意した。その後、政長は「やって御覧にいれます!」と発言し、自らが殿軍を務める決意を示した。
伊勢守の承知と奉公衆の動揺
新九郎の弟・弥次郎盛興や奉公衆の小笠原政清は、伊勢守が既に承知していたのではないかと疑念を抱いた。政清は伊勢守の行動に父・貞親を重ねて見ていた。政清は正綸殿から薦められた茶を飲みながらも、「不味い」とこぼし、内心の苛立ちをにじませた。
河内守護職罷免の報せと苦境の認識
政清は河内守護職罷免を改めて知らされ、従来の戦線の継続に疑問を抱いた。兵の疲労も激しく、軍の士気も低下していた。政清は政長に進言するが、その場では従うしかなかったと振り返った。
情勢の逆転と伊勢守への反発
義材は事態を見直し、「ことこうなると悪い条件でもない」と発言し、政長の存在が重要であることを認識した。一方で、政長も「政元を倒すべし」と発言し、決断を示した。
小将軍軍の上洛と御所の動向
四月二十五日、小将軍の軍勢は上洛の途についた。これまで通り慎重に進む方針をとりつつ、右京大夫の不信を招かぬよう配慮された。赤松は上洛の決断を公にし、「右京大夫の直意である」として発した。
義材廃立後の京方の動揺
義材の廃立を受け、京方の兵は進軍の目的を失い、一部には朝倉攻めの停止を唱える者もいた。多くの兵が旧主を見捨てて新たな判断を下す状況にあり、奉公衆の宿所はほとんど空となっていた。政清は「不忠者ら」と怒りを叫んだ。
宿所の空虚と将来への不安
最後に、申次の者が奉公衆の宿所を訪れると、そこはほとんど空であった。
多数の兵が姿を消していた。
宿所に残った一人と再起の意志
奉公衆の宿所には申次が一人だけ残っていた。政清は本来の任ではないが、人手不足のために対応していた。
足利義材の前向きな決意
義材は、自らに残された将軍としての役割を改めて自覚し、申次らを集めて決意を表明した。残された者一人一人が「一騎当千」であることを示し、右京大夫らに見せつけると意気込んだ。
第百三十五話 明応の政変 その6
新将軍・義稙の初対面と名乗り
細川政元邸にて、足利義稙(改名後:香厳院清晃)が新将軍として正式に御成りし、関係者たちに挨拶した。義稙は自らを「未だ僧形なれど武家の気構えに満ちている」と表明し、将軍としての決意を明言した。
政元の思惑と諸将の対応
斯波義敏邸では、政元の権勢に屈した形で、各家臣や有力者が義稙への恭順を示していた。政元は「今は大きく顔を立てておくべき」と語り、右京大夫(細川高国)の功績を認めつつ、伊勢貞宗ら他家との連携を図っていた。政元は現状を維持しつつも次の策を模索し、兵の休養を命じた。
御屋形様派の葛藤と対立
政元に敵対的な御屋形様派(堀越公方支持派)では、遠江の美濃守光(甲斐敏光)が兵の帰還を提案する一方、左衛門督は「再出兵」を主張したが却下される。彼は御屋形様への忠義から激昂し、反発心を示した。
河内での対立と緊張の拡大
尚順陣営では、伊勢守からの書簡が届くが尚順は拒絶の姿勢を示し、「清晃殿への恭順を促す内容」と断じて読まずに突き返した。一方、足利義材の陣では、上洛した将たちが義稙(清晃)に付き従っていると報告があり、状況の急変に驚愕する声もあがった。
義材側の混乱と猜疑
義材陣営では、右京大夫との対決を覚悟していたものの、諸将が義稙に転じたことで見放されたとの印象が強まる。彼らはその理由を探り、「何か原因があったのでは」と振り返った。義材本人は不満を隠さず、「自分の何がそれほど嫌われたのか」と問い、側近に率直な意見を求めた。
大納言の苦言と左衛門督の辞職
大納言が率直な意見を述べようとしたが、義材に制される。左衛門督は責任を感じて辞職を申し出、義材の不満と困惑の中で場は重苦しい空気に包まれた。
御所様の出兵に対する疑問と批判
兵庫は御所様の戦の始め方に疑問を呈し、大納言は戦の経費が自己負担である現実を訴えた。戦の継続に慎重な声が上がり、御所様の越前・朝倉攻めへの意欲が明かされると、さらに反発が強まった。
御所の政治停滞と家臣団の反発
大納言は御所様が二年もの間、京で政務に集中したにもかかわらず、情勢が改善されなかったと指摘し、政務の滞りや未処理案件の存在が浮き彫りになった。兵庫は激しく反発し、大納言に対して発言を慎むよう命じられる。
緊張の打破と和解の試み
諸将の反発を受けた御所様は、自らの非を認め「諸将の痛みに思い至らなかったのは不徳」と述べ、反省の意を表した。その姿勢に一同は驚きつつも和らぎ、政長は「次は上手くやろう」と述べて場を収めた。
高屋城防衛戦と赤松軍の派遣
赤松政則が赤松・大内らを味方につけ、高屋城への支援派遣を決定。堺の布陣では政元が防衛準備を進め、正覚寺を要塞化。義材軍による正覚寺籠城戦が始まった。
京の新九郎邸での再会と対話
京では、新九郎の邸宅に伊勢八郎貞辰が訪問。細川の兵が増えてきたことを理由に、父の指示で早めに帰還したと述べたが、実際には家族の病は偽りで父に騙されて戻されたことが明らかになった。
家臣・親族との進退相談
貞辰は父に加勢する意思を示したが、盛時はそれを咎め、冷静に状況を見極めるよう助言した。
清晃との関係を巡る葛藤
盛時は貞辰に清晃に頭を下げよと意見した。それに貞辰は抵抗を見せたが、祖父は「兵庫助が状況の変化を見越して帰還させた」と説明し、清晃と関係を築く必要性を強調した。
家族との会話と一時の和やかさ
貞辰は盛時に諭される一方で、幼い親族と会話を交わし笑顔を見せた。ぬいから勧められた甘味を口にし、涙を浮かべながらも心を落ち着け。それを見ながら盛時は最近こんなばかりと内心でボヤいた。
クーデターの成立
同じ頃、駿河国・富士下方の新九郎の居館では、伊勢守による「クーデター」が成されたことが示唆された。
清晃擁立の報告と御所襲撃の計画
駿河国の伊勢守陣営において、清晃(足利義稙)が正式に将軍に立てられたとの報がもたらされた。これを受け、討ち入りを含む御所攻撃が現実味を帯びるが、堀越御所を襲って頭を狩っても維持が難しいと慎重な意見も出された。
戦略的課題と支配維持の困難
堀越御所の地理的状況と、北伊豆を支配下に置きたいと新九郎が言い、新九郎達の勢力単独での進攻は困難との判断が下された。御所襲撃の是非はまだ決しておらず、奉公衆との協議継続が必要とされた。
伊玄の訪問と意外な正体
新九郎のもとに「伊玄」と名乗る僧が面会を求めて訪れた。応対に出た者が「聞いたことのない名」と訝しむ中、伊玄の正体がかつて「上杉景春」と名乗っていた男であると判明する。彼は上杉修理太夫からの書状を伊勢守に届ける使者であった。
同シリーズ








同時に読みたい本
お金の流れで見る戦国時代 歴戦の武将も、そろばんには勝てない

百姓から見た戦国大名

その他フィクション

Share this content:
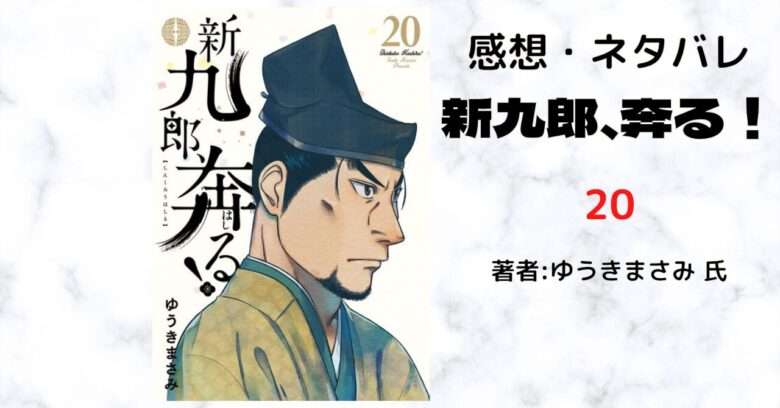

コメントを残す