物語の概要
本作は、大正時代の東京を舞台に、華族の娘・瀧川鈴子と神職華族の当主・花菱孝冬が、悪霊退治に挑むファンタジー小説である。鈴子は、親代わりだった人々を殺害した犯人を捜しながら、幽霊を喰らう怨霊を連れた孝冬と共に、数々の怪異に立ち向かっていく。
主要キャラクタ
- 瀧川鈴子:侯爵令嬢でありながら、浅草で育ち、怪談蒐集を趣味とする。過去の事件の真相を追い求める。
- 花菱孝冬:花菱男爵家の当主で、神職華族。幽霊を喰らう怨霊を使い、悪霊退治を行う。
- 淡路の君:十二単を纏う謎の霊。孝冬の力の源であり、物語の鍵を握る存在
物語の特徴
『花菱夫妻の退魔帖』シリーズは、大正時代の東京を舞台に、和風ファンタジーとミステリー要素を融合させた作品である。主人公たちの過去と現在が交錯し、個々の成長と共に物語が進行する。また、幽霊や怨霊との対峙を通じて、人間の内面や社会の闇を描き出している点が特徴的である。
書籍情報
花菱夫妻の退魔帖 五
著者:白川 紺子 氏
出版社:光文社
レーベル:光文社文庫
発売日:2025年5月13日
価格:770円(税込)
ISBN:978-4-334-10640-9
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
花菱孝冬は、友人の新聞記者・五十嵐を通じて、根岸の貸し家に出る女の幽霊の相談を受ける。
鈴虫の刺繍が施された朽葉色の単衣をまとったその幽霊は、家主によれば、以前住んでいた元娘義太夫・小鈴とのことで、十年ほど前に肺炎をこじらせて亡くなっていた。
小鈴には娘がいたが、義太夫の母を嫌って疎遠だったらしい。
貸し家を訪れた孝冬と鈴子は、小鈴がじっと一点を見つめていることに気づくが……。
果たして小鈴は、花菱家に祟っている怨霊・淡路の君の〝獲物〟となるのか?
ますます好調、大人気の大正浪漫悪霊退治ファンタジー第五弾!
感想
幽霊譚の始まりと“執念”のリアリズム
月鈴子
根岸の貸家に現れた幽霊の正体を追う章であった。
幽霊は、かつて娘義太夫として活躍したが、誹謗中傷と孤独の末に亡くなった女性・小鈴であった。
鈴子と孝冬は、小鈴の娘・お豊との確執や過去への執着を抱えていることを知り、淡路の君による吸収ではなく、魂を穏やかに導く方法を模索する。
関係者からの証言により、小鈴の真実が次第に明らかとなり、櫛を介して母娘の想いをつなぐことで小鈴は成仏する。
星の川
鈴子の婚礼準備を背景に、武蔵屋の女将・昌江が見る悪夢の真相を追う。
昌江の夢には過去の父親の姿が現れ、精神的に追い詰められていた。
一連の幽霊騒動は、元芸妓の女中・スエとその情夫による仕組まれたものであったが、昌江の心の傷は深く、夢の根にある実家の記憶が原因であることが判明する。
廃屋で対峙した血まみれの父親の幽霊は淡路の君により消滅し、昌江は解放された。
章末では、鴻八千代の不穏な監視と実秋への疑念が静かに浮上する。
鬼子母の実
女中・わかの菊見と並行して、鈴子は小松崎邸で観菊会に出席し、過去の使用人・加藤銀六と南条の接点を探る。
そこで鴻八千代と再び対峙し、感情的なやり取りを交わす。
一方、鶯谷では南条てるの死と赤子殺しの過去が明らかになり、淡路の君がその霊を吸収して解決する。
妹・らくの存在と実秋の関与が浮かび上がり、孝冬は兄への疑念と信頼の間で揺れる。
らくの遺志による供養の実現と『ともしび』に写る兄の姿によって、不安と覚悟を残して終わる。
鴻心霊学会の不穏と長男の影
鴻八千代率いる鴻心霊学会が再び不穏な存在感を示した。
その動きは表面的には友好を装いながらも、どこか底知れない気配を孕んでいた。
彼女の再度の接近には悪意以上に執着や実験的な興味すら垣間見える。
さらに、孝冬の兄・実秋の名が、霊学会の集合写真に記されていたことは驚愕に値する。
この伏線の張り方は非常に巧妙であり、「兄は一体、何を知っていたのか」「どこまで関与していたのか」と、想像が止まらなくなる。
不気味さが増すばかりで、読後もなおざわつきが残る構成となっていた。
穏やかな夫婦描写と静かな信頼
本作の魅力は、退魔や調査といった劇的な要素だけではない。
日常のひとときに織り込まれた花菱夫妻の関係性にもある。
とりわけ印象に残るのは、月見の夜に交わされる、野菊についての穏やかな対話である。
言葉少なながらも互いを思いやるやり取りに、信頼と寄り添いの温もりが漂っていた。
孝冬が不安と疲労の中で鈴子に真実を語ることを控えた場面では、理性と感情のせめぎ合いが丁寧に描かれており、夫婦の距離感が逆に繊細な信頼を際立たせていた。
わかと由良、脇役たちの潤い
本巻では、由良とわかの関係にもほのかな変化が描かれた。
女中としての立場ながらも、日常の延長線上に芽生える感情の揺れが丁寧に綴られており、作品世界に現実感を与えていた。
鈴子がわかに着物を譲る場面などには、階級を超えた情のやり取りがあり、時代背景を踏まえながらも温かみを失わない点が秀逸である。
事件の深化と“動く予感”
小鈴の事件にひとまずの決着がつき、昌江の悪夢も終息を迎えたが、物語全体は終わりではなく、次の局面へと静かに進んでいく。
てるの死や赤子の霊、加藤銀六と南条宏通の過去、そして実秋の関与。
謎は幾重にも重なりながら、核心に近づこうとしている。
披露宴という晴れの舞台を控えながら、何かが大きく動き出す予感が漂っており、次巻が楽しみでならない。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
登場キャラクター
花菱鈴子
侯爵家出身で、孝冬の妻。怪異や人情に強い関心を抱き、夫の退魔活動を精神面から支える存在である。
・旧瀧川侯爵家令嬢、花菱家の妻
・小鈴や昌江の霊的事件に関わり、赤子の霊の成仏に尽力した
・霊との対話を通じて、人の心に寄り添う姿勢が描かれた
花菱孝冬
本作の主人公であり、神職華族の家系に生まれた退魔師。妻・鈴子と共に幽霊や怨霊に関わる事件を調査する立場にある。
・花菱家当主、退魔師
・幽霊騒動の調査、怨霊の処理、小鈴の霊の成仏支援、昌江の夢の原因調査を行った
・退魔の力を淡路の君と共有しつつ、妻と協力して事件解決に臨む姿勢を示した
淡路の君
花菱家に長く憑いている霊的存在であり、孝冬と協力関係にある。幽霊を吸収する能力を持ち、姿は十二単姿の女性霊である。
・花菱家に憑く古い怨霊
・南条てるの幽霊や赤子の霊を吸収し、姿を見えなくさせた
・吸収された魂の行方は不明であり、「成仏」とは明確に異なる処理である
・孝冬に完全には従っておらず、自我と独自の判断基準を持つ存在として描写された
五十嵐
新聞記者であり、孝冬夫妻に協力する情報提供者。旧知の友人として信頼を得ており、調査における補佐役を務める。
・新聞記者
・小鈴の過去調査、憤懣生の素性調査、鴻心霊学会に関する情報収集を担った
・報道の枠を超え、調査協力者として存在感を示した
小鈴
かつて人気を博した娘義太夫であり、幽霊として登場する。
・元娘義太夫
・朽葉色の衣を纏って現れ、仏間や庭でその姿を目撃された。死後も娘や過去に強い執着を残した
・鈴子たちによって成仏させられ、穏やかな表情で消失した
浅野
根岸の貸家の持ち主であり、小鈴の旧知。小鈴を匿っていた過去がある。
・貸家の家主
・小鈴を保護しつつも、その過去を秘していた。後に花櫛を隠し持っていたことが発覚した
・小鈴への執着を抱きながらも、それを素直に語れなかった内面が描かれた
お豊
小鈴の実娘であり、母を拒絶しながらも心の底では深く想っていた。
・医者の妻
・鈴子の訪問に当初は冷たく応じたが、母の花櫛を受け取り心を揺らした
・母の霊が成仏したことを聞き、「お母さん」と呟くまでに変化を見せた
おはま
小鈴と同時代の元娘義太夫であり、かつては親交があったが、後に小鈴に嫉妬心を抱いた。
・元娘義太夫
・投書によって小鈴の引退に関与し、その過去を五十嵐に暴かれた
・嫉妬に基づく行動を悔いたものの、自己憐憫的な態度が印象付けられた
成田
小鈴の熱心なファンであり、時計店を営む資産家。浅野の旧友でもある。
・時計商、個人商店経営者
・浅野と小鈴の関係について証言し、過去の贔屓ぶりを語った
・当時の芸能を支えた背景人物として、小鈴の芸と生涯に理解を示した
憤懣生
匿名の新聞投稿者であり、小鈴を中傷する記事を投書していた。
・不明(後に収監)
・悪意ある記事を投稿し、小鈴の引退を間接的に誘導した
・後に五十嵐の調査により収監中であることが判明した
田鶴
花菱家に長年仕える年配の女中であり、鈴子の行動を厳しくも温かく見守る存在である。
・花菱家の女中頭
・夜の外出を危ぶむ発言や安全を優先する姿勢を通して、鈴子の身を案じた
・長年の忠誠と実直な態度により、屋敷内の信頼を集めている
宇佐見
花菱家の若い使用人であり、警戒心が強く、護衛としても行動する冷静な青年である。
・花菱家の使用人
・孝冬襲撃時に迅速に対応し、襲撃者を取り押さえる役割を果たした
・事件の後、鈴子から金一封の謝礼を受けた
由良
花菱家の女中で、わかの良き理解者。柔和な性格で周囲に安心感を与える。
・花菱家の女中
・孝冬襲撃事件で宇佐見と共に対応にあたり、鈴子の護衛に努めた
・鈴子より休日の褒賞を受け、わかとの交流も深めている
わか
花菱家の若い女中であり、由良と親しく交流している。おしゃれや外出を楽しむ年頃の娘である。
・花菱家の女中
・鈴子から着物を譲り受け、由良とともに菊見に出かけた
・主従の枠を超えた交流が描かれ、屋敷内での人間関係に温かみを加えた
昌江
武蔵屋の女将であり、鈴子の親族筋。過去の家庭環境に深い傷を負い、夢に悩まされていた。
・武蔵屋女将
・父の霊に悩まされ、現実と幻覚の境界で精神的に追い詰められた
・淡路の君によって悪夢から解放され、安堵の表情を取り戻した
惣兵衛
武蔵屋の主人であり、昌江の夫。実直で責任感が強く、妻の不調に深く心を痛めている。
・武蔵屋主人
・昌江の悪夢の件で孝冬に相談を持ちかけ、事態の解決に協力した
・事件を通じて妻への理解と信頼を改めて示した
スエ
かつて芸者であった過去を持つ女中であり、昌江の側仕えとして雇われていたが、裏で暗躍していた。
・武蔵屋女中
・幽霊騒動を演出し、昌江の不安を煽る工作を行ったのちに逃亡した
・最終的に捕縛され、陰謀の一端を担っていたことが明かされた
清充
鴻八千代に付き従う青年であり、鴻心霊学会の関係者。常に控えめな態度を崩さない。
・鴻心霊学会関係者
・八千代に随伴し、鈴子たちの動向を共に観察した
・八千代の目的に戸惑いながらも忠実に行動していた
鴻八千代
鴻心霊学会の代表的人物であり、鈴子に対して一方的な興味と執着を抱いている女性である。
・鴻心霊学会幹部
・昌江に実家へ戻るよう助言し、鶯谷で鈴子たちを密かに監視していた
・善意と呼べるか判然としない態度で接近し、今後の動向が不穏さを含んでいる
鴻善次郎
鴻八千代の父であり、霊学会の創設者的存在。過去の機関誌に名を連ねていた。
・鴻心霊学会創設者
・8年前の『ともしび』にて実秋や南条と共に写真に写っていた
・現在の活動状況は不明だが、過去の事件に関わる鍵を握る人物である
タカ
花菱家に仕える女中で、鈴子に随行することが多く、実務面で支える役割を担う。
・花菱家の女中
・小松崎邸の観菊会に同行し、現地の女中から情報を得ようとした
・調査への関心と行動力を見せ、鈴子の信頼を得ている
小松崎夫人
小松崎子爵の妻であり、社交の場に不慣れながらも丁寧な応対を見せる婦人である。
・子爵夫人
・観菊会を主催し、鈴子に夫の過去や使用人についての情報を語った
・夫の嫉妬心に悩みながらも、旧家としての体面を保ちつつ応対を行っていた
是澤
物書きを生業とする男性であり、南条てるの旧宅に住んでいる現住人。観察眼が鋭い。
・作家
・てるの霊やらくの来訪について証言を行い、供養にも協力した
・現場に居合わせた第三者として、重要な情報を提供した
南条てる
南条宏通の前妻であり、困窮の末に自ら命を絶った女性。死後は幽霊として登場する。
・元南条家の妻
・庭先に霊として現れ、淡路の君によって吸収された
・預かり子殺しの真相が明らかになり、事件の発端となった
薗部らく
南条てるの妹であり、物語中盤以降にその存在が明らかになる。姉を思う気持ちを持ちつつも距離を置いていた。
・不明(婚約者がいたとされる)
・姉の死後、供養費用を代理人を通じて支払い、子供たちの供養のため玩具や香花を届けた
・登場時点では所在不明であったが、再訪により東京に実在していることが判明した
鶯谷の少年
てるの旧宅近くに住む少年であり、赤子の霊の気配を最初に感知した数少ない人物。
・近隣住人の子供
・赤子の泣き声が聞こえることを鈴子に語り、後に聞こえなくなったことを報告した
・物語の節目に霊の消失を感知する重要な証言者として描かれた
加藤銀六
かつて小松崎家に仕えていた執事であり、南条と何らかの因縁を持っていた可能性がある人物。
・元小松崎家執事
・過去に南条と顔を合わせた可能性があり、現在は所在不明
・殺人事件の背景に関与していた可能性が示唆され、今後の調査対象となっている
花菱実秋
孝冬の兄であり、外交官としての経歴を持つ。物語では過去の事件との関与が疑われる立場にある。
・元外交官、花菱家長男
・過去に鴻心霊学会と関係を持ち、鴻善次郎・南条宏通との集合写真に写っていた
・らくの代理人として行動した可能性が浮上し、事件との関わりが疑念を呼んでいる
南条宏通
南条てるの元夫であり、過去に殺人事件の容疑者として浮上した人物。傲慢で無責任な性格が描写された。
・不明(過去に霊学会関係者と接点あり)
・小松崎家の来客として出入りし、鴻心霊学会の集合写真に姿を見せていた
・被害者の遺族や関係者から恨みを買う立場にあり、現在の動向は不明である
小松崎子爵夫人
小松崎家の先代夫人であり、加藤銀六を使用人として雇っていた時代の関係者。
・旧小松崎家子爵夫人
・手紙と写真を通じて加藤銀六と南条宏通の関係を明らかにした
・過去の人脈と記録によって現在の事件の手がかりを提供した
御子柴
花菱家と関わる調査員であり、孝冬に依頼された人物背景調査などを担う。
・調査業
・加藤銀六の経歴を調査し、孝冬に報告書を提出した
・影から事件解明に貢献する裏方的な存在として描かれた
展開まとめ
月鈴子
幽霊の出現と謎の女
初秋の夜、仏間にうつむいて座る女の幽霊が現れた。朽葉色の着物に銀杏返しの髷という装いで、姿は風に吹かれ消えるように消失した。数日後、向島の百花園を訪れた花菱孝冬と鈴子夫妻は、孝冬の友人で記者の五十嵐から「幽霊が出て店子が定着しない貸家」の相談を受ける。孝冬は、家に憑く霊を「淡路の君」に食わせる対象として、その家の調査に向かうことにした。
幽霊が棲む仏間の探索
夫妻が訪れた根岸の貸家は整備が行き届いていたが、奥の仏間で若い女の幽霊を発見する。女は朽葉色の単衣に鈴虫の刺繍を施した衣装を着て、正座した姿で現れた。家主の浅野はその装いから、「小鈴」というかつての住人で娘義太夫だった女性を思い出し、彼女の生涯を語り始める。
娘義太夫・小鈴の過去
小鈴は大阪出身で、娘義太夫として若くして人気を博した。だが、未婚で出産した過去やスキャンダルが原因で追われるように上京し、浅野の貸家に住むようになった。芸を誠実に極めたものの、熱狂的な支持者「堂摺連」からの中傷と妨害を受け引退に追い込まれた。その後は仕立物などで生計を立てながら娘を育てていたが、病気の悪化により孤独のうちに亡くなった。
娘・お豊の拒絶
小鈴の娘・お豊は医者の妻となり駒込に住んでいたが、母親に関する話題を頑なに拒絶した。訪ねてきた孝冬と鈴子を冷たくあしらい、「母の幽霊が出ようと私には関係ない」と言い放つ。彼女は母の過去とスキャンダルが原因で、いわれなき差別と苦痛を経験しており、その傷は深く根を残していた。
関係者の証言と成仏への糸口
失意のまま帰路に着いた夫妻は、次に小鈴の同時代の娘義太夫である「おはま」から話を聞こうと芝へ向かう決意をする。お豊の拒絶が示すように、母娘の関係性は世間の偏見と伝統芸能の陰の部分に根差した複雑なものであった。鈴子と孝冬は、淡路の君に幽霊を食わせるのではなく、小鈴の魂を安らかに導く術を模索し続ける。
おはまの回想と小鈴の過去
鈴子と孝冬は、小鈴の旧友である元娘義太夫・おはまを訪ね、引退前後の小鈴の様子を聞き取った。おはまは、小鈴が芸に真摯で気立ての良い人物だったことを語りつつも、男運に恵まれなかったことを悔やんでいた。また、芸能界の風評と偏見、新聞報道によって追い詰められた小鈴の苦境も語られた。一方で、おはま自身は恋愛に失敗し、離婚していたことが明かされ、当時の距離感や互いの立場の変化もにじませた。
成田の証言と浅野の過去
続いて孝冬は、小鈴の熱心な追っかけであった時計店社長・成田を訪問した。成田は当時の小鈴の印象を語り、浅野が小鈴を住まわせた経緯についても詳述した。浅野はかつて小鈴に強い思い入れを持っていたが、成田によれば、表立っては語らず、気恥ずかしさから「偶然だった」と偽っていたという。これにより、浅野と小鈴との関係の背景に、好意と後悔が交錯していたことが明らかになった。
幽霊の真相と新聞記事の出所
五十嵐は、小鈴の引退のきっかけとなった新聞投書の出所を調査し、「憤懣生」と名乗る投稿者が過去に多数の誹謗中傷を書いていた事実を突き止めた。さらに、その人物が別の娘義太夫・菊之助の熱心な支持者であり、菊之助から聞いた話として小鈴を貶めた可能性が高いと結論づけた。菊之助とは、かつて鈴子たちが訪ねたおはまであり、五十嵐は真相を確かめるべく彼女のもとを再訪する決意を固めた。
鈴子と孝冬の夫婦としての関わり
鈴子は、自らも幽霊調査に同行する意思を明確にし、淡路の君の“餌”として幽霊を見定める孝冬に釘を刺した。鈴子の意志の強さと気遣いは、孝冬にとって精神的な支えとなっていたが、同時に孝冬は鈴子の感情の機微に鈍感であることを五十嵐に指摘される。孝冬は改めて鈴子の存在を見つめ直し、彼女の信頼に応えるべく心を引き締めるに至った。
真実への歩みと人情の綾
小鈴の死の背景には、悪意ある誹謗、友人の裏切り、そして周囲の無力感が複雑に絡み合っていた。事件を追う孝冬たちは、単なる幽霊祓いに留まらず、小鈴の名誉を取り戻すための調査へと動いていた。五十嵐の執念と行動力、鈴子の直感と共感力、孝冬の信念が交差し、物語は真相の核心へと迫りつつあった。
おはまの告白と五十嵐の報告
五十嵐は巣鴨の監獄に収監されている「憤懣生」から情報を得たうえで、おはまを再訪した。おはまは小鈴への嫉妬心から虚偽の悪評を流し、それが元で小鈴が引退に追い込まれた事実を認めた。反省の弁を述べつつも、同情を引こうとする語り口や自己憐憫に満ちた態度に、五十嵐は嫌悪を覚えた。報告を受けた孝冬と鈴子は、五十嵐に感謝を述べつつ、事態の核心に近づいたことを感じ取った。
鈴子と孝冬のすれ違いと和解
おはまとの面会について話す中で、孝冬は五十嵐に「臆病だ」と指摘されたことを思い返し、鈴子の心情を確かめようとする。鈴子は、孝冬が他の女性と会って情報を聞き出すこと自体には否定的ではないが、幽霊に関する事案には自らも関与したいと強く主張した。孝冬は彼女の意志に応え、自らの不安と向き合いながら「嫌われたくない」と本心を吐露し、鈴子はそれに対して「嫌いません」と静かに応じた。二人の間に、言葉以上の信頼が確かに育まれていた。
仏壇の抽斗と小鈴の思念
再び貸家を訪れた孝冬と鈴子は、幽霊・小鈴が見つめる仏壇の抽斗に注目した。その奥から臙脂色の袱紗が見つかり、中には珊瑚の玉が一つだけ入っていた。小鈴の視線がその抽斗に向けられていたことから、この袱紗と中身に何らかの未練があると推察した二人は、家主の浅野に問いただした。浅野はしぶしぶ、珊瑚玉が付いた櫛を自宅に隠し持っていたことを認め、その櫛を持参した。
花櫛の由来と浅野の執着
持ち込まれた櫛は、鈴子の娘であるお豊が幼少時に愛用していたもので、小鈴が自身の母から譲られた思い出の品であった。小鈴は苦境にあってもこの櫛だけは手放さずにいた。浅野は櫛に対して自己正当化を試みつつ、小鈴への過度な思慕と監視行為を吐露し、彼女の死に対する複雑な感情を語った。小鈴が執着していたのは櫛そのものではなく、それに込めた娘への想いであることが明らかとなった。
小鈴の成仏と想いの託し先
鈴子が花櫛に残った珊瑚玉を嵌め直し、小鈴にお豊への引き渡しを約束した瞬間、幽霊は深々と頭を下げ、静かに消えていった。孝冬は浅野にその旨を告げ、家の貸し出しが可能になったことを伝えたが、浅野の顔は羞恥と悔恨に歪んでいた。
お豊との再会と櫛の受け渡し
その足で鈴子と孝冬は、お豊の元を再訪した。かつて拒絶されたこともあり逡巡したが、今回は丁重に謝罪を述べ、櫛の入った袱紗を差し出した。お豊は驚きつつもその品に強く心を動かされ、鈴子の「小鈴は成仏した」との言葉に心の揺れを隠しきれなかった。鈴子たちは強く迫ることなくその場を辞し、残されたお豊の「お母さん」という声が、かすかに彼らの背中を押した。
菊と庭の風景に寄せた静かな夕暮れ
夕暮れの庭で虫の音が響く中、鈴子は菊の鉢植えの前に佇んでいた。鉢植えは植木屋や実家の瀧川家から届いたものであり、庭には萩や女郎花と共に一輪の嫁菜が咲いていた。孝冬はその光景を静かに見守り、鈴子の佇まいに魅了されていた。鈴子が野菊を見て微笑む様子に、孝冬は彼女の好みを察し、共感を示して寄り添った。
野菊を介した夫婦の穏やかな対話
孝冬は、鉢植えよりも野菊を好むかと鈴子に尋ねた。鈴子は明確には否定せず、「そうかもしれません」と穏やかに答えた。その言葉に合わせて孝冬も「私もです」と応じたが、内心では菊に特段の関心はなかった。鈴子は夫の迎合を見抜いたが、咎めるでもなく受け入れた。二人の会話は、信頼と温かみ、そして互いの気持ちをそっと認め合う静かなひとときとして描かれていた。
星の川
瀧川家訪問と婚礼準備
鈴子は婚礼の披露に向け、瀧川家を訪れた。着物は万寿菊の刺繍を含む菊尽くしの装いで、家族や武蔵屋の女将・昌江から称賛を受けた。打掛は朝子が監修し、武蔵屋に注文した見事な品であった。訪問中、昌江は「不穏な夢」を見続けていると千津から話が出て、鈴子は興味を抱いたが、昌江は詳細を語らなかった。
昌江の悪夢と惣兵衛の依頼
数日後、昌江の夫・惣兵衛が花菱家を訪れ、妻が見る夢の内容と体調悪化について相談を持ちかけた。昌江の夢には、かつて母親を殺し自らも殺そうとした父親の姿が現れ、「家に帰ってこい」と繰り返し呼びかけていた。昌江はその悪夢に悩まされ続け、ついには血まみれの幽霊の姿を現実に見るようになり、極度の衰弱に陥った。
幽霊の目撃と玉簪の記憶
幽霊は昌江にしか見えず、唯一、付き添いの女中・スエが鏡越しに一度だけ目撃したと証言した。昌江は鈴子と孝冬に、自身の父の破滅と関連した砂金石の玉簪を見せ、父への複雑な記憶と憎しみ、そして恐れを語った。その姿は深い心の傷と長年の記憶の重みを物語っていた。
屋敷の調査と血糊の発見
鈴子と孝冬は屋敷内を調査し、昌江が幽霊を目撃したという庭の植え込みに血糊と思しき痕跡を発見した。このことから、幽霊は人為的な仕掛けではないかと推測し、目撃者スエに再度確認を促したが、証言は曖昧であった。
女中スエの逐電と真相の判明
その後、武蔵屋からスエが失踪したとの連絡が入った。惣兵衛によれば、スエはかつて芸妓であり、妾の関係を清算されたのち、紹介で武蔵屋に勤めていた。幽霊騒動は彼女とその情夫による悪戯であった可能性が高まり、特に鏡の場面で昌江を故意に驚かせた形跡があった。動機は不明だが、昌江の夢の内容を事前に把握していたことから計画性が疑われた。
未解決の悪夢と新たな疑問
スエの逐電により幽霊の件は終息に向かったが、昌江の悪夢自体は続いていた。昌江が夢を見始めたのはちょうどお盆の時期であり、幽霊とは別に夢の背景に何かしらの引き金がある可能性が示唆された。孝冬と鈴子は、夢の根にある記憶や想念に注目しつつ、さらに原因を探ることを決意した。
月明かりの襲撃と孝冬の応戦
鈴子と孝冬は月明かりのもと、麹町から屋敷までの道を散歩していたが、背後からの不審な足音に気づいた。孝冬は鈴子を先に帰宅させ、自らは後方の敵に応対することを選んだ。鈴子は急ぎ花菱邸へ駆け戻り、宇佐見に救援を求めた。宇佐見と由良が迅速に対応し、男を取り押さえることに成功した。男は刃物を所持しており、取り押さえられた際には匕首が孝冬の足元に転がっていた。
事件の後始末と使用人への感謝
男は警察に引き渡され、孝冬と宇佐見は事情説明のため警察署へ向かった。屋敷に戻った鈴子は、女中たちに事件の概要を伝え、冷静に対応した。特に田鶴からは厳しくも愛情ある忠告を受け、安全への配慮を改めて認識した。後日、鈴子は由良と宇佐見に感謝の意を伝え、報奨として由良には休日、宇佐見には金一封を贈ることを決定した。
襲撃犯の正体とスエの陰謀
襲撃犯は、以前幽霊騒動を起こした女中スエの情夫であり、鈴子たちが武蔵屋に助言したことを逆恨みしての犯行であった。スエは昌江の悪夢を利用し、精神的に追い詰めた末に毒殺し、後妻に納まろうとする計画を立てていた。さらに惣兵衛をも殺害し、武蔵屋の財産を乗っ取るつもりであったが、計画は未遂に終わり、スエも逮捕された。
鈴子と孝冬の心情と信頼の深まり
事件の直後、鈴子は孝冬を案じて現場へ戻ったことを反省し、孝冬もその心遣いに感謝の念を抱いた。二人の間には一層の信頼が芽生え、互いの大切さを再確認する時間となった。由良とわかの間には心を通わせる場面もあり、鈴子はそれを温かく見守った。
昌江の悪夢の原因と決着
後日、昌江と惣兵衛が花菱邸を訪れ、昌江は悪夢の原因が父の亡霊にあると信じていたことを語った。夢の発端は、お盆にかつて父が自死した家の前に立ち寄ったことであった。昌江の申し出を受け、鈴子と孝冬は彼女と共にその家を訪れ、幽霊の正体に対峙することとなる。
廃屋での邂逅と淡路の君の介入
昌江の旧宅に足を踏み入れると、かつて父が母を殺し、自ら命を絶った座敷で血まみれの幽霊が現れた。しかし、その幽霊は淡路の君によって迎えられ、光とともに消滅した。床には父が破壊したとされる砂金石の破片が星のように散っており、過去の哀しみと執念の象徴として印象深い場面となった。
夢からの解放と昌江の再生
幽霊の消滅とともに昌江は解放され、明るい表情を取り戻した。彼女は自らの恐れや罪悪感を克服し、再び日常に戻る希望を得た。供養に向かうきっかけを与えたのは、鴻心霊学会の鴻八千代であり、宗教団体との新たな接点が生まれる伏線として示された。
鈴子の不安と崖上の人影
帰途に着く三人を、崖の上から誰かが見下ろしていた。鈴子はそれに気づかぬまま、心の奥にわずかな不安を残して家路についた。
崖上からの監視と八千代の動向
鴻八千代は鴻心霊学会の清充を伴い、日暮里の崖上から鈴子たちを密かに見下ろしていた。彼女は崖の端に立ちながら、鈴子と孝冬、そして昌江の姿をじっと見つめ、満足げな表情を浮かべていた。その行動は、あたかも花菱夫妻への強い関心と執着を示すものであり、特に鈴子に対して一方的な興味を寄せているようであった。清充はその様子に漠然とした不安を抱いた。
月見の夜と穏やかな語らい
花菱邸では中秋の名月を迎え、鈴子と孝冬が団子や秋の味覚を供え、静かな月見のひとときを楽しんでいた。英国製のテーブルに供えを飾る様子は和洋折衷の趣を漂わせ、二人は伝統行事に心を寄せて語り合った。孝冬は「片月見」を避けるべく十三夜の月も拝む意志を示し、季節の節目を大切にする心根が見て取れた。
御子柴の報告と銀六の過去
翌朝、孝冬は御子柴からの報告書を受け取った。それには、かねてより調査を依頼していた加藤銀六についての詳細が記されていた。加藤銀六は久我家分家と姻戚関係にある子爵・小松崎家で執事を務めていたが、夫人との不義を疑われて解雇された人物であった。主人の猜疑心によるもので、実際には冤罪であった可能性が高いとされた。
久我家との縁と浮かぶ遺恨の可能性
小松崎家、南条家、久我家分家はいずれも姻戚関係にあり、顔を合わせる機会があったと推察された。銀六が解雇後に貧民窟へ流れ着き、按摩と繋がりを持った可能性があり、その過程で南条とも接点があったのではと考察された。南条との関係性が浅からぬものであったならば、過去に遺恨を残した可能性も否定できず、そこに殺害の動機が潜んでいるのではと孝冬は推測した。
実秋との関係を否定したい思い
孝冬は、兄・実秋が事件に関与していないと信じたいがために、他者との遺恨という動機を探し求めていた。その感情は無意識下の願望となり、調査の方向性に影響を及ぼしていた。彼は自身の心情に気づきながらも、真相解明へと一歩踏み出す覚悟を固めていた。
鬼子母の実
わかの装いと観菊会の目的
鈴子は、由良に誘われ目黒へ菊見に出かける女中・わかのために、自身の手持ちの錦紗の小紋と帯を譲り、晴れやかな外出に送り出した。一方、自身も小松崎子爵邸で開かれる観菊会に出席することとなった。この催しは、加藤銀六がかつて勤めていた可能性のある華族の邸であり、また南条家との接点を探る機会としても適していた。観菊会は婦人限定であったため、孝冬は同行できず、鈴子は女中のタカと共に邸宅へ向かった。
小松崎夫人との接触と過去の使用人
観菊会の庭園は壮麗で、色とりどりの着物をまとった婦人たちで賑わっていた。鈴子は茶席で小松崎夫人と親しくなり、夫人が社交に不慣れな様子や、夫の嫉妬心から男性使用人を次々に解雇したことを聞き出した。加藤銀六の名を挙げて尋ねたが、夫人は記憶していない様子であった。また、南条家の名にも覚えがないと語った。
鴻八千代との再会と対立
観菊会の場に現れた鴻八千代は、鈴子の南条家に関する発言を耳にし、助力を申し出たが、鈴子は彼女の善意を疑い、冷ややかに拒絶した。さらに、昌江に対し実家に戻るよう助言した経緯を八千代は正当化したが、鈴子はそれを人の心を弄ぶ行為であると非難し、その場を立ち去った。タカの調査も成果を得られず、鈴子は疲労感を覚えつつ帰途に就いた。
鶯谷での調査と南条てるの死
翌日、鈴子と孝冬は五十嵐の情報に基づき、南条てるの住居を訪ねた。すでにてるは首を吊って亡くなっており、現在は是澤という作家が居住していた。てるの死因や背景ははっきりせず、是澤によると夫はほとんど帰宅せず、てるは孤独と苦労の末に命を絶ったとされる。
庭での幽霊目撃と淡路の君の出現
鈴子は柘榴の木の下に幽霊を目撃し、それが南条てるの霊と直感した。幽霊は淡路の君により吸収され、姿を消した。なぜてるの霊が座敷でなく庭に現れたのか、淡路の君がなぜ介入したのかは不明のままであった。
近隣住民の証言とてるの苦悩
近隣住人の証言により、てるが過酷な生活の中で子供の治療費を稼ぐため、赤ん坊の一時預かりをしていたことが明らかとなった。亭主はほとんど帰らず、彼女の心身は次第に疲弊していった。また、妹と名乗る若い女性が訪れていたことも判明し、姉を気遣う様子が語られた。
包装紙に残された手がかりと西国の繋がり
妹が持参していた土産物の包装紙から、淡路島の和菓子屋「寶榮堂」の名が確認された。これにより、妹が関西在住である可能性が示され、南条てるの過去や南条本人の情報を追う新たな手がかりとして浮上した。
南条てるの死の詳細と妹の存在
鈴子と孝冬は、南条てるが暮らしていた家の家主を訪ね、彼女の死とその後始末についての証言を得た。てるの遺体は夏の盛りに発見され、死後約一週間が経過していたという。亭主は家にほとんど帰らず、連絡先には妹「薗部らく」の大阪の住所が記されていた。てるの死後、らくの代理と見られる紳士が現れ、葬儀費用と家賃を全て支払っていた。
幽霊の目撃と少年の証言
鈴子は幽霊の出没した柘榴の木に興味を抱き、周囲の調査を進めた。そこで近所の少年から「赤ん坊の泣き声が木の下から聞こえる」という証言を得る。再度庭を訪れた鈴子と孝冬は、地面から浮かび上がる赤子の霊と泣き声を体験した。恐怖に震える鈴子を孝冬が支え、現場の異常さを改めて実感した。
赤子殺しの発覚と供養の申し出
その後の調査により、てるとその夫・南条は預かった赤子を殺害し、柘榴の木の根元に埋めていたことが判明した。骨の発見後、新聞報道によって社会的注目を集めることとなった。作家・是澤のもとには、若い女性が現れ、赤子たちの供養のためにと金包みを託した。金包みには「らく」と署名されており、薗部らくである可能性が濃厚となった。
銀六と南条の過去の接点
小松崎子爵夫人からの手紙と写真により、加藤銀六がかつて小松崎邸に勤めており、南条が客人として屋敷に出入りしていたことが明らかとなった。二人の直接の関係は不明だが、接点があったことは確かであり、南条が銀六に遺恨を抱いていた可能性も浮上した。
鈴子と孝冬の会話とらくの行方
らくの消息を追うため、薗部らくの写真を是澤や近隣住人に確認してもらった結果、彼女が確かに訪れていたことが判明した。身なりは垢抜けており、現在も東京近辺に住んでいると見られるが、連絡先は大阪の他人名義で記されていた。彼女が姉・てるの所業を知っていたかどうかは不明であった。
子供の証言と鈴子の感情
再訪した近隣の少年は「赤ん坊の泣き声がもう聞こえない」と語り、事件の終息を象徴するかのようであった。鈴子は男児に感謝の言葉を述べ、心の中で亡き赤子たちに祈りを捧げた。
手紙と焼き芋の夜
事件後、鈴子は精神的に疲弊していたが、孝冬が持ち帰った焼き芋に心を癒された。五十嵐とのやり取りや孝冬のさりげない気遣いに、二人の絆が深まる描写が重ねられた。翌朝には是澤からの電話が入り、「らく」と名乗る婦人の訪問が再度確認された。薗部らくは、確かに東京に存在していた。
再訪と供養の実現
鈴子と孝冬は再び鶯谷を訪れ、柘榴の木の下に供えられた玩具や花々を前に手を合わせた。らくの遺した金と人々の善意により、無縁仏となる赤子たちの供養が進められた。鈴子はてるの心情を思いやりつつも、すべてを理解することはできないまま、ただ深い悲しみに包まれていた。
南条とらくの関係、今後の探索へ
らくの居場所や南条との関係は未解明であり、孝冬と五十嵐は淡路島の親族に調査を依頼することにした。事件の発端とされる浅草の殺人事件、銀六と南条の関係、らくの役割、すべてがまだ霧の中にありながらも、鈴子と孝冬は歩みを止めず、真実を求めて進み続けていた。
鶯谷の酒屋訪問と意外な一致
孝冬は、南条てるがかつて住んでいた家の家主である酒屋を訪ねた。そこでてるの死後に葬儀の手配を行った紳士について確認すると、店主は記憶は曖昧ながら、写真を見せられてすぐにその人物が誰かを認識した。写真に写っていたのは、孝冬の兄・実秋であり、確信と困惑を抱いたまま孝冬はその場を後にした。
実秋の関与と兄への葛藤
車内で孝冬は兄・実秋の行動を思い返し、らくの恋人であったならば姉の葬儀を手配するのも不自然ではないと自らに言い聞かせようとした。しかし、てるが南条の妻であったこと、南条の存在が殺人事件に関わっている可能性があることが、孝冬の思考を複雑にした。彼は兄が関係していないことを必死に願いながらも、不安と疑念に心を覆われた。
不意の小包と機関誌『ともしび』
会社に戻った孝冬は、差出人不明の小包を受け取った。中には『ともしび』という白表紙の雑誌が入っており、それは八年前に発行された鴻心霊学会の機関誌であった。ページを開いた孝冬は、会員たちの集合写真の中に兄・実秋の姿を見出し、驚愕した。さらにその中には鴻八千代の父・鴻善次郎と、南条宏通の名も確認された。
写真が示す過去の繋がり
写真の下には「鴻心霊学会会員の名士たち」と記されており、そこに花菱実秋男爵、鴻善次郎、南条宏通の名が並んでいた。兄が霊学会の会員であり、南条とも面識があったという事実は、孝冬にとって耐えがたい衝撃であった。兄が知っていた南条に殺意を抱いていたのではないかという疑念が、静かに孝冬の中で膨らんでいった。
鈴子との距離と秘めた動揺
帰宅後、鈴子は孝冬の様子の変化に気づくが、彼は疲労を理由に会話を避け、書斎に籠もった。暗がりの中で、孝冬は兄が自分の知る人物とは異なる存在である可能性に苦しんでいた。実秋の過去や南条・鴻との関係に思いを巡らせながらも、鈴子にその事実を話すには早すぎると判断し、調査を優先する決意を固めた。
自問と決意
孝冬は、鈴子の前で取り繕いたくないという思いと、彼女を無用な不安に巻き込みたくないという思いの間で揺れていた。兄の真実を知るまで、そして自分が受け入れられるまで、語るべき時ではないと結論づけた。外は宵の闇に包まれ、鈴子の温もりを求める気持ちに駆られながらも、彼は静かにその場に留まり続けた。
同シリーズ



同著者のシリーズ
後宮の鳥




その他フィクション

Share this content:
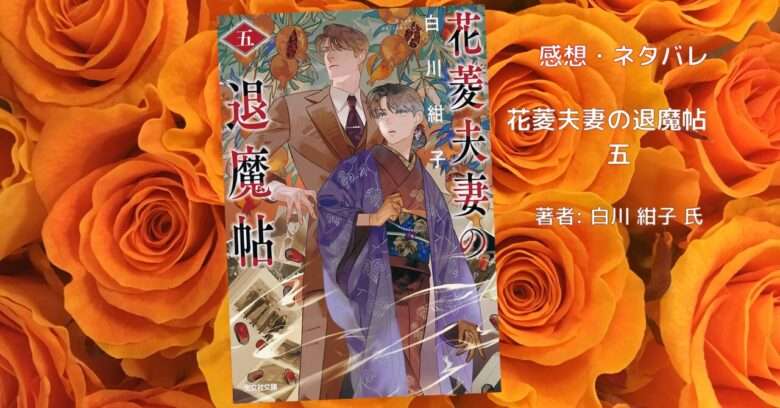

コメントを残す