本の概要
本書は、生成AIの進化によって変化する「努力」の概念を再定義し、効率的かつ効果的な成長戦略を提案するビジネス書である。著者は、ChatGPTを活用することで「頭の良さ」「経験」「センス」をコピーし、ラクをしながら成果を出す新しい努力の形を提示している。従来の「苦労して努力する」から「効率的にラクをする」へのパラダイムシフトを解説し、現代のビジネスパーソンに向けた実践的な指南書となっている。
著者プロフィール
• 伊藤 羊一(いとう よういち):武蔵野大学アントレプレナーシップ学部学部長、LINEヤフーアカデミア学長。次世代リーダー育成のスペシャリストであり、代表作に『1分で話せ』がある。
• 尾原 和啓(おばら かずひろ):IT批評家。京都大学大学院で人工知能を研究し、マッキンゼー、Google、楽天などで事業立ち上げや投資に携わる。著書に『モチベーション革命』『アフターデジタル』などがある。
書籍の特徴
• AI時代の新しい努力法則:ChatGPTの登場により、努力の質が変化し、効率的に成果を出す方法を解説。「頭の良さ」「経験」「センス」をコピーすることで、誰もが成長できる時代の到来を示している。
• 実践的な内容:ChatGPTを活用した具体的な方法や、ビジネスシーンでの応用例が豊富に紹介されており、読者がすぐに実践できる内容となっている。
• 著者の多角的な視点:異なるバックグラウンドを持つ二人の著者が、それぞれの専門性を活かし、多角的な視点でAI時代の成長戦略を提案している。
書籍情報
努力革命 ラクをするから成果が出る! アフターGPTの成長術
著者:伊藤 羊一 氏 尾原 和啓 氏
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
「ChatGPT使えねぇ」って舐めてない?
まだそんなシンドイ努力してるの?
このゲームチェンジに気づいていない人は、生き残れない!
ChatGPTを使えば、「頭の良さ」をコピーできる。「経験」もコピーできる。「センス」もコピーできる。誰もがラクをして楽しく成長しながら、多くのチャンスを手にきるようになる。
というより、これからはラクをしなければ、成果を出せない。
ChatGPTの登場によって起きた、「努力革命」というゲームチェンジ。
成長の方法も成功のあり方も180度変わってしまった世界をサバイブするための実践の書。
感想
ChatGPTの登場によって、「努力」の定義が大きく変化したことを、本書は説得力をもって伝えてくれた。
従来のように苦労や根性を積み重ねて成果を得るのではなく、「ラクをしながら成果を出す」という姿勢こそが、新時代の努力であるという主張に、素直に納得させられた。
と同時に、これができる世代が少しうらやましくも感じた。
本書の魅力は、単なるAIの礼賛にとどまらず、実践的な活用術に踏み込んでいる点にある。
「まずざっくり聞いて、じっくり深掘りしていく」「小分けにする」「選択肢を求めてみる」など、ChatGPTの思考補助としての特性を引き出す具体的な方法が紹介されており、読みながら「これなら自分にもできそうだ」と思わせる説得力があった。
特に印象に残ったのは、「80点はゴールではなくスタートである」という視点である。
この価値転換が社会に定着すれば確かに理想的だが、現実としてまだそのような環境に到達していない点には疑問も残った。
いわゆる「昭和的常識」がいまだ根強く残る世界線に生きている者としては、AI活用を全面的に受け入れるには心理的な壁も存在する。
しかしながら、その違和感すらも含めて、本書は読者に「今ここからどう変わるか」を問いかけてくる。
また、本書は「正解主義から修正主義へ」という大きな流れを提示しており、たとえ最初から完璧な答えが出せなくても、仮説と修正を繰り返す過程にこそ価値があるという発想は、とても前向きで救いがある。
失敗を恐れずに挑戦できる社会へのヒントが詰まっていた。
さらに「経験」や「センス」すらコピー可能な時代において、人間にしかできないことは何か、という問いも投げかけられている。
「飛ぶ力」や「やりたいことに従う勇気」といった、論理の外側にある感情や直感の重要性を強調する終盤には、強く共感した。
最後に、「すげー、やべー」と叫ぶことの大切さや、「好奇心の再起動」が学びと成長のきっかけになるという言葉には、不思議と背中を押された気がした。
ChatGPTはあくまで補助輪であり、そこからどう走るかは自分次第なのである。
補助輪チャリでイキるオッサンを想像したらシュールだわw
似合うようにチャリを変えるか、そう思われないように努力しよう。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
展開まとめ
はじめに──いま、努力革命が起きている!
ChatGPTによる努力の転換
ChatGPTの登場により、従来の努力の概念は大きく変化した。これまで苦労と根性が前提とされた努力に対し、AIの活用によって「ラクをしながら成果を上げる」という新たな形が可能となった。著者は、この変化を「努力革命」と定義し、旧来の努力では成果が出にくい時代に突入したと断言した。
成長の格差とチャンスの集中
現代社会では、頭の良さや経験、センスを持つ者にチャンスが集中し、同じ時間を費やしても結果に大きな差が生じていた。ChatGPTはそれらをコピー・活用するツールとして機能し、誰でも効率的に学び、成長できる手段となり得ることが示された。これにより、これまで差をつけられていた人々もチャンスを得られる環境が整ってきた。
ChatGPTの本質と利用の心構え
ChatGPTは正解を求める厳格な教師や上司ではなく、誰にでも使いやすい優秀なパートナーであるとされた。正確なプロンプトを追い求めるより、まずはざっくりと使ってみることが重要であり、その過程で学びが生まれる。AIを恐れず、気軽に接する姿勢こそが成長の鍵であるとされた。
著者の背景と実践からの知見
本書は、実践的に成長支援を行う伊藤羊一と、新しい技術を事業や行動に変換してきた尾原和啓の共著である。両者ともに自身の方法論を大きく見直し、AI時代にふさわしい成長のあり方を追求した。その過程で得た知見と行動の変化が、本書の内容に結実している。
本書の構成と目的
本書では、AIによって世界にもたらされた3つのゲームチェンジと、個人の成長に関する6つのゲームチェンジが紹介されている。読者がこれらの変化に乗り遅れることなく、自らの成長を楽しむための実践的なコツや事例を、具体的に解説している。また、ChatGPTの使用経験がある読者に対しても、思考の転換を促す内容が含まれており、すぐに日常に取り入れられる実用性が重視された。
序章 ChatGPTがもたらした3つのゲームチェンジ
合格ラインの変化と「ワクワク価値」への移行
ChatGPTをはじめとした生成AIの登場により、ビジネスにおける仕事の基準は大きく変化した。従来は80点を取ることが「合格ライン」とされていたが、AIの導入によってその80点は人間が担うべき領域ではなくなり、単なるスタート地点に格下げされた。AIは議事録作成やスケジュール調整、プレゼン資料の原案作成といったタスクを自動で処理し、人間はAIが生成した成果物に修正や補完を加えるだけでよくなった。したがって、人間の仕事は「ワクワク価値」、すなわち顧客に感動を与えるレベルの付加価値を生み出すことに移行した。この変化は、従来の「優秀さ」の定義を覆すものであり、正確にこなす力よりも創造性や共感力が重要視されるようになった。
個別化による教育とビジネスの再構築
ChatGPTは個別化対応が可能であり、質問者の前提知識や関心に応じて柔軟に回答を変化させる。この特性は教育現場にも大きな影響を及ぼし、集団授業の一律化から、一人ひとりの学習進度や理解度に応じた最適な説明への転換を促した。学習者は自らに合った説明をAIに求めることで、理解の段差を克服できるようになった。さらにビジネス領域においても、社員ごとの適性に合わせたマニュアルの作成や、顧客一人ひとりに最適化されたセールス文の生成が可能となった。このように、個別化が進むことで、教育や企業活動のあり方は根本から再構築されつつあった。
正解主義から修正主義への価値転換
AIが高精度な「80点解答」を即時に提示する時代において、正解を一発で導く能力だけでは通用しなくなった。求められるのは、不完全な試行から軌道修正を繰り返し、よりよい結果を導く修正主義的な姿勢である。この変化に適応できない者はAIと競合し、成果を上げられずに消耗していく。一方で、自分の興味や好きを原動力に尖ったアウトプットを出せる者は、社会で成功の機会を広げていった。動画配信やSNSによる発信が社会的成功に直結するようになった現代においては、従来型の正解重視のキャリアでは報われにくくなりつつある。
努力の構造の「逆転」と今後の展開
これまで努力とは、時間をかけて「頭の良さ」「経験」「センス」を積み重ねることとされてきた。しかし、ChatGPTはそれらを容易にコピー・活用できる手段を提供するため、努力の方向性そのものが逆転した。これに伴い、成長のための方法も「常識」とされてきた枠組みを脱却する必要が生じた。本書では第1章から第4章にかけてChatGPTを用いた成長戦略を具体的に解説し、第5章では新しい学びの形を示し、第6章以降ではAIには代替できない人間固有の力の育成法について述べている。これらを通じて読者に「逆の常識」へのアップデートを促している。
第1章 ChatGPTで壁打ちする
ChatGPTによる壁打ちの有効性
著者は、ChatGPTの活用方法として「壁打ち」という思考整理手法を提案した。これは、ざっくりとした問いを投げかけ、返答を受けてさらに深めることで、自らのアイデアを構築していくプロセスである。ChatGPTは、ITに不慣れな者でも扱いやすく、仕事や学習に汎用的に役立つ壁打ちの相手として機能しやすかった。
ChatGPTは正解を探す道具ではない
ChatGPTは検索エンジンとは異なり、既存の情報を探すものではなく、学習した知識をもとに新しい内容を生成するツールである。正解を求める使い方では本来の力を発揮できず、共創的対話に活用することで初めてその価値が生まれるとされた。
問題解決のための五つのステップ
ChatGPTによる壁打ちは「ざっくり → じっくり」の五段階で進めるとされる。まずはざっくり質問し、次に問題を小分けにし、そこから具体的な打ち手を考え、絞り込みを行い、最後にじっくりと質問を繰り返す。このプロセスを通じて、漠然とした課題も具体的に分解され、実行可能な施策が導き出された。
絞り込みとプロンプトの工夫
ChatGPTから有益な回答を得るには、問いに前提や制約条件を加えることが重要とされた。自身やChatGPTの役割設定、対象読者やアウトプットの目的を明確にすることで、回答の精度が高まり、期待する情報に近づけることが可能となった。また、観点の多様化や抽象度の調整によって、多面的な検討も可能であると示された。
深津式プロンプトによる効率化
note株式会社のCXOである深津貴之が提唱した「深津式プロンプト」は、壁打ちの流れをテンプレート化したものである。命令書・制約条件・入力文という構成により、初動の精度が高まり、より目的に適した出力が得られやすくなる仕組みであった。これは壁打ちのプロセスを明示的に埋め込むことで、効率的な対話を可能にした。
ChatGPT使用時の留意点
ChatGPTは開発途上の技術であるため、使用にあたって以下の注意点が挙げられた。第一に、誤情報や虚偽の内容を含む可能性があり、情報の信頼性を常に確認する必要があった。第二に、2024年4月時点では2022年1月までの知識しか持たないため、時事的情報には制限がある。第三に、学習データの偏りから、英語圏情報に基づいた回答が中心となる場合がある。第四に、著作権の取り扱いについても注意が必要であり、生成された文章の二次利用には確認が求められた。入力内容も学習に利用され得るため、企業利用では情報管理上の配慮が必須であるとされた。
この章全体を通じて、ChatGPTの活用は「問いを洗練させながら共に思考を深めるプロセス」であり、技術の利便性を理解しつつも批判的思考と慎重な運用が求められると論じられていた。
第2章「頭の良さ」はコピーできる
頭の良さの構造とChatGPTの可能性
頭の良さとは「引き出しの多さ」と「つなげる力」に集約されると定義された。従来は努力と時間により培われるものであったが、ChatGPTの登場によって誰でも簡単にこれらを獲得できるようになった。ChatGPTは自然言語を介して情報を呼び出し、推論エンジンとして機能するため、複数の知識をつなぎ意味を見出す能力を支援するツールとなった。
自分ごと化と意味ある情報の導出
優れた思考者は情報を「自分ごと」として捉え、事象を仮説へとつなげる力を持っていた。マッキンゼーの「空・雨・傘」フレームワークはこの発想法を象徴し、事象から有用な意味を引き出す構造を示した。ChatGPTを活用すれば、誰もがこの仮説構築の手法を実践可能となることが示された。
抽象化と転用の自動化
前田裕二が提唱した「ファクト → 抽象化 → 転用」の思考法も、ChatGPTによって容易に実践できるようになった。たとえば「スターバックスの行列」という事象を抽象化し、体験価値やブランド志向といった概念に変換した上で、それを他業界や仕事に転用するというプロセスが自動的に支援されるようになった。マルチモーダルAIの発展により、今後は画像などの非テキストデータからも意味ある情報を抽出できる可能性が示唆された。
抽象化と具体化による思考の深掘り
思考を深める鍵は「つまり?」による抽象化と「たとえば?」による具体化の往復にあるとされた。個別の出来事を抽象化して大きな傾向を導き、それを裏づける具体的情報を探ることにより、理解が深化する。ChatGPTはこのプロセスを補助し、質問を通じて思考を拡張させるツールとして活用された。
問題の特定と小分けによる解決
問題解決において最も重要なのは「問題の正体を特定すること」であると強調された。ChatGPTに原因を列挙させ、再生成機能を使って納得できる要因を特定し、さらに分解することで問題の核心に迫る手法が提案された。この小分けによる可視化は、課題を自然に解決可能な単位へと導いた。
センターピン思考と優先順位の見極め
複数の課題に対処する際は、中心となる「センターピン」を見つけることが重要とされた。ChatGPTに段階的な質問を投げかけることで、複数課題に同時に作用する最も効果的な解決策を導出する手法が提示された。これはビジネスにおける時間効率と成果最大化に寄与する考え方であった。
仮想ディスカッションと視点の多様化
ChatGPTを活用すれば、名経営者を模した仮想ディスカッションを行うことも可能であった。異なる立場や思考法を取り入れることで、新しい視点を得られ、壁打ちの幅が広がる効果が期待された。さらにChatGPT自身に思考のプロセスを説明させることで、論理的な引き出しの増強にも繋がった。
制約条件の最適化と論理補強の支援
良質な出力を得るためには、前提や制約条件の追加が有効であった。ChatGPTに「何が足りないか」を尋ねることで、よりよい質問設計が可能となり、回答の品質向上が促進された。また、学者の理論を引用させることで新しい切り口を見出すなど、論理的視点の拡充も図られた。ChatGPTの出力には事実誤認も含まれるため、外部での裏付けが必要とされたが、思考補助としての有用性は高く評価された。
第3章「経験」はコピーできる
下積みの価値の変容とAIの役割
従来の日本企業では、新人が下積みから始めて経験を積み、昇進するというキャリアパスが一般的であった。しかし、AIが80点までの仕事を担うようになった現代において、そのような下積みは意味を持たなくなりつつある。たとえば、Microsoft 365 Copilotのようなツールを用いれば、会議の要点や担当業務を自動で把握でき、理解が追いつかない内容も質問することで即時に教示されるようになった。将来的には、ウェアラブルデバイスを通じて、発言の意味もリアルタイムで提示される可能性があると示唆された。
職人技の「見える化」と習得の加速
寿司職人の修業に象徴されるように、従来は長年の経験により技術を習得する必要があったが、現在ではYouTubeや料理教室などを通じて技術が広く共有されている。ChatGPTの拡張機能を活用すれば、動画からマニュアルを作成することも可能であり、これにより職人の「目」や「技」も可視化され、効率的な学習が実現された。重要なのは、標準化された作業は早期に習得し、より創造的な領域に時間と労力を投資することであった。
ノウハウの数値化と再現可能性
著者の知人である岩佐大輝が、イチゴ栽培の技術を数値化し高品質なイチゴの量産を可能にした例が紹介された。これは職人の経験を形式知化し、多くの人が再現可能にした実例であり、経験のコピーが生産性を高めることを示している。ただし、経験そのものの意味が失われたわけではなく、形式知と創造的経験のバランスが重要であるとされた。
無意味な下積みと「アリバイ仕事」の批判
企業に残る形式的で意味を持たない業務、たとえば「お辞儀ハンコ」や不要なZIPファイル送信、目的不明の商談などは、「アリバイのための仕事」として批判された。これらは価値を生まず、単にその場に居ることを目的化した仕事であり、日本の生産性低下の要因とされた。実際に日本の時間当たり労働生産性はOECD加盟国中でも下位に位置している。このような環境下では、若い世代が旧来の慣習に縛られず成果を上げやすい状況にあると結論づけられた。
憧れのリーダーの思考法の模倣
ChatGPTを用いることで、著名なリーダーの思考パターンを模倣することが可能となった。著者は実際に孫正義やキング・カズ、三枝匡といった人物の思考を想像し、自身の意思決定に応用してきた。ChatGPTを活用すれば、インターネット上の情報を編集・統合し、自分の置かれた状況に合わせたアドバイスを仮想的に受け取ることができる。この手法は時間も費用もかからず、個別最適化された思考支援を可能にした。
完全模倣による思考のトレース
編集者の箕輪厚介が行っている「完コピ」も紹介された。尊敬する人物の言動を徹底的に模倣することで、その人の思考パターンを自らに取り込むという方法である。人間の思考が言葉で構成されている以上、その人の言語を完全に再現することで思考の模倣が可能となる。ChatGPTはこのプロセスを大幅に短縮し、人物の経験や知見を迅速に吸収する手段となった。
第4章「センス」はコピーできる
生成AIによる創作の加速とその影響
音楽制作の分野では、生成AIがわずか30秒で3分の楽曲を生成し、何千通りものアレンジを可能にした。中国の大手ストリーミング企業によるAIボーカル楽曲は1億回再生を突破し、注目を集めた。この技術は、過去の楽曲を学習し、新たなメロディを生み出すという形で進化している。同様の進展はアートや脚本の世界にも及び、画像生成AIが芸術賞を受賞したり、脚本家がAIに対して危機感を示したりする事例も見られた。かつて人間特有とされた「センス」が、AIによって再現・拡張されつつある現実が明らかとなった。
センスとは「圧縮体験」によって形成される
茶道や美術鑑定のように、センスは膨大な判断の蓄積、すなわち「圧縮体験」により培われる。SNSの普及により、写真や動画を日常的に大量に見ることで、誰でも自然と審美眼を養えるようになった。生成AIはこのプロセスをさらに高速化し、写真や動画だけでなく、アイデアの生成においても膨大な「叩き台」を瞬時に提供することで、センスの習得を支援した。
量産によるSSRアイデアの発掘と共有
画像生成AIによるデザイン案の大量生成は、従来の「数案から選ぶ」手法を凌駕した。関係者の意見を引き出すためにも叩き台の量産は有効であり、初期案の不完全さを前提に磨き上げていくことで、優れた成果に至る確率が高まるとされた。このプロセスは、いわば「SSRが出るまでガチャを回す」ようなものであり、試行回数そのものが成功の鍵となると結論づけられた。
開発プロセスの変化とDCPAの優位性
ビジネス領域においては、計画重視のPDCAではなく、実行優先のDCPAモデルが有効とされた。ベータ版を市場に出し、ユーザーからのフィードバックを反映しながら製品を磨く手法がインターネット業界で主流となっており、今後は全産業に広がると予測された。生成AIの登場により叩き台が即座に用意できることが、この変化を後押ししている。
多産多死戦略とビジネスの進化
生物学における多産多死の進化論が、ビジネス戦略と重なる構図として示された。膨大な試行を重ねる中で成功するアイデアが生まれ、イノベーションの芽が育つとされた。TikTokを成功させたバイトダンス社も、多様なアプリを試作・市場投入しながら成功領域を絞り込んだ結果、ショート動画に辿り着いた事例である。
失敗を恐れず反復する姿勢の重要性
アマゾンの成功は、革新的なアイデアではなく、継続的なイテレーションにあったとジェフ・ベゾス自身が語っていた。DCPAの実行数こそが競争力の源泉であり、失敗の多さがむしろ成功確率を高める。失敗から学び、それを共有できる人材が今後高く評価されるようになるという社会的変化も示唆された。
イノベーションは組み合わせから生まれる
イノベーションは既存の要素同士の「新結合」によって生まれると定義され、回転寿司や孫正義の発想法などが例示された。ChatGPTはこの組み合わせ思考にも有効であり、食材や概念の組み合わせを提示させることで、新しい価値を生み出す手段として機能することが示された。
アナロジー力と抽象思考の活用
アナロジー、すなわち異なる物事の共通点を見出す力は、ビジネスセンス向上に直結する能力であるとされた。ChatGPTは、この類推力を育てるための思考訓練の道具としても有効であり、成功と失敗、自由と束縛のような対義語の関係性を問い直すことで、新たな発見が得られるとされた。
クリエイティブ経済における個人の優位性
AI時代の到来により、消費者とクリエイターの境界が曖昧になるクリエイティブ経済が拡大している。ChatGPTの活用により、少人数や個人でも高度な企画・制作・販売が可能となり、従来の大量生産・大量消費型のビジネスモデルよりも、個別性とスピードに富んだ個人や小規模事業者が有利になる構図が形成された。今後は、熱量の高いコミュニティを持つ個人が経済を動かす存在となっていく。
第5章 ChatGPT時代の学び方
受験制度の意味の消失と教育の再定義
従来、安定した職業に就くために受験勉強が重視されてきたが、企業の寿命が短くなる中で「安定」は保証されなくなった。教室の定員という物理的制約によって存在していた入学試験も、オンライン講義の普及により不要となりつつある。世界中の大学が提供するMOOCにより、希望者全員が講義を受けられる環境が整いつつあり、さらにChatGPTの登場により、講義の難易度を個別に調整できるようになったことで、教育の形態が大きく変化した。
自発的な学びの時代の到来
学ぶべきタイミングは個々人によって異なり、自身の興味や必要性に気づいた瞬間が最も効果的な学習の開始点であるとされた。生成AIの台頭により、学習コストは劇的に下がり、誰もが「今こそ学びたい」と思ったときに、最高水準の教育にアクセスできるようになった。この変化は、単なる教育の機会の拡大にとどまらず、人間の学びの在り方そのものを刷新した。
学習プロセスの最適化とパーソナライズ
第二言語習得において提唱される「気づき→理解→内在化→統合」の4段階モデルに照らし、ChatGPTはそのプロセスを加速させる役割を果たした。海外旅行先で即座に必要な表現を教えてもらい、実践に移すという体験を通じて、効率よく学習が進む構造が成立した。学ぶ内容もスピードも個人に最適化でき、理解できるレベルへの調整や、適切な教材の提示によって、より深く柔軟な学習が可能となった。
フロー状態と学びの楽しさの両立
人が「不安」と「退屈」の中間にあるとき、最も夢中になれる状態、すなわち「フロー」に入りやすいとされている。ChatGPTは、学習者の習熟度や興味に応じて難易度を調整し、自然なフロー状態に導くことで、学びをゲームのように楽しいものへと変化させた。このような状態では、学習が努力ではなく娯楽となり、自発的な成長が促進された。
スキル獲得の意義の変化
従来、「食いっぱぐれない」ためには特定のスキルを学ぶべきだとされていた。しかし、生成AIがノーコード・ローコード開発を可能にし、法律や会計のような専門分野にも代替が進む中で、「スキルを身につける」という考え方自体が形骸化しつつある。ユーザーが自然言語でAIに指示を出すだけで、ほとんどの作業が完結する時代が到来し、スキルの定義が根本的に問い直される状況となった。
言語の壁の消滅と情報収集の革新
YouTubeの自動字幕機能やChatGPTによる要約・翻訳機能により、海外の動画や情報を母国語で迅速に理解できるようになった。特にBBCやアルジャジーラなどのチャンネルを活用することで、日本のメディアでは報じられない国際ニュースにも容易にアクセス可能となり、情報取得の質と視野が飛躍的に向上した。
自分だけの大学院の構築と世界最高峰へのアクセス
YouTubeやChatGPT、Chrome拡張機能を活用することで、世界の大学やカンファレンスの知見に自宅からアクセスできるようになった。代表的なMOOCにはCoursera、edX、Udacity、MIT OCW、Khan Academyなどがあり、英語の壁も音声文字起こしと翻訳ツールで克服可能である。高い学費や入試を突破する必要なく、意欲と少しのツール活用で、誰でも世界最高水準の学習環境を手に入れられる時代が到来した。学ぶか否か、学びをどう活かすかで、今後の格差が生じていく構図が明確に示された。
第6章 それでもコピーできないものがある
AIが持ち得ない「飛ぶ力」
論理的思考力や合理性はAIによってほぼ完全に再現可能であるが、人間が持つ「飛ぶ力」だけは模倣できなかった。この力は、明確な根拠を超えて直感や信念に従い、論理の外に跳躍する判断力を指す。孫正義は、赤字を出しながらも果敢に投資やM&Aを進め、スティーブ・ジョブズも直感に従った決断を重視していた。これらの非合理な判断こそが一流のリーダーに共通する資質であり、未来に正解が存在しないからこそ、人は自らの信念に基づいて意思決定する必要があった。
論理では導けない意思決定の本質
意思決定に際し、項目ごとの○×表を作る手法が多用されてきたが、それは単なる情報整理であり、判断そのものではなかった。○×の内容は前提条件によっていくらでも変化するため、最終的な決断は表の情報を踏まえた「飛び」によって下される。AIが情報整理や選択肢の比較を担うようになる時代において、人間に残された役割は、「覚悟を持って選び取ること」であり、リーダーの本質はそこにあるとされた。
思考の質的変化と人間の役割
AIによって業務支援が高度化した結果、人間の思考力が低下するとの懸念が生まれたが、筆者は思考の内容自体が変化していくと論じた。今後、人間に求められるのは、AIの示す提案に対して自分の信念や未来志向をもとに判断し、時にそれに逆らう決断を下す力である。そのためには「やりたいことに従う」姿勢が不可欠だが、正解主義に慣れた人々には難しく、自らの内面と向き合う作業が必要とされた。
「軸」を育てる対話と内省の重要性
LINEヤフーアカデミアでは、参加者が自分の「軸」を見つけることに重きを置いていた。対話による思考の深化を促すカリキュラムを通じ、出来事を振り返り、それが自分にとってどんな意味を持つかを言語化することで、内面の価値観に気づくことができた。インプットとアウトプットを繰り返すことで初めて「気づき」が得られ、その積み重ねが自己の軸を形作る基盤となった。
停滞の原因はアウトプット不足
成長が止まったと感じるとき、多くの場合インプットではなくアウトプットの不足が原因であった。知識は外に出して初めて定着し、思考の整理につながる。LINEヤフーアカデミアでは対話によるアウトプットを実施し、個人でも日記やSNSによる表現が推奨された。悩みの言語化もアウトプットの一環であり、壁打ちによって思考の可視化が進み、問題解決の糸口を見出せるようになるとされた。
ChatGPTを壁打ち相手にする新しい学びの形
ChatGPTは、専属コーチのように対話相手となり、ユーザーが自己の価値観や課題と向き合う手助けを行った。「コンディションの確認」や「KPT法」などを通じて、振り返りを習慣化し、改善のヒントを得ることが可能であった。また、ソクラテス式問答法を活用することで仮説思考を鍛え、問題の核心に迫る対話が実現された。ユーザーがモヤモヤした感情をそのまま投げかけても、ChatGPTは的確に言語化を補助し、思考の整理を支えた。
「How are you?」の問いかけがもたらす思考の起動
日常的な挨拶である「How are you?」には、思考を内省へと向かわせる仕掛けが含まれていた。相手の問いかけに答えることで、自分の状態に意識を向け、言葉にする訓練が自然と行われていた。1on1ミーティングも同様に、問いかけによる言語化が核心であり、ChatGPTとの対話を通じてその習慣は一人でも継続可能であった。
好奇心を再起動する「すげー、やべー力」
インプットが不足する原因の一つとして、好奇心の低下が挙げられた。その対処法として、身の回りの物事に対して無理にでも「すげー!」「やべー!」と声に出して反応する「すげー、やべー力」が紹介された。この言葉の反復が心の感受性を呼び覚まし、自分の興味関心を再起動させる効果をもたらした。
マインドフルネスがクリエイティビティの源泉となる理由
人は現実のわずか30パーセントしか見ておらず、多くは過去や未来への不安に囚われていた。マインドフルネスは「今、ここ」に意識を向けることで、モヤモヤから解放され、目の前の出来事に敏感になる力を取り戻させた。この状態こそがクリエイティビティの起点であり、現実世界にワクワクを取り戻すための基本的な姿勢であるとされた。
第7章「やるべき」でなく「やりたい」を起点に
自分の「やりたい」を起点にした行動の連鎖
人は必ずしも最初から自分の「やりたいこと」が明確なわけではなく、多くは「やるべき」という外部の動機で動き出す。しかし壁打ちを続けることで「やりたい」に出会い、これを軸に行動すれば、共感が生まれ、仲間が集まり、現実が動き始める。マーケティング主導の多数派に迎合するのではなく、個人の世界観に基づく価値提供が、これからのビジネスを支える循環となることが示された。iPhoneの成功も、マーケットの声ではなく、ジョブズの内発的な欲求に基づいていた。
「欠乏の充足」から「欲望の創出」へ
過去のビジネスは「存在しないもの」を補う形で展開されたが、現代では多くの基本的なモノが行き渡り、物理的欠乏は希薄になった。これにより、つくり手の内なる欲求、すなわち「これがつくりたい」というビジョンが出発点となる。AppleのVision Proは、新しい欲望を喚起し、共感を呼ぶ未来像として人々を惹きつけた。顧客に「何が欲しいか」と問うよりも、自らの熱を形にすることが求められる時代へと移行した。
行動の原点は「なぜやるのか」という動機
マーケティングにおいて「アウトサイド・イン」が主流だったが、ChatGPTの登場により、市場調査は誰でも可能となり、その価値は相対的に低下した。今後は「インサイド・アウト」、すなわち内なる声に従って行動する力が重要になる。サイモン・シネックのスピーチにもあるように、人を動かすのは「何をするか」ではなく「なぜやるか」という思いであり、情熱に共感したときに人の心が動く構造が強調された。
パーパス経営と「Why」の優先順位
企業経営においても、「なぜそれをやるのか」という存在意義の明確化が重視されている。経済同友会の提言でも、イノベーション創出の鍵として「自社の存在意義」が最初に挙げられており、手段の前に目的を問う順序が強調された。Nikeがリスクをとって掲げた広告のように、フィロソフィーを明確にすることが、社会的な共感と成果を生む鍵となった。
スキルの目的化に対する警鐘
武蔵野EMCでは、学生が夢を語り、それを実現するプロセスの中で必要なスキルを学ぶことが重視されている。スキルはあくまで手段であり、本来は「こうなりたい」という思いが出発点であるべきであった。しかし実際には、スキルを身につけること自体が目的化し、安心材料として追求されがちである。そのような手段の目的化は、人生の本質的な動機を曇らせる要因となる。
組織構造の変化とヨコ型マネジメントの必要性
従来の日本企業はタテ型組織を基盤とし、命令系統に従うことで動いていたが、変化の激しい現代では柔軟な対応が求められる。情報共有と自律的行動が可能なヨコ型組織こそが、競争力を持つ。役職による権威ではなく、対話と共創によって場をつくり出し、目的に向かって協働する力がマネジメントにおいて不可欠とされた。
人材の競争優位性は「偏愛」へと移行する
かつて人材の優位性は筋力にあり、次いで頭脳に移行したが、現在はAIによって頭脳労働すら代替可能となった。次に問われるのは「偏愛」、すなわち個人が心から好きでこだわる対象を持つ力である。AIと同じ土俵で仕事を競うのではなく、自らの情熱と興味を軸に、新しい道具を活用して可能性を拡張することが、人間の競争優位性の本質であると結論づけられた。
第8章 普通の人だってこんなに高くまで行ける
起業家に共通する「クレイジーキルトの原則」
優れた起業家には、自らの「やりたいこと」を起点に人や技術を結びつけ、新たな事業を創出するという共通点があった。これを「クレイジーキルトの原則」と呼び、生成AIの普及によってその実現はさらに容易になっていた。小さな発信が共感を呼び、仲間と共に形となり、熱量が広がっていくことで、現実化の速度が増していった。
「やりたい」から始まる起業と「わらしべ長者」的発想
身近な課題を出発点にした個人の工夫が事業へと発展する事例が紹介され、これまでのような明確な事業計画による起業家像からの脱却が提案された。「わらしべ長者」のように、目の前の小さな機会を積み重ねることで大きな成果に繋がるという考え方が奨励された。重要なのは、自分自身の「これ、やりたい」に忠実であることであった。
キャリアにおける「逆算思考」からの脱却
キャリアを逆算して設計する発想には限界があり、予測不能な変化に柔軟に対応する姿勢が求められていた。そのためには仮置きのゴールを設定し、漂流するように柔軟に進路を変えながら、キャリアアンカーを指針として行動する「キャリアドリフト」の考え方が有効とされた。
「好き」を起点にしたマネタイズの実現
好きなことだけで生計を立てるのは容易ではないが、人が集まり共感が得られる場には自然とマネタイズの可能性が生まれるとされた。Yahoo!の例を挙げ、実用的なサービスが発展し収益化された経緯が説明された。個人が発信力を持ちやすくなった今、SNSやVoicyなどの活用により、小規模な発信でも価値が広がる環境が整っていた。
情報発信の基本構造とSNS活用法
SNSにおける効果的な発信は、「情報」「意見」「日記」の順番で行うことが重要であった。最初は有益な情報を提供し、徐々に意見を述べ、信頼が蓄積された段階で日常的な内容を発信することが推奨された。また、ChatGPTを活用して効率的なコンテンツ制作が可能であり、情報発信を習慣化する際の有力な補助ツールとされた。
一歩踏み出す勇気と「装備」の後調達
変化の激しい時代には、あらかじめすべてを準備するのではなく、行動しながら必要な装備を整えていく柔軟性が求められた。ChatGPTはその補助役として機能し、不確実な未来に対して「センスメイキング理論」に基づいた理解共有が成功の鍵であるとされた。
レゴ的発想と仮説的推論「アブダクション」
ビジネスや思考のスタイルは、あらかじめ決まった正解を目指すジグソーパズル型から、自由に組み替えるレゴ型へと変化していた。この発想転換に伴い、アブダクションという仮説的推論を重視し、試行錯誤を繰り返しながら進む柔軟な思考が重要とされた。
不安と痛みに伴う変化のプロセス
「やりたい」を実行に移すには不安と痛みが伴い、初期段階では孤独や評価の低下も避けられなかった。しかし、そうしたプロセスを経て学びと喜びに到達することで、真の成長が可能になるとされた。変化を恐れてコンフォートゾーンに戻るのではなく、未来に向けた挑戦を続けることが強調された。
正解よりも共感と行動を重視する時代へ
選択が正しいか否かは誰にもわからず、むしろ大切なのは「好き」を原動力に一歩を踏み出すことであった。仲間や共感者は後から現れ、ChatGPTのようなツールに支えられながら、普通の人でも高くまで登ることができる時代が訪れていた。
その他フィクション

Share this content:
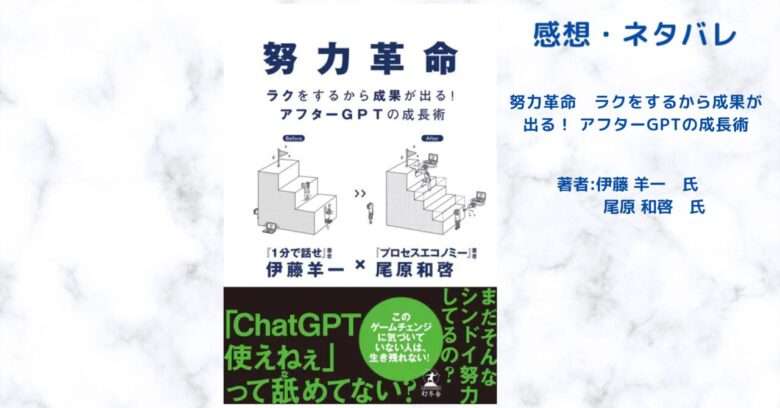

コメントを残す