物語の概要
ジャンル:
時代小説・歴史劇である。本作は江戸時代を舞台に、“侍火消し”として知られた松永源吾が、新たに羽州新庄藩の火消し組を再建するために奮闘する姿を描いた群像劇である。
内容紹介:
かつて「火喰鳥」と呼ばれ、江戸一の侍火消しとして名を馳せた松永源吾であったが、ある火事の責任を負い、浪人となってしまった。そんな中、羽州新庄藩からの招聘を受け、壊滅状態にあった藩の火消し隊の再建を命じられることとなる。予算も人手も乏しい“ぼろ鳶組”を率いて、源吾は再び火事場に立ち向かい、仲間たちと共に江戸の街に立ちはだかる数々の災厄と陰謀を乗り越えていく。
主要キャラクター
- 松永 源吾(まつなが げんご):本作の主人公であり、かつて江戸最強と謳われた侍火消「火喰鳥」。浪人を経て羽州新庄藩の火消し組頭に就任し、“ぼろ鳶組”を率いて再起を図る人物である。
- 寅次郎:元力士の鳶人足であり、源吾に誘われて“ぼろ鳶組”に加わる力強い新メンバー。火消しとしての未経験ながら、その腕力と武勇で現場を支える。
- 彦弥:現役の軽業師出身で機敏な身のこなしを持つ鳶職。跳躍力を活かした活動で鳶仕事に取り組む、“ぼろ鳶組”の異色の若手である。
- 星十郎:風読みの技術を持った学者肌の青年。元火消しだった父の影響もあり知識と冷静な判断力を武器に、チームの知恵袋的存在として活躍する。
物語の特徴
本作の魅力は、「火消し」という職業を通じて描かれる男たちの再生と覚悟、そして“再起”のドラマにある。崩壊した藩の火消しを再建するという重責を背負った“ぼろ鳶組”の面々が、それぞれの過去や挫折を抱えながらも火事場での活躍を通じて己を取り戻していく姿が胸を打つ。また、江戸の大火や陰謀による人為的な放火といった火の恐怖と、火消しとしての誇りとの対比が、炎の描写を通して作品全体に緊張感と情熱を与えている点が、本作を単なる時代活劇や歴史小説と一線を画している。
書籍情報
火喰鳥 羽州ぼろ鳶組
著者:今村翔吾 氏
出版社・レーベル 伝社文庫(祥伝社)
発売日:2017年3月15日
ISBNコード:9784396342982
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
2017年啓文堂書店時代小説文庫大賞受賞!
一気読み間違いなし! 炎より熱い、侍火消の物語
かつて、江戸随一と呼ばれた武家火消がいた。その名は、松永源吾。別名、「火喰鳥」――。しかし、五年前の火事が原因で、今は妻の深雪と貧乏浪人暮らし。そんな彼の元に出羽新庄藩から突然仕官の誘いが。壊滅した藩の火消組織を再建してほしいという。「ぼろ鳶」と揶揄される火消たちを率い、源吾は昔の輝きを取り戻すことができるのか。興奮必至、迫力の時代小説。
感想
アニメ化の話を聞き、興味を持って手に取った『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』。
火消しの物語と聞いていたけれど、武士が火消しをするという設定にまず惹きつけられた。
江戸の火消しといえば、町火消のイメージが強かったから、武家火消という存在を知り、新鮮な驚きがあった。
物語には、火付盗賊改方の長谷川平蔵も登場する。しかし、私が知っているアニメの長谷川さん(まるでダメなおじさん、略してマダオ)とは全く違う、凛々しい姿だった。
権力の中枢に近い場所にいながら、思うように権力を行使できず、嫌な因縁をつけられて破滅へと向かいそうな危うさを常に抱えている。
その状況が、なんとも言えない感情を呼び起こす。
武士としての誇りと、組織の中で生きる難しさ、その狭間で葛藤する姿が、胸に迫ってくる。
主人公である松永源吾は、かつて「火喰鳥」と呼ばれたほどの腕利きだった。しかし、過去の出来事が原因で、今は貧乏浪人として暮らしている。
そんな彼に、出羽新庄藩から火消組織の再建を依頼される。一度は失った輝きを取り戻せるのか、という展開に、否が応でも期待が高まる。
そして、源吾の妻である深雪。彼女の銭ゲバぶりには、思わず笑ってしまった。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
登場キャラクター
新庄藩火消(羽州ぼろ鳶組)
松永源吾
冷静沈着な指揮役であり、かつて“火喰鳥”と呼ばれた経験を持つ。過去の火災による負傷と恐怖を抱えつつも、再建を託され組織を導いた。仲間の命を尊重し、己の弱さを晒しながらも矜持を示した。
・所属組織、地位や役職
新庄藩火消・頭取。
・物語内での具体的な行動や成果
壊滅状態の組を二百両の予算で再建。芝神宮大火では場内指揮を執り、鐘楼破却などで延焼を防いだ。駒込救援では避難民と合流し、短時間で延焼を押し返した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
“羽州ぼろ鳶組”を名乗り、嘲称を気概の象徴へと転じた。火喰鳥として再び番付に名を連ね、影響力を広げた。
折下左門
新庄藩の使者として源吾を招聘し、再建の補佐を担った。冷静かつ実務的で、時に私財を投じて組を支えた。
・所属組織、地位や役職
新庄藩・使者。組再建の監督役。
・物語内での具体的な行動や成果
三百石の待遇を提示し、源吾の召し抱えを実現。越前人足の手配や資金補填を行い、再建を実務面で支援した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
再建を陰から支える存在として組内で信頼を得た。
鳥越新之助
若侍であり、鳥越蔵之介の子。未熟で軽率な面を見せつつも、次第に父の姿勢を理解し成長していった。
・所属組織、地位や役職
新庄藩火消・頭取並。
・物語内での具体的な行動や成果
芝神宮の火災では観客避難に奔走。行人坂大火では犬を救うために扉を開き、朱土竜の爆発で重傷を負った。駒込の防衛では意識を取り戻し、避難者を指揮した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
“襤褸鳶”として番付に記され、未熟ながら頭取補佐として成長を見せた。
荒神山寅次郎
大柄な力士であり、怪力を誇る。誇りと母への仕送りを重んじたが、源吾の言葉で火消への加入を決意した。
・所属組織、地位や役職
新庄藩火消・壊し手。元力士。
・物語内での具体的な行動や成果
芝神宮の大火で取組を続けつつ、場内防衛に協力。永代橋炎上時には舟橋を支えて避難を助けた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
“荒神山”の名を背負い、壊し手として組の柱となった。
谺彦弥
軽業師「山彦」として知られる。孤児として育ち、借財や因縁を抱えつつも火消に加わった。俊敏で人を鼓舞する才を持つ。
・所属組織、地位や役職
新庄藩火消・纏持ち。
・物語内での具体的な行動や成果
日本橋の火災で屋根を駆け、お夏を救出。永代橋の避難では纏を立て士気を鼓舞。駒込でも源吾を救い、再び纏を掲げた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
“谺”として番付に名を刻み、纏持ちとして組の象徴的存在となった。
加持星十郎
学者肌の人物であり、火消を余事と断じていたが、爆発火災を機に参加した。風読みとして理知的な指示を与える。
・所属組織、地位や役職
新庄藩火消・天文方。風読み。
・物語内での具体的な行動や成果
小諸屋火災で粉塵爆発を看破し、延焼阻止を指揮。四谷大火では鐘楼破却を進言。日本橋怪火では瓦斯の性質を見抜き、砂での鎮火策を示した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
“赤舵”の異名で番付に記され、理知による風読みとして重用された。
深雪
松永源吾の妻であり、冷静で算盤に長ける。家計を守りつつ夫を支え、避難誘導や交渉でも活躍した。
・所属組織、地位や役職
松永家の妻。
・物語内での具体的な行動や成果
越前屋との交渉で算盤を用いて値切りを成功。四谷大火では避難民を説得し、人命を守った。行人坂大火では座敷牢の源吾を支え、再起を促した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
家庭内に留まらず、組再建と避難の要として存在感を示した。
新庄藩関係者
眞鍋幸三
先代火消方。倹約重視の藩政に抗し、道具と安全を重んじたが受け入れられず自刃した。
・所属組織、地位や役職
新庄藩火消・頭取。
・物語内での具体的な行動や成果
装束軽視に反発し、諫死によって意志を示した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
死によって組を去ったが、その姿勢は源吾の再建に影を落とした。
北条六右衛門
新庄藩江戸家老。財政難の中でも火消の質を求めた。時に厳しく源吾を咎めたが、最終的には庇護した。
・所属組織、地位や役職
新庄藩・江戸家老。
・物語内での具体的な行動や成果
源吾に一年半での成果を課し、出動の統制を監督。最終的には責任を負って閉門処分を受けた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
“仏の喜之助”と呼ばれた温厚な人柄を持ち、己を犠牲に組を守った。
幕府関係者
長谷川平蔵
火付盗賊改方頭。冷静で人を見る目を持ち、狐火対策の中心となった。
・所属組織、地位や役職
幕府・火付盗賊改方頭。
・物語内での具体的な行動や成果
狐火の手口を解明し、特別編成組を組織。横山町での戦いを主導し、鍵屋の闇を調査した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
源吾を庇護し、田沼意次と連携して政治的策を進めた。
田沼意次
幕府老中。革新的な思想を持ち、源吾に狐火討伐を託した。
・所属組織、地位や役職
幕府・老中。
・物語内での具体的な行動や成果
江戸大火後に源吾を召し、狐火討伐を正式に命じた。女子の社会進出にまで言及し、遠大な理念を語った。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
未来志向の施策を掲げ、平蔵と並んで物語の政治的背景を形成した。
他藩火消・町火消関係者
大音勘九郎
加賀鳶を率いる頭取であり、華美な装束と高い統制力を誇った。源吾を当初は蔑視したが、現場では協力し合った。
・所属組織、地位や役職
加賀藩火消・頭取。
・物語内での具体的な行動や成果
四谷紙問屋の火災で寺社優先の方針を取ったが、源吾と役割を分担して消火を進めた。千住防衛戦では加賀鳶を率いて西方を守り、鎮火に貢献した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
黒羽織の象徴的存在として、源吾に「西は任せろ」と言い、信頼を示した。
白狼金五郎
日本橋い組の指揮者であり、果敢に鎮火に挑んだ。定石通りの行動を取ったが、怪火により殉職した。
・所属組織、地位や役職
町火消・日本橋い組の頭取。
・物語内での具体的な行動や成果
日本橋の瓦斯火災において鎮火を試みたが、爆発に巻き込まれ重篤の末に死去した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
“白狼”と呼ばれる存在感を持ち、死は江戸中に衝撃を与えた。
宗助
に組の小組頭。父・宗兵衛と縁を持つ源吾の説明を受け、協力に転じた。
・所属組織、地位や役職
町火消・に組の小組頭。
・物語内での具体的な行動や成果
馬喰町の火災で当初は新庄藩と反目したが、源吾の言葉により協力し、消火に尽力した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
父の名を引き継ぐ若手として、組の未来を担う存在と描かれた。
旧定火消・松平家関係者
鵜殿平左衛門
松平隼人家中の者であり、深雪への執着心から源吾に敵意を抱いた。卑劣な手段で源吾を妨害した。
・所属組織、地位や役職
松平隼人家・家臣。
・物語内での具体的な行動や成果
渡辺邸火災の折に源吾を襲撃し、脚を砕いて出動を妨害した。後に定火消屋敷の火災でも門保護に固執し、消火を遅らせた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
敵対者として描かれたが、源吾の指揮により命を救われ、結果的に罪を免れた。
鍵屋・花火師関係者
秀助
鍵屋で才覚を発揮した花火師であり、“焔の鬼”と称された。娘と妻の死を経て復讐に走った。
・所属組織、地位や役職
鍵屋・番頭。
・物語内での具体的な行動や成果
怪火を用いた狐火の一人として暗躍。横山町で覆面の一人として出現し、馬喰町でも源吾に追われた。右手を斬られたが、猶予を求められ見逃された。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
後に平蔵に捕縛され火刑となった。赤い鈴を娘の象徴として抱き、物語の核心を担った。
清七
温和な花火師であり、秀助とともに鍵屋を支えた。
・所属組織、地位や役職
鍵屋・手代。
・物語内での具体的な行動や成果
火薬調合や花火製作に尽力した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
直接的な火付けには関与せず、家業を守る立場であった。
清吉
清七の子であり、天才的な才覚を持つ花火師。独自の調合法で新発色を生んだ。
・所属組織、地位や役職
鍵屋・花火師見習い。
・物語内での具体的な行動や成果
赤味を帯びた新作を試みたが、暴発を招き事故につながった。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
“玉屋”の名を与えられるほど将来を嘱望されたが、悲劇の引き金を作った。
市井の人々
お夏
寺育ちの孤児で、後に茶屋の娘として暮らした。甚助と夫婦になる約束をしていた。
・所属組織、地位や役職
掛茶屋の娘。
・物語内での具体的な行動や成果
借金のため売られそうになったが、彦弥や源吾に救われた。丹波屋火災では火の見櫓に取り残され、命を落としかけた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
江戸払いとなったが、運命は彦弥や甚助と深く交錯した。
甚助
派手な纏で人気を集めた鳶であり、“花纏”と呼ばれた。お夏と夫婦になる約束をしていた。
・所属組織、地位や役職
町火消・に組の鳶。
・物語内での具体的な行動や成果
丹波屋火災で櫓に突進したが失敗。火消を辞して甲斐で農に従事する決意を固めた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
花纏の名を彦弥に託し、火消の世界を去った。
展開まとめ
序
火災現場の惨状
左門は九段坂飯田町で炎に包まれた店を目の当たりにし、類焼の広がりに息を呑んでいた。熱気は喉を焦がし、鐘の音が鳴り響く中でも火消は現れていなかった。野次馬の声から、備蓄の油に引火して瞬く間に燃え広がったことを知った。
羽州ぼろ鳶組の登場
やがて羽織袴の一団が砂煙を上げて現れ、先頭に立つ若き頭が迅速に指示を飛ばした。その姿に群衆は歓声を上げ、火消たちは勇敢に炎へと立ち向かった。他の組も駆けつけたが、この組の働きは一際目立っていた。
富商との対立
頭のもとへ地元の富商が駆け寄り、自らの店を先に救うよう頼んだ。富商は礼を約すとまで言ったが、頭は危険な場所から優先するのみと一蹴し、富商は退いた。
姫の行方
救出された人々の中にいた武士が、主君の娘である姫の行方を探して錯乱していた。事情を聞いた頭は、姫が店内に取り残された可能性を知り、即座に自ら助け出すと決意した。
炎への突入
左門は無謀だと制止したが、頭は水を被り炎へ飛び込む覚悟を示した。左門が命を惜しむなと叫ぶと、頭は自分も同じ気持ちだと返し、真紅の炎の中へと身を投じた。左門はその背を震えながら見送り、心を熱くさせられていた。
第一章 土俵際の力士
一
召し抱えの知らせと源吾の疑念
松永源吾は新庄藩より召し抱えの使者・折下左門を受け、理由の不明さから強い疑念を抱いていた。源吾は学問も剣も人並み以下と自認しており、妻・深雪も怪しんだため、当初は応じかねていたのである。
三百石の提示と承諾
左門は役目や詳細を伏せつつも、御城使格・三百石という破格の待遇を示した。深雪は即座に了承し、源吾は逡巡しつつも受諾した。源吾は現場に出ぬ指導役で良いとの条件に安堵し、再び火消には戻らぬ決意を胸に秘めていた。
火喰鳥の過去
源吾は定火消・松平隼人家中において自らも火事場に躍り込み人命を救った経歴を持ち、鮮やかな手並みと派手な装束で火喰鳥の異名を得ていた。しかし火消の寿命の短さと過酷さを知り、手の甲の火傷痕を見つめながら過去を封印していたのである。
江戸消防の概説
江戸の消防は、奉書火消の教訓から大名火消が置かれ、所々火消・方角火消などに細分化されていた。旗本が指揮する定火消も存在したが、後発の町火消(いろは組)の台頭で定火消は縮小傾向にあった。
新庄藩の事情と左門の説明
新庄藩は過去の財政難と出仕停止の影響を引きずりつつ、若年の戸沢正産を戴き、江戸家老・北条六右衛門が執政として倹約と産業振興を推進していた。六右衛門は予算を絞りながらも見栄えを重視し、火消の質は落とすなという難題を突きつけていた。
眞鍋幸三の抵抗と切腹
前任の火消方・眞鍋幸三は、装束より道具と安全に資金を投ずべしと主張し、六右衛門と鋭く対立した。結果として眞鍋は二通の遺書を残して自刃し、鳶衆の暴発は止まったものの、有力な鳶や同輩が次々と去り、組は壊滅した。
再建条件の苛烈さ
源吾には二百両での再建と名を上げることが求められた。定員百十名に対し在籍は二十四名のみで、七つ道具も欠乏していた。源吾は難題と断じ、最悪は切腹の沙汰もあり得ると左門は示唆したが、左門は源吾の手並みに確信を示し再建を託した。
源吾の腹決めと人員の実情
源吾は現場復帰の意志はなくとも、受けた以上は立て直すと腹を決めた。上屋敷の教練場に集った面々を見て、気骨ある者が抜け落ち青瓢箪ばかりと嘆息したが、頭取として挨拶し立て直しに着手する構えであった。
鳥越新之助の登場
教練の場に遅参した若侍・鳥越新之助は言い訳を重ねて左門に咎められつつも、源吾の傍らで頭取並としての礼を尽くした。組の規律の緩みと人材の脆さが露わになる中、源吾の重責は一層明確になっていった。
二
座敷での協議と家格のからくり
教練後、松永源吾は折下左門・鳥越新之助と残り、頭取並が繰り上がれぬ武家社会の家格制を確認した。左門は源吾を大和松永氏の末裔として触れ込み、家格を盛って採用にこぎつけていた。
新之助の遅参と資質
新之助は寝坊を見抜かれて詫び、以後の無作法を戒められた。源吾は左門を「左門」、自らを「源吾」と呼び合うことを提案し、関係の実務化を図った。
左門の私財拠出
左門は二百両不足を補うべく三十両を差し出し、源吾は感謝して受領した。新之助は事の重大さを十分に理解していなかった。
鳥越家の事情と蔵之介の殉職
新之助の父・鳥越蔵之介は、前頭取・眞鍋幸三の諫死後も代行として火消を支えたが、二月前の赤羽橋近くの不審火で殉職した。狐火と呼ばれる巧妙な火付が続発しており、蔵之介は鎮火後の土蔵検分中に爆ぜで命を落とした。
朱土竜の指摘
源吾は現象を朱土竜と断じ、密閉部の破断で外気が流入し爆発的に燃え上がる危険を説明した。ただし火消一筋の蔵之介が知らぬはずはなく、経緯に腑に落ちぬ点が残った。
北条六右衛門との直談判
源吾は江戸家老・北条六右衛門に再拝謁し、やり方への一切不干渉を要求した。六右衛門は予算増を拒みつつも、一年半で結果を出す約定を了承した。源吾は男に二言はないと応じ、再建に踏み出した。
再建方針と人員計画
評定(実質は源吾と新之助の二人)で、鳶の確保を最優先と定めた。定員百十名のうち、初動を担う一番組三十名を精鋭で固めれば七割は決するとし、残りは鍛錬で補う方針を示した。
江戸の火災環境の観察
日本橋へ向かう道すがら、源吾は火除け地の減少や手桶未設置など防火の弛緩を指摘し、人口流入による火災増の必然を新之助に説いた。
必要人材の定義
源吾は纏持ち(先陣・偵察・踏みとどまる胆力と俊敏)、壊し手(鳶口・刺叉で家屋破砕の怪力)、風読み(複雑な風向を読む軍師)の三役を必須と定め、特に風読みには心当たりがあると述べた。
越前屋での人集め交渉
口入れ屋・越前屋の松太郎に八十名の手配を依頼したが、相場では二百四十両以上を要すると示された。源吾は予算の限界を示し、打開策を探った。
深雪の勘定と値切り
呼び出された深雪は算盤を捌き、越前人の雇用単価・旅費・税・口入れ取り分・上納金の扱いの誤りを次々と指摘した。上納金施行前で不要、虚偽算定の科料相当を値引き要件とし、最終的に百五十五両で手配・口止め・御足代三両を確保した。松太郎は承諾し、新之助は深雪の剛腕に戦慄していた。
三
柱となる人材探しの難航
越前からの人員は二月後に到着予定であり、その間に中核となる鳶を見つけねばならないが、江戸では各藩の争奪戦が激しく口入れ屋でも手の打ちようがない状況である。
芝神宮の相撲見物へ
鳥越新之助の進言で芝神宮の興行を見物する。巨躯の荒神山寅次郎は不調で敗れ、前頭筆頭の達ヶ関森右エ門は圧倒的な相撲で場内を沸かせた。
力士同士の軋轢と寅次郎の人柄
手形配りの場で達ヶ関が三役力士と口論となり、寅次郎が仲裁に入って収める。新之助は執念で達ヶ関から手形を得、そこで達ヶ関が寅次郎への敬意と近況を語る。寅次郎は一年前後前、鳶との揉め事を仲裁した折に膝を傷めて以降、成績が低迷し、千秋楽に負ければ幕下転落・引退の瀬戸際にあるという。千秋楽の相手は達ヶ関自身で、弟弟子として引導を渡す覚悟であると明かされる。
新之助の勧誘と源吾の諫言
新之助は寅次郎を壊し手として火消に誘うが、寅次郎は母への仕送りと誇りを理由に固辞し、鳶への嫌悪もにじませる。松永源吾はこれを咎め、鳶は命懸けで町を守る者であると説き、さらに自身の右脚の骨変形や火傷痕、炎への恐怖を晒して「戻ったからにはやれることをやる」と胸中を吐露する。そして寅次郎に対し、母を言い訳にせず「大関の夢を諦められぬ」と堂々と言えと促す。
去り際の励ましと余韻
源吾は勧誘を引っ込め、「諦めぬ者が好きだ。負けるな」とだけ告げて立ち去る。夕日に染まる中、寅次郎は支度部屋の前で立ち尽くし、震える大きな背をひぐらしの声が包み込むのであった。
四
千秋楽の熱気と火の報せ
非番の松永源吾と鳥越新之助は芝神宮で相撲を観戦していたが、太鼓と半鐘の連打から火事を察知する。火元は浜松町南端の商家土蔵で、南風に煽られ芝神宮方面へ延焼の恐れありと知れる。源吾は観客に落ち着いた避難誘導を試みるが、丹羽家の火消が騒ぎ立てたため混乱が拡大したのである。
土俵に残る荒神山と達ヶ関
荒神山寅次郎と達ヶ関森右エ門は「土俵に上がった以上、どちらかに土が付くまで終わらぬ」という相撲の決まりに従い、火勢迫る中でも取組を続行する覚悟を示す。寅次郎は「一世一代の大一番」と言い切り、達ヶ関も応ずる。源吾は「ならば意地でも火を防ぐ」と腹を決め、場内の指揮と壊しの号令を出しつつ、自ら軍配を拾って行司役を務めることにしたのである。
消し口の布陣と鎮火
新庄藩・毛利家・丹羽家の桜田組勢が消し口を争わずに布陣できた幸運もあり、神宮南の家屋を壊して延焼線を切る策が奏功する。燻煙立ち込める中での取組は一瞬で勝敗が決し、寅次郎が「大関になれ。お主なら必ずなれる」と達ヶ関に言い残す。浜松町の火は一刻半後に鎮火したのである。
見舞いと寅次郎の決断
火事の翌々日、源吾と新之助は達ヶ関・寅次郎を見舞う。二人は喉を痛めたのみで大事に至らず、達ヶ関は源吾の采配に礼を述べる。寅次郎は「髷を切り、結い直す覚悟」を固め、松永組への加入を願い出る。源吾はこれを受け、「弱きを守る」火消の道に寅次郎を迎え入れたのである。
別れの相撲と未来
移動の途上、源吾が勝敗を質すと、寅次郎は空を仰いで「達ヶ関は大関になる男だ」とだけ応える。自らの幕引きを悟り、達ヶ関の飛躍を確信して笑む寅次郎の背は、風に流れる雲とともに近江の空へ続いていくかのようであった。
第二章 天翔ける色男
一
長屋の改修と教練の日々
寅次郎は入居から十日目に二部屋分を与えられ、怪力で人並み以上の働きを見せていた。源吾は彼と新之助に特別教練を課し、火事場での判断や指揮を学ばせた。新之助は理解は早かったが気持ちが伴わず、失敗と叱責を繰り返して気鬱になっていた。
火消番付の収集と人材選定
源吾は左門から火消番付を受け取り、有力な町火消を引き抜く計画を進めた。三役は移籍が困難であるため、狙いは町火消に絞られた。番付には新之助の父・鳥越蔵之介の名もあり、優れた火消として評価されていたが、新之助は父に関心を示さなかった。
花纏の甚助の存在
番付に記された「に組」の甚助は、折り紙の花を纏に飾る派手な鳶で、花纏と呼ばれ人気を博していた。源吾は彼の引き抜きを検討したが、必要な金額は五十両と高額であり、左門は苦慮した。夕餉の席では深雪が食費を徴収し、家計を守る姿勢を示した。
甚助との交渉と彦弥の乱入
翌日、源吾は甚助と交渉したが、甚助は五十両を要求し態度も傲慢であった。その最中、女衒との因縁を抱える美貌の男・彦弥が乱入し、甚助と激しく衝突した。彦弥は軽業師「山彦」として知られる存在で、屋根から屋根へと飛び移りながら逃走した。その姿を源吾らは驚愕しつつ見送った。
二
源吾の捜索と山城座での聞き込み
源吾は三日三晩眠らずに彦弥を追い、江戸中を手分けして探したが成果は乏しかった。山城座で座長の彦右衛門から、彦弥は孤児で寺育ちであり、借金を肩代わりして丹波屋に追われていると聞き出した。彦右衛門は土下座して捜索を頼み、源吾は胸を詰まらせてこれを止めた。
お夏の所在発見と三人の過去
寅次郎の旧贔屓筋の伝手で掛茶屋の娘・お夏を突き止めた。お夏は孤児として寺で育ち、のちに茶屋へ、彦弥は山城座へ、甚助は蔦へ引き取られた過去を語った。お夏は昨年に甚助と夫婦になる約束をしており、彦弥は笑顔で祝福していた。
借金の経緯と甚助への疑念
和尚の病に金が要り、甚助が限界まで借りたため、お夏は高利貸しに手を出した。証文は書き換えられ、借金は三十両へ膨らんだ。吉原に売られる段でお夏が告げると、彦弥は二月前に三十両を渡して姿を消した。源吾は一連の流れから甚助の謀略を疑った。
待乳山の大銀杏での再会
お夏の記憶を手掛かりに源吾は待乳山へ向かい、大銀杏の下で彦弥を発見した。源吾は身分を明かし、匿うと約した。二人は惚れた女を守る思いを語り合い、彦弥は源吾を信じて同行することに応じた。
源吾宅の食卓と深雪の裁き
源吾宅で彦弥は大食を見せ、新之助と寅次郎も競うように食べた。深雪は家計の掟に従い、源吾を当日の尽力で無銭とし、寅次郎は手土産で免除、彦弥は初回と容貌を理由に値引き、新之助には常連・手土産無し・不美男の三拍子で五十文を科した。場は笑いと苦笑に包まれた。
勧誘と借金返済策の提示
新之助は直球で仲間入りを求め、源吾も江戸一の火消になれると断言した。彦弥は三十両の借金を理由に難色を示したが、源吾は左門に頼んで俸給からの前借三十両を無利子で貸す策を示し、非番に興行へ出ることも許すと説得した。彦弥は感謝しつつ決断を熟考していた。
半鐘の遠鳴りと丹波屋火災
遠い半鐘を源吾が聞き取り、寅次郎に火元の確認を命じた。戻った寅次郎は日本橋北端の丹波屋方で出火と報告し、町方は火付けと見做していた。下手人が若い娘との噂に彦弥は蒼白となり、源吾は馬二頭を命じ、新之助には当直を連れて追従を指示した。二人の脳裏には同じ人物の影がよぎっていた。
三
日本橋への急行と屋根伝いの進撃
源吾と彦弥、寅次郎は馬で日本橋へ急行した。群衆と大八車で道が塞がる中、彦弥は屋根へ跳び移り、義経八艘跳びを思わせる速さで火元へ向かった。源吾は寅次郎に放り上げられて屋根に上がり、現場把握に移った。
風読みと現場指揮の再起動
源吾は月齢や風向を口に出して整理し、火は東進と判断した。町火消から事情を聴取し、火元は丹波屋、若い女お夏による放火が疑われていると把握した。に組の援軍が到着し、甚助は青ざめていた。
火の見櫓の危機と甚助の突進
火の見櫓頂上にお夏が立ち、炎と火粉が迫っていた。甚助は花纏を持たずに櫓へ取りつき、和尚の死と自責を吐露したが、老朽化した木組みで足を滑らせ屋根へ落下した。お夏は放火を否定し、揉み合いで延焼したと訴えた。
彦弥の登攀と寅次郎の受け
彦弥は新庄藩火消を名乗って櫓へ挑み、熱風に焼かれながらも跳躍を重ねた。櫓崩落の兆しの中、お夏は身を投げ、彦弥は身を楯に抱き留めて落下した。寅次郎は股割りで二人を受け止め、命をつないだ。櫓は直後に崩れ落ちた。
鎮火後の保護と処遇の見立て
卯の刻に鎮火し、死者は出なかった。源吾はお夏と彦弥を自宅に収容し、医者を手配した。お夏は将軍御成日の失火ゆえ手鎖五十日や江戸払いもあり得ると告げられたが、放火犯断定は避けられる見通しであった。
火消勧誘と三十両の算段
源吾は無利子前借の三十両で借金を清算させる策を示し、非番の興行も許すと説いた。彦弥は火消入りを承諾し、江戸で涙する女を減らすと気炎を上げた。
詮議の結果と別れの支度
お夏は江戸払い、甚助は手鎖三十日となった。甚助は火消を辞して甲斐で農に就く決意を固め、和尚の遺志に従うことにした。
四谷の見送りと三十両の返上
源吾と彦弥は四谷木戸まで見送り、彦弥は借り受けた三十両を麻袋ごと甚助へ渡した。甚助は花纏の名を継ぐよう願ったが、彦弥は断り、笑いを交わして別れた。
纏の意匠「大銀杏」と余韻
彦弥は纏の意匠を大銀杏と定め、銀杏が火を防ぐ話に源吾は頷いた。花が咲き、夏が去り、残る銀杏が江戸を守るという調べを口ずさみ、二人は甲州街道の銀杏並木を思い描きながら歩みを進めた。
第三章 穴籠りの神算家
一
越前人足の到着と戸沢方の活気
長月に入り、越前屋手配の人足が屋敷に到着し、過酷な仕込みが始まった。朴訥な気質ゆえ逃亡者は出ず、残留の青瓢箪たちにも「褒めて伸ばす」源吾の采配が効き、腕が上がり始めていた。
風読みの迷いと江戸の放火多発
源吾はお夏の件で風を読み違えた自責に苛まれ、腕が落ちたと焦っていた。折しも江戸では放火が急増し、幕府が摘発を重ねる中でも狐火だけは依然として捕まらなかった。
親爺=加持孫一の回想と捜索決意
源吾は十八で頭となった頃に出会った「完全無欠の風読み」たる親爺を思い出した。鬢に白を混ぜた初老ながら言葉がすべて的中し、屋外で風と月を感じねば人は瞬かぬと語った謎多き男であった。名は加持孫一。六年前に「野暮用」を理由に去り、以後行方知れずとなっていた。源吾は再会を決意し、武鑑を遡って加持の痕跡を探し、御徒町筋を当たる算段を立てた。
御徒士筋の事情と小諸屋行き
御徒士の配置や役目を確かめつつ、源吾は単独で上野方面へ向かうつもりだったが、新之助に「小諸屋の蕎麦」を口にしたため同行を願い出られ、結局、彦弥と寅次郎も連れ立つことになった。道中で真意――加持孫一を風読みとして迎えたい――を明かすと、新之助と寅次郎は肩を落としたが、まず腹ごしらえに小諸屋へ入った。
小諸屋の賑わいと親爺の面影
信濃蕎麦を土蔵で備蓄する人気店は満席で、番付「東の関脇」と新之助が持ち上げる。源吾は蕎麦を手繰りながら、飢饉に強い作物として蕎麦を説いた親爺の声音や、暦を民のために使えと憂えた面影を思い出していた。
不穏な托鉢僧の来訪
常連の席取りで少し待つよう女将が告げると、煤けた僧が激昂し、語調を豹変させた。源吾は「気持ちよく食ってやらねえと蕎麦も泣く」と宥め、寅次郎と彦弥を制して睨み合いを受け止める。僧は無言で去り、唐金の風鈴が高く鳴った。女将が詫びると、源吾は「美味い蕎麦だったから邪魔をされたくなかっただけだ」と軽く受け流した。
二
御徒町での空振りと手掛かりの糸口
源吾ら四人は武鑑に載っていた加持星十郎の旧宅を訪れたが、すでに別家の住まいとなっており行方は不明であった。近隣の聞き込みでも加持家の転居先は掴めず、新之助が掛茶屋の主人から「加持の隠居は団子好きで通っていたが、宝暦末から姿を見せなくなった。息子・星十郎は明和三年ごろ御家人を辞めると言い残して以後は来ない」との証言を得た。星十郎は陽に透けて赤みが差す髪から「赤火事」と渾名され、最後に来た折には老爺を「連貝軒殿」と呼んで長居していたという。
取組表に現れた「連貝軒」
翌日、寅次郎が持参した相撲の取組表に「幕府天文方・山路連貝軒(本名・山路弥左衛門主住、六十七)」の名が六曜の照合で記されているのを源吾が見つけ、左門に根回しして面会を取り付けた。
山路の証言――親爺の正体と最期
山路は源吾の定火消時代の異名「火喰鳥」を承知しており、加持孫一の消息を明かした。孫一の本姓は渋川、三代目天文方・渋川敬尹の庶長子で、母は長崎出島で出会った蘭人の娘であった。嫡子の則休・光洪を助けつつ天文を極めたが、「学びは巷にあり、巷へ還元すべし」と御徒士・加持家の株を買って市井に身を置いたという。やがて山路が暦編纂権の奪還を期して協力を請うと、孫一は逡巡の末に応諾したが、明和二年、中山道守山宿での大火に際し、湖風の読みを退けられた現地火消が退くなか、逃げ遅れの救助に踏み止まって炎中に殉じた。山路は以後、土御門家に屈して宝暦暦を使い続けるほかなかったと語り、かつて孫一が源吾の言葉「日は人々の暗い今日を消すため沈み、輝く明日を彩るため昇る」を愉しげに話していたと付け加えた。
次なる行き先――天才への道標
山路は最後に「孫一が唯一天才と呼んだ者が、荒川を越えた宮城村に隠棲している」と示し、源吾はその名が加持星十郎であると確信した。
三
宮城村の庵訪問と初対面の緊張
源吾は新之助・寅次郎・彦弥を伴い宮城村の庵を訪ね、加持星十郎と対面した。赤茶の総髪と彫りの深い相貌は南蛮の血を思わせ、年齢に似合わぬ落ち着きを帯びていた。源吾は新庄藩で士分百三十石・天文方として迎え、非常時のみ火事場で力を借りたいと申し出たが、星十郎は即座に辞退した。源吾が孫一との縁を明かすと、星十郎は「学者の本分は理を顕かにすること」とし、火消は「余事の余事」ゆえ父の死を犬死と断じたため、場は一触即発となったが、源吾が抑えたので事なきを得たのである。
星十郎の学問観と挑発――月距離と「心の学」
星十郎は学問の目的を「虚説を糺すこと」と定義し、南蛮の知を引き合いにジェローム・ラランドの月距離、さらに「ピシフォロフィー(心理学)」を口にして彦弥の仕草から心情を言い当てた。慇懃無礼な物言いは反感を招いたが、源吾は矛を収め、日を改めることにした。
再会の小諸屋――髪と黒子、鈴のことば
数日後、源吾は小諸屋で星十郎と二人きりの席を設けた。人目を避け頭巾で現れた星十郎は、髪色ゆえ生きづらいと吐露した。看板娘の鈴が「綺麗な御髪」と褒め、口元の黒子を示して「嫌いだったけれど、人に褒められて好きになれた」と語ると、星十郎は赤面しつつ「良いと思います」と応じ、わずかに氷解の兆しを見せた。やがて彼は父を「学者として誇るが火消としては誇らない」と本心を明かし、差別の記憶を抱えつつ「父のやり残しを天文で成す」と固く拒んだのである。
決裂と当面の方針
源吾は勧誘を退けられたまま帰し、定例の会合で「当面は自分が風読みを務める」と宣言した。新之助と寅次郎は星十郎への不快を隠さず、彦弥もそっぽを向いた。左門は禄増しでの再交渉を示唆したが、源吾は渋い顔をした。
深雪の示唆――報酬以外の鍵
この折、深雪が「誰もが銭や禄を望むわけではない」と静かに差し挟んだ。金では動かぬ者がいるという当たり前の真理が、場の空気を一変させた。星十郎を動かす鍵は名誉でも禄でもなく、彼自身の傷と誇りに触れる何かであると、源吾は悟り始めていたのである。
四
野分の夜と小諸屋の火災
源吾は夜半に半鐘と爆裂音を聞き取り、火消屋敷に駆け込み配下を招集した。火元は上野の小諸屋であり、寛永寺を守る松平相模守に馳走すべく急行した。火事場では所々火消や町火消が入り乱れ指揮は混乱、野次馬も多く道は塞がれていた。戸沢鳶は粗末な装束を嘲られ士気を失いかけたが、彦弥が「火消は命を救う腕で魅せる」と鼓舞し立ち直らせた。
小諸屋の女将と不可解な爆発
現場では西の蔵が爆発し、舞い散った紙片が北西に延焼。店は無事だったが女将が発作で倒れ、お鈴が看病を続けていた。残る東の蔵は内燃の兆候を示し、風向きが変われば店を直撃する危険があった。源吾は唯一の望みを加持星十郎に託し、宮城村へ走った。
星十郎の推理と粉塵爆発の真相
説得を受けた星十郎は現場に赴き、瓦礫から火縄を発見。爆発は火薬ではなく蕎麦粉を充満させた粉塵爆発によるものと断じた。残る蔵にも仕掛けがあると見抜き、別の方向から屋根を破り消火すれば延焼を防げると提案した。寅次郎が巨石を放り屋根を破壊すると火柱が噴き上がり、百余の水桶で一斉に鎮火した。
火除け地の形成と延焼阻止
星十郎は風向きを読み上げ、幅十間の火除け地を作るよう指示。源吾と配下は町火消をも巻き込み、富商の蔵をも崩して延焼を食い止めた。完全に火が収まった後、源吾は星十郎をお鈴に紹介し、女将救出を感謝された星十郎は戸惑いながらも心を揺さぶられた。
仕官受諾の決意
後日、源吾は星十郎を宮城村まで送り、彼の胸中に残る父・孫一の言葉を想起させた。数日後、星十郎は「仕官の儀、謹んでお受け致します」との文を送り、戸沢家天文方としての道を歩むことを決意したのである。
第四章 花咲く空の下で
一
北条六右衛門の叱責と「ぼろ鳶」問題
小諸屋の火事から十日後、源吾は北条六右衛門に呼び出され、無断行動や管轄外への介入を厳しく咎められた。六右衛門は新庄藩火消の装束と統一感の欠如を挙げ、他家から「ぼろ鳶」と嘲られている現状を指摘した。源吾は費用を出さぬまま名声を求める姿勢に反発したが、結果を出すと応じたのである。
名声と資金の葛藤、源吾の決意
六右衛門は名声向上を至上命題としつつ、支出を拒む方針を貫いた。源吾はやり方に干渉しないという約束を念押しし、金は出ないと承知の上で、方法を問わず名を上げると決意を固めた。
四谷出火と現場の混乱
師走初めの未明、四谷で紙問屋が出火した報が届いた。寺社が密集する一帯であり、紙類の延焼が各所に飛び火していた。町火消を除く多くの大名火消が動員され、現場は竜吐水が交錯し、指揮系統不在のまま混乱していた。
加賀鳶との遭遇と方針の対立
源吾は総指揮不在を確認し、中心火点の制圧に向かった。先着していたのは黒染の刺子と華美な裏地を備えた加賀鳶であり、指揮する大音勘九郎は新庄藩を蔑視した。加賀鳶は寺社の防御を優先しており、民家の延焼を看過する姿勢が露見したことで、源吾は人命軽視を厳しく糾した。
人命最優先の指揮と新庄鳶の奮戦
源吾は寺社奉行の意向に拘泥せず、人命と民家保護を最優先とする方針を布告した。彦弥は大銀杏の纏を高所へと立て、士気を鼓舞した。装備の質では劣る新庄鳶であったが、統制された加賀鳶と役割を分け合い、相互に干渉せず消火を推進した。
鐘楼破却による延焼遮断
星十郎の進言により、延焼拡大の要となる鐘つき堂の破却を決断した。源吾は縄を掛けて合図し、寅次郎らと一斉に引いて転倒させ、倒壊後は梁を速やかに解体して火勢を削いだ。これにより火の勢いは鈍り、消火線が安定したのである。
鎮火と評価、そして叱咤
新庄藩の到着から一刻半で鎮火に至った。死者は紙問屋の奉公人一名に留まり、寺社奉行も結果を称えたという報が新之助から伝えられた。これに対し源吾は、たった一人で済んだのではなく一人も死なせてはならないと諭し、火消の本分が命を守ることにあると厳しく叱咤した。
火消装束の意味と源吾の内省
新之助は装束の華やかさを問うたが、源吾は裏地は鎮火後にのみ返して歩む生き様の象徴であると語った。自らは鳳凰の意匠を用い、火からの再生を信じる心を示してきたと明かした。語り終えた源吾は蒼天を仰ぎ、なお自分は立ち止まっているのではないかと省みつつ、再生への意志を噛み締めたのである。
二
小火への急行とお七の救出
新庄藩火消の管轄内で小火が発生し、源吾は一番乗りを指示した。現場は半焼の長屋であり、避難はほぼ済んでいたが、齢十ほどの娘お七が母の救出を懇願していた。源吾は棟の破却を一時停止させ、頭から水を浴びて炎中へ踏み込み、彦弥も続いた。源吾は煙に倒れた母を救い出し、お七に喉を傷めただけで命に別状はないと告げた。
恐怖の後遺と矜持
救出直後、源吾は人目の届かぬ路地で嘔吐するほど衰弱していた。新之助は休養を促したが、源吾は強がりつつ現場復帰を選んだ。新庄藩火消は救出後に棟を崩して鎮火し、死人は出さなかった。源吾は規律に従い、胸を張って帰るべく羽織の裏を返すことを許した。
嘲笑の行列と「ぼろ鳶」の名乗り
帰路、往来の嘲りに新之助は顔を伏せた。源吾は彦弥に口上を任せ、彦弥は軽業と語りで群衆を惹きつけ、寅次郎や星十郎、新之助を次々に紹介した。締めくくりに彦弥は火喰鳥の再起として源吾を掲げ、源吾は敢えて我ら羽州のぼろ鳶組でござると高らかに名乗った。群衆は歓声で応え、蔑称が気概の象徴へと反転したのである。
奉書到来と飯田町出動
小晦日の訓練場に奉書が届き、飯田町の火勢に身命を賭して当たるよう沙汰が下った。源吾は混雑回避のため西回りを選択し、道中で新之助に管轄との連携と指揮の可否を問うた。星十郎は源吾の顔色を案じつつも、私事を捨てよと諫め、源吾は援護方針へ転じて玄蕃桶の補給線を整備させた。
松平家との軋轢と連携策
現地で新庄藩の名を出すと受け入れを拒まれ、松平側は余計な真似をするなと通告した。源吾は背後からの散水で類焼を防ぐ策を新之助に命じ、星十郎には本郷から受け入れざるを得ない援軍を呼ぶよう走らせた。
鵜殿平左衛門との対峙
馬上で指揮する鵜殿平左衛門を見つけた源吾は奉書を理由に立ち入りを求めたが、鵜殿は地勢を口実に拒み、深雪を侮辱する言を投げた。源吾は激昂して刀に手を掛けたが、新之助が制止し、言を取り消せと迫った。鵜殿は侮辱のみを撤回し、なお手伝い無用と言い残して去った。源吾は己の取り乱しを恥じ、すべき消火に専心する決意を新之助と共有した。
援軍到着と終局への展望
独自の消火を続けるうち、遠方から歓声が上がり、星十郎が呼び込んだ加賀鳶が到着した。戦力の加勢により鎮火は近いと見込まれ、源吾は蒼い冬空を仰いで静かに息を整えたのである。
三
火消番付の発表と軽口
年が明けて明和八年の番付が公表され、松永源吾のみが過去の実績により西小結「火喰鳥」として名を連ねた。新之助や彦弥は入幕せず落胆したが、新顔の反映は時期尚早と理解した。新之助が久哥の読みを尋ね、名に口が二つで口煩いとからかうと、源吾は新之助の名正勝に勇壮さを求めてやり返し、座は笑いに包まれたのである。
飯田町大火の総括と自責
小晦日の火事は飯田町で二割全焼、三割半焼に及び、正月返上で復旧が続いた。原因の一端は松平側の初動遅れにあったが、源吾は松平家に在れば避け得たとの自負を抱き、自らにも遠因があると省みていた。
夕餉の卓での応酬
深雪は自責を否定し己の責任を口にしたが、源吾は駆け付けられなかった事実を認めた。源吾が深雪の情の薄れを揶揄するように述べると、深雪は険しい表情でそっぽを向き、源吾は宥めることも億劫に感じて無言で箸を進めた。
出会いと縁談の始まり
七年前の明和元年、源吾は松平隼人家の勘定方長・月元右膳から一人娘を娶らぬかと持ちかけられた。婿養子の打診に源吾は家断絶を口実にいったん辞退したが、右膳は火消頭の職はそのままにと条件を緩め、深雪の強い思慕と源吾の清廉を評価して再考を促した。
噂の拡散と鵜殿の敵意
縁談の噂は家中から管轄の町まで広まり、形原十内の甥である鵜殿平左衛門が深雪への懸想と家中の権益思惑から源吾へ敵意を募らせた。以後、道具破壊や因縁などの嫌がらせが頻発した。
雪の日の差し入れと番傘
明和二年睦月、深雪が雪の中を差し入れに訪れ、手際よく鍋を整えた。源吾は好みの味に思わず称賛し、深雪はいつでも持参すると応じた。帰り支度には番傘がなく、源吾は外へ走って買い求めて差し出した。深雪は悪天の日に返すと微笑み、二人は礼を保ちながらも親密さを深めた。
逡巡と心の変化
差し入れが重なるうち、源吾は深雪を待つ自分に気づいた。しかし火消の志を最優先とする思いは残り、右膳の申し出を即答するには至らなかった。
右膳の病と床前の約定
如月中旬、月元右膳が重病で倒れ、源吾は見舞いに赴いた。右膳は家の存続より娘の幸せを望む心中を明かし、深雪の意中の相手を案じつつも口を割らなかった。源吾はついに受諾を表明し、火消頭の職の継続を条件に深雪を娶ると伝えた。右膳は義息として託すと応じ、笑みを残して床に身を横たえたのである。
四
婚約の流言と祝言の取り決め
松永源吾の婚約は瞬く間に広がり、月元家の婿養子になるという尾鰭まで付いて騒がれた。右膳の病状を踏まえ、慣例を繰り越えて早急に段取りされ、水無月に祝言を執り行うことが定まったのである。
鵜殿平左衛門との往来の一触
卯月、往来で鵜殿平左衛門が取り巻き五名を従え源吾に絡んだ。源吾が「勘定方は遠戚が継ぐ」と告げると、鵜殿は安堵しつつも深雪への執着を滲ませ、嫉妬を露わにした。刃傷沙汰寸前、深雪が現れて機転で場を収め、鵜殿一行は退いたのである。
渡辺邸の出火と中庭の待伏せ
月末、松平家中・渡辺邸の失火が走り、隣の月元家への類焼が迫った。出動支度のため奥へ入った源吾は、中庭に鵜殿らが酒甕を携えて待ち構える異様を目にした。鵜殿は「お前が出ねばよい」と暴行で源吾を抑え込み、脚を踏み砕き、気絶に至らせた。源吾が出なければ町火消も他藩応援も動けぬという幕府の定めが、意図的に悪用されたのである。
右膳の最期と遅れた消火
深雪が駆けつけて源吾を介抱したが、当家の火消は遅れ、町火消も出られなかった。右膳は「婿殿と幸せにやれ」と笑みを残しながら臨終に臨んだ。源吾は激痛の脚でなお現場に向かい、玄蕃桶を被って炎中へ飛び込み、病の老婆救出に賭したが、すでに死人は三名にのぼっていた。
断罪と破談の予想を越えて
翌日、焼け跡から右膳の亡骸が見つかり、月元家は養子を迎えて存続が決した。世は源吾を罪人視し、縁談破談は必定と見たが、一月後、屋敷明け渡しの折に深雪が訪れ、「月元とは縁を切った」と言い、黙々と荷をまとめ始めたのである。
川開きの花火と告白
気力を失う源吾を、深雪は東へ歩かせ隅田川の川開きへ導いた。藍の夜空に緑がかった大輪が静かに咲き、源吾は「火消の業の先には泣き顔、花火師の業の先には笑顔」と涙し、自責と恐怖、そして火事が無くなることへの卑小な恐れまで吐露した。深雪は「辞めてもよい、何をしても生きていける、支えさせてほしい」と抱き寄せ、源吾は嗚咽して膝をつき、夏の気配の中で胸の澱を吐き出したのである。
六年の荒廃と夫婦の沈黙
退転後、非役だった鵜殿が火消頭を乗っ取り、六年のうちに源吾が育てた組織は面影を失った。被害を思えば胸は締め付けられた。囲炉裏の火を前に右手甲の火傷を撫でる源吾は、深雪の淹れた熱い茶に現を戻される。仲睦まじい条件は備えながらも、婚礼の儀も無く月日が過ぎ、言葉は減っていた。片付けに立つ深雪の背を見つめ、源吾は静かに茶を啜ったのである。
第五章 雛鳥の暁
一
世間の変化と「ぼろ鳶組」の呼称
明和八年の夏を境に新庄藩火消への眼差しが変わり、童が加入を願い、翁や嫗が水を勧め、職人や商人も声を掛けるようになった。相も変わらず見窄らしい装いで「ぼろ鳶組」と呼ばれ続けたが、その語には嘲りよりも敬意と愛着が混じり始めていたのである。
北条六右衛門の疑義と左門の説明
二度目の秋、北条六右衛門と左門に呼ばれ、源吾は火付け多発と自作自演の嫌疑を告げられた。下手人「狐火」の出没が源吾の復帰時期と符合すると指摘され、目をつけられた相手が悪いと左門は苦い顔で語った。
長谷川平蔵の来訪と嫌疑
まもなく火付盗賊改方頭となる長谷川宣雄(平蔵)が源吾宅を訪れ、小諸屋の件や鳥越蔵之介の殉職を挙げて疑いを質した。利得は名声と加持星十郎の獲得だと突き、番付にまで目を通す念の入れようであったが、平蔵の眼差しは終始揺らがなかった。
狐火の手口と平蔵の見立て
平蔵は蔵に朱土竜を仕込み、犬を押し込み、炭で気を奪って時間差で紙に着火させる外道の手並みを耳打ちした。常人離れの火の知識と狡猾さを備えた狂気の所業と断じ、源吾の人柄を見て疑いは遠のいたと明言したのである。
深雪の進言と嫌疑の払拭
深雪は「夫は強くないからこそ人の痛みが分かる」と静かに言い切り、無用の詮議を止めるよう求めた。平蔵は腹を抱えて笑い、「渡辺綱」と称して度胸を賞し、嫌疑は晴れたと告げた。さらに深雪は田沼意次への所感を問うて知的な憧憬を覗かせ、平蔵は百年先を見る老中と持ち上げて応じた。
平蔵の託宣
改めて平蔵は狐火に勝手はさせぬと誓い、万一の取り逃がしには源吾に討ち止めを託した。源吾は不安を押し退け、力強く頷いて応えたのである。
二
訓練後の非番と加賀藩天文座談
神無月に入り火消最繁忙期となり、源吾は厳しい訓練の後、新之助と非番の酒の約束を交わした。星十郎は加賀藩邸の天文座談会に通っており、不在であったのである。
日本橋の爆発と奔走
日本橋へ向かう途上、乾いた破裂音と地鳴りが連続し、源吾は即座に出動に転じた。土蔵群の一角で爆音とともに火球が乱舞し、土壁に風穴が穿たれ、内側から火焔が噴き上がる異様な現場であった。
水で勢いを増す怪火
炎は漆喰壁にまとわり付き、通常より熱く、水を浴びせるほど勢いを増すという怪異を示した。源吾は匂いの欠如から油ではないと断じ、理解不能の火勢に身を固くしたのである。
い組・白狼金五郎の被災
日本橋い組を率いる白狼・金五郎が定石どおり鎮圧に着手したが、隣蔵の扉周りが爆炎に吹き飛び、金五郎は火達磨となった。救出ののちも重篤であり、現場は地獄絵図の様相を呈した。
加賀鳶の合流と砂による制圧
大音勘九郎率いる加賀鳶が到着し、星十郎は火の正体を瓦斯と看破した。水が効かぬと見た源吾と勘九郎は砂で覆う策に切り替え、新庄藩火消も砂の手配と搬送に従事し、三刻余を費やしてようやく鎮火に至ったのである。
白狼の逝去と平蔵の再訪
三日後、金五郎は全身の火傷がもとで息を引き取った。葬儀ののち、長谷川平蔵が来訪し、星十郎の洞察に礼を述べつつ情報を開示した。焼失蔵は材木商い美濃屋で、玉皮の製作も手掛けており、多くの職人や花火師が嘆いていたという。
狐火の木札と深雪の一言
平蔵は下手人が残す「狐」の木札が円形である極秘を示し、模倣犯識別の意図を語った。深雪は大火中に木札が焼け残る理を疑問視し、源吾は木札の残置位置に風読みの計算が働いていると閃いたのである。
下手人像の絞り込みと結論
水で増す怪火は亜鉛由来の瓦斯と推測され、候補は学者や砲術家に及んだが、先の風を読み高精度で仕掛けを成す者となれば範囲は狭まった。稲荷=狐の縁、玉皮に通じる材の扱い、そして風読みに長けた技を総合し、源吾は下手人を花火師と断じたのである。
三
平蔵が掴んだ鍵屋の闇
半月足らずで長谷川平蔵が不穏な花火師の線を掴み、鍵屋に二人の天才がいたと語った。温和な清七は今も手代として研鑽を重ね、寡黙で才気煥発な秀助は番頭にまで上り詰め、弥兵衛から焔の鬼と評されていたのである。
秀助の変化と家族の幸福
秀助は奉公人のお香を娶り、娘お糸を授かって性情が和らぎ、後進を導くまでに変わっていった。迷子癖のあるお糸のため自作の赤い鈴を拵え、いつか赤い花火を見せると約したのである。
神才・清吉の台頭と玉屋の構想
清七の子清吉は見るだけで一玉を組む才を示し、独創の調合法で新発色を生み出した。弥兵衛は将来の暖簾分けに玉屋の屋号まで与えようとし、家中は清吉の新作、赤味を帯びた破裂後に火玉が泳ぐ仕掛けに沸き立っていた。
試し揚げの悲劇
隅田川の試し揚げで秀助は危険を再三進言した。赤の鮮明化には瞬時の腐蝕が要り、あるいは火薬増量で極めて危険だと断じ、筒仕込みの蜂は未だ早いと述べた。清吉は蜻蛉と名付け己の発案と張り合い、弥兵衛とお糸の期待もあって強行された。着火の刹那、玉は飛翔せず筒中で暴発し、火玉が飛散した。鈴の音が鳴る中、お糸が胸に直撃を受けて炎上し、秀助は覆い被さって消火を叫んだが水の用意はなく、後手に回った。お糸は鈴を握ったまま微笑を残して瞼を閉じ、お香は魂の抜け殻のようになり、ほどなく井戸に身を投げたのである。
秀助の出奔と狐火の輪郭
お糸の死の当日に秀助は書置きもなく出奔し行方は杳として知れなかった。鍵屋も火消も口を噤み、清吉の天才を守るために金が動いたと平蔵は見ていた。源吾は淡い緑の花火を秀助のみの秘伝と聞き、深雪と見た隅田川の花を思い出して胸を衝かれたのである。
黒幕の気配と平蔵の策
秀助が下手人であるならば、なぜ鍵屋を先に狙わぬのかという源吾の疑問に、平蔵は材料調達の困難から背後の糸引きを示唆した。憎悪に付け込む者がいると読み、己に考えがあると協力を求め、源吾は即座に応じた。平蔵は火鉢に落とした火種の熱を見つめ、たったこれだけでも熱いと呟き、己の情を押し殺していたのである。
四
特別編成組の設立
平蔵は狐火に対抗するため、火盗と外様藩の火消からなる特別編成組を組織した。幕閣に働きかける代わりに田沼意次の内諾を得て、極秘裏に実施されたのである。新庄藩からは源吾・彦弥・星十郎、加賀藩からは大音勘九郎ら四名、さらに肥後藩・仁正寺藩からも選抜され、精鋭十余名が揃った。指揮は勘九郎の推挙により源吾が執ることになった。
狐火との遭遇
六日目の夜、横山町で火の手が上がり、捕方が路地を封鎖していた。現場に現れたのは七名の覆面の男たちであった。捕方は斬り結ぶが苦戦し、戦場は混乱を極めた。源吾ら火消は敵を斬るのではなく、まず炎を抑えることに専念した。
怪火と秀助の姿
彦弥が屋根に上がり消火を試みたが、敵の一人が金属粉を撒き散らし、炎が水を伝って襲いかかった。常軌を逸した火勢に誰もが呆然とする中、星十郎は粉の性質を見抜き、塩での鎮火を提案した。源吾が塩を撒いて炎を相殺すると、下手人は狼狽した。その声から、源吾は下手人の一人が秀助であると確信した。
秀助の逃走と組織の影
激しい火炎の中で下手人らは突破を図り、秀助を含む三名が逃走した。平蔵の指揮で四名は捕縛、二名は斬られたが、捕えた者たちは舌を噛んで自害した。残された証拠からも、彼らが特殊な訓練を受けた集団であることは明らかであった。
平蔵の確信と源吾の苦悩
翌日、平蔵は源吾に狐火の背後に組織の存在を示唆した。狙われた商家は田沼意次の方針を支持する者ばかりであり、政治的な思惑が絡んでいると考えられたのである。源吾は炎に向かう勇気を持ちながらも、心の底では火を恐れる己を直視し、再び絶望に囚われていった。
田沼意次との邂逅
年が改まり、源吾は平蔵に導かれて田沼意次と対面した。田沼は女子の社会進出をも見据えた革新的な理念を語り、源吾に「狐火の火を必ず止めよ」と託した。民を我が子のように思うその姿勢に源吾は感銘を受けたが、同時に火への恐怖を克服できぬ自分への苦悩を深めることとなった。
五
流言の拡散と標的化
「火付けの下手人は火消、最有力は松永源吾」との流言が突如として江戸一円に広がる。田沼意次と長谷川平蔵までも黒幕扱いにする荒唐無稽な噂であるが、拡散速度と浸透の深さから、強い影響力を持つ勢力の企図と察せられるである。
大目付の詮議と座敷牢
三日後、大目付・池田政倫の手勢が源吾宅を包囲。現場に落ちていた「源吾の煙草入れ」を証拠に連行を迫る。源吾は潔白を主張し自ら同行。長谷川は池田に怒鳴り込み、極秘の連合編成を己の独断として証言し閉門処分を受ける代わりに、多藩精鋭の証言を取り付ける。嫌疑は完全には晴れず、源吾は新庄藩上屋敷の座敷牢に監置となるである。
源吾の内的崩落と深雪の支え
幽閉下の源吾は、火への恐怖と「火を消す快楽」への自覚の狭間で自責を深め、悪夢に苛まれる。面会した深雪は一切の疑いを退け、ただ手を握り支えるである。
ぼろ鳶の動揺と新之助の決意
「御頭不在で訓練どころではない」と憤る彦弥に、新之助は「今こそ鍛える時」と応じ衝突。彦弥は去るが、配下には復帰を命じており、隊は辛うじて維持される。新之助は書類仕事と巡察に身を入れ、父・蔵之介の地道な働きを遅れて理解し始めるである。
如月二十九日・目黒発火
半鐘が鳴り響き、新之助は目黒・行人坂大円寺へ。人海の中で怪しい黒衣の男(僧装の偽装)を認め「狐火」と呼ばわるも見失う。寺内の楠から内部発熱の黒煙が噴出する怪異。方角火消・丹羽家が到着し、新之助は十名の応援を得て上大崎の異常な土蔵へ向かうである。
朱土竜の兆しと決断
土蔵は外から塗り固められ、内部は高温。犬の悲鳴が十数、しかも人の可能性も捨て難い。定石は冷却待ちであるが、新之助は「命を救うのが火消の本分」として開扉を決断。鳶口でこじ開けた刹那、朱土竜が爆ぜ、紅蓮が渦を巻いて新之助を呑むである。
訃報と江戸の臨界
同刻、座敷牢の源吾のもとへ左門が駆け込み、「新之助がやられた」と告げる。江戸中に半鐘が重なり、爽やかな晴天の朝は、一転して「江戸百万人にとって忘れえぬ日」へと転じ始めるである。
六
新之助の負傷と源吾の絶望
左門は格子越しに、新之助が朱土竜の爆発で負傷したと告げた。火傷は軽かったが頭部を強打し、出血は甚大であった。犬を救うために扉を開けたと聞いた源吾は衝撃を受け、自らの教えを守ろうとした若者に対し、己なら炎に怯えて見過ごしたのではないかと慟哭したのである。
左門の叱咤と火喰鳥の記憶
源吾が「火は消せぬ」と嘆いた時、左門は激昂し「宝暦八年、飯田町の火事」を持ち出した。少年であった源吾が商家に飛び込み命を救ったことを思い起こさせ、「立ち直れることを教えたのは火喰鳥だ」と叫んだ。その言葉に源吾の瞳は次第に光を取り戻したのである。
六右衛門の登場と切り放ち
そこへ江戸家老・北条六右衛門が現れた。目黒行人坂の火災が大火に発展しつつあると告げ、源吾に切り放ちを命じた。切り放ちは火事の際に囚人を一時的に放ち、公の役目を果たせば罪を減ずる仕組みである。源吾は一つでも多く命を救うと誓い、解き放たれた。
深雪との再会と決意
門前で待っていた深雪は羽織を手渡し、「あのような外道と旦那様は違う」と涙を滲ませて支えた。源吾は強く抱き寄せ「ただ今」と応じたのち、火消羽織を翻し再び現場へ向かった。背に描かれた鳶の意匠が蒼天に舞い、深雪はその小さくなる背を見送り続けたのである。
第六章 火喰鳥
一
町火消との衝突と麻布への到達
新庄藩火消は広尾で町火消に阻まれ、疑惑を理由に火に近づけぬと拒まれた。逃げ惑う群衆は妊婦を蹴り倒し、僧侶が子を踏み越えるなど地獄絵図であり、星十郎はその惨状を八幡地獄と形容した。寅次郎の先導で麻布へ向かったが、到着時には家々に火が移り手の施しようがなかった。
守る対象を巡る選択
星十郎は御城か日本橋の二択を示し、火消たちの多くは御城を守るべく北上していた。寅次郎もまた武家屋敷と妻子を優先すべきと主張したが、源吾は人命の集中する日本橋防衛を決断した。深雪を信じると語り、鳶たちの士気を奮い立たせた。
幕府使者の到来と源吾の反発
幕府使者が赤坂紀伊家屋敷守護を命じたが、源吾は田沼の不在を理由に従わず、日本橋を守ると宣言した。鳶たちはその覚悟に呼応し、大音声で鬨を上げた。使者は激昂したが、源吾はぼろ鳶としての矜持を示した。
深雪の避難誘導
半蔵門周辺は避難者で混乱し、家財を抱える者で道が塞がれていた。深雪は必死に荷を捨てるよう訴え、鳥越新之助の負傷を例に命の尊さを説いた。やがて避難者たちは家財を手放し、北への避難が進み始めた。途中で深雪は高貴な羽織を着た男に声を掛けられ、それが田沼意次本人であると察した。
彦弥とお七の再会
屋根を飛び渡る彦弥は避難中のお七と再会し、消防に励むよう叱咤される。彦弥は自らの弱さを告白しつつも奮い立ち、再び火勢に立ち向かう覚悟を固めた。
新庄藩火消の奮戦と彦弥の復帰
新庄藩火消は堀を背に防火に努めたが、炎が水面を走る怪異に襲われ、源吾は危機に陥った。そこへ彦弥が舞い戻り、源吾を救った。纏を受け取った彦弥は屋根に上り、火勢に立ち向かい鳶たちを鼓舞した。
永代橋の危機と舟橋の策
隅田川に火が移り永代橋が炎上、人々が川辺に押し寄せ溺死の危険が高まった。源吾らは越前の舟橋を参考に戸板を利用し、鳶が水中で支える即席の橋を築いた。寅次郎は己の体力を顧みず支え続け、限界に達した時、力士仲間の達ヶ関らが駆け付け支援した。
避難完了と感謝の声
達ヶ関らの助力で舟橋は強固となり、多くの避難者が渡河に成功した。人々は新庄藩火消に感謝を叫び、鳶たちは涙を浮かべながらも応えて火中へ戻っていった。源吾は止めると高らかに号令し、仲間と共に次の戦場へと進んだ。
二
炎の北端を探る進軍
源吾らは炎の北端を追い、飯田町を経て浅草方面へ向かっていた。火は紙に墨を垂らしたように枝分かれし、浮島のような延焼防止地を残しながら北東へと広がっていた。浅草で食い止めるべく火消が集まっていたが、飯田町では救援を乞う鳶が源吾に縋りついた。
松平定火消屋敷の炎上
導かれた先は源吾の古巣である松平定火消屋敷であった。三方は安全で、半刻あれば消せるはずの現場だったが、杜撰な消火で炎は拡大していた。指揮を執っていたのは鵜殿であり、武家の慣習に従い「門を残せば咎め無し」と執拗に門の保護を叫んでいた。
寅次郎の暴発と制止
寅次郎は過去の因縁で鵜殿を憎み、暴発しかけた。源吾は必死に抱き止め、「俺がいる」と繰り返して宥めた。寅次郎は涙ながらに踏み止まり、源吾に全てを託した。
門を守る決断
鵜殿は怯えと懇願を繰り返したが、源吾は「門を残せば命が救われる」と判断し、組を指揮した。彦弥は屋根を飛び、寅次郎は火傷を恐れず柱を折り、星十郎は自ら玄蕃桶を担いだ。半刻足らずで屋敷は全焼したが、門だけが残り、鵜殿は罪を免れることとなった。源吾は「犬の命でも見捨てぬ」と吐き捨て、火消の矜持を示した。
千住への進軍と応援の到来
北上した一行は千住を防衛線と定めた。浅草は火の海となり、他の火消も続々と千住に集まった。そこへ島原藩、備中庭瀬藩、峯山藩、常陸牛久藩などの援軍が相次いで到着し、さらに「加賀鳶」の大音勘九郎も現れた。黒羽織の勘九郎は「西は任せろ」と告げ、源吾と並び立った。
千住での死闘と鎮火
加賀鳶と新庄藩を含む二十を超える火消組が千住で奮戦した。舟橋を渡して人々を避難させ、互いに協力し合って炎を押し返した。小塚原刑場付近を最終防衛線とし、四町も火を戻した末に鎮火を果たした。源吾は「火は止まった」と宣言し、人々は歓喜した。
本郷の火柱と駒込の危機
しかし雷鳴のような轟音と共に本郷で火薬が炸裂し、新たな大火が起こった。火は北東へ進み、避難した深雪や新之助らがいる駒込を脅かしていた。源吾は駒込救援を望んだが、浅草の鎮火を優先せねばならず、勘九郎が「駒込はお主らが行け」と託した。勘九郎は三頭の馬を提供し、源吾はその厚意を胸に配下と共に駒込へ駆けた。
三
駒込への避難と火柱の出現
深雪が火柱を目にしたのは、ようやく駒込に辿り着いた時であった。火元は本郷丸山町の道具屋与八宅とされ、強風に煽られた炎と煙は駒込に迫っていた。藩士の多くは公文書の搬出のため上屋敷に向かい、ここには中屋敷や下屋敷の藩士とその家族が百名ほど集まっていた。昏睡状態の新之助は戸板に乗せられて運ばれていた。
深雪の決断と人々の動揺
西ヶ原で避難が詰まり、逃げ場を失った一団に深雪は「ここで防ぐ」と提案した。素人に無謀と反発する声もあったが、森川房次郎の妻・昌が子を託して加勢を申し出ると、女たちも次々に賛同した。侍たちも覚悟を決め、柱を折って延焼を防ぐ作業に挑んだ。
新之助の覚醒と指揮
試みは失敗が続いたが、意識を取り戻した新之助が立ち上がり、火消の知識を示して縄の結び方や折れやすい柱を指示した。顔色は土のように悪く、包帯も血に染まっていたが、それでも「命懸けは今に始まったことではない」と微笑んで皆を励ました。深雪は涙を流しつつその姿を見守り、新之助は次々と柱を倒して火除け地を作り出した。
源吾の帰還と合流
炎が迫る中、辻から現れたのは煤に塗れた新庄藩火消の一団であり、先頭の馬上には源吾の姿があった。深雪は涙で視界を曇らせながら夫を迎え、新之助は源吾に「素人火消は奥方様の発案」と伝えた。源吾は「火の神に人の強さを思い知らせてやる」と咆哮し、配下を率いて突撃した。
駒込での死闘と鎮火
新庄藩火消は獅子奮迅の働きを見せ、わずか一刻で七十棟以上を打ち壊して火を押し返した。避難民たちは歓声を上げ、深雪や昌は涙ながらに声援を送った。やがて炎は駒込を越えられず、歓喜の中で源吾は「これ以上は来ない」と告げた。深雪は「人は何度でもやり直せる」と応え、夫婦は再び希望を分かち合った。
残火処理と新たな疑念
鎮火後、残火の見回りと遺体の処理が始まった。黒焦げの遺骸を前に源吾が手を合わせる中、新之助は「狐火を見た」と告げた。彼は以前小諸屋で出会った僧が朱土竜事件に関わっていたと推測し、さらに行人坂でもその姿を見たと主張した。源吾は半信半疑であったが、新之助は「奴は再び鍵屋を狙う」と断言した。
四
焼け跡と狐火の予測
弥生の初日、江戸は焼け跡と化していた。源吾は憤りを覚え、星十郎は徹夜で火付けの動きを推測した。残る町並みや風向きを踏まえ、狐火が馬喰町を狙うと断定された。源吾は星十郎を信じ、行動を開始した。
馬喰町での遭遇
馬喰町に到着した新庄藩火消は数を減らしていた。彼らはに組の小組頭・宗助と出会い、当初は反目されたが、源吾が事情を語り、宗助の父・宗兵衛との縁を示したことで協力を得た。直後、町で新たな出火が確認され、一行は急行した。
狐火の仕掛けと奮戦
火元では青白い炎が猛り、硫黄を大量に用いた仕掛けであることが判明した。彦弥や寅次郎も合流し、五十名の勢力が結集した。源吾は弔い合戦として指揮を執り、新庄藩火消は周囲の火消をも巻き込み奮闘した。
偽装火消の露見
源吾は金属音を手掛かりに、青木甲斐守の家中を名乗る一団の正体を暴いた。彼らは放火犯であり、新之助の剣術により戦闘は優位に進んだ。しかし首領格と秀助が逃走し、源吾は秀助を追撃した。
秀助との対峙
源吾は追跡の末、秀助を追い詰めた。秀助は鈴の音で正体を看破されたことを認め、火を以て復讐を遂げようとした。激闘の末、源吾は秀助の右手を斬り落とし、彼を無力化したが、なお復讐心は消えていなかった。秀助は藤五郎と名乗る仲間に助け出されるが、仲間割れから爆炎を起こし、重傷を負った。源吾は鈴を拾い、秀助に託すこととなった。
別れと混乱の収束
秀助は二月の猶予を求め、償いを誓った。源吾はその願いを受け入れ、彼を見逃した。現場では火付盗賊改方が残党を捕縛し、長谷川平蔵が黒幕解明を誓った。新之助の剣の腕前も明らかとなり、源吾は彼の真価を知った。戦いの後、新之助は「ただの火消侍」と語り、青空を仰いだ。
五
大火の収束と被害
三日間に及ぶ大火はようやく収束した。焼失は九百三十四町、大名屋敷百九十六、寺社三百八十二に及び、死者一万四千七百余、行方不明四千人余という惨状であった。明暦の大火に次ぐ規模でありながら死者数が抑えられたのは火消の奮闘によるものであった。しかし源吾は家を失い親族と逸れた人々の姿を前に無力感を覚えていた。
平蔵の報告と一橋家の影
卯月半ば、長谷川平蔵が訪れ、首領藤五郎の名を吐かせたことを伝えた。さらに黒幕は一橋徳川家と示唆されたが、証拠不十分で糾弾には至らなかった。田沼意次の存在を恐れた一橋家の動きと見られたが、結果は牽制の域を出なかった。
六右衛門の覚悟
平蔵は北条六右衛門が幕閣に呼び出され、源吾の責任を問われた件を伝えた。六右衛門は自らの采配であったと庇い、閉門処分で済んだ。若き日「仏の喜之助」と呼ばれた温厚な人柄が、己を犠牲にして部下を守る覚悟へと変わったと語られた。
花火と秀助の捕縛
明和九年卯月晦日、江戸の夜空に赤や淡緑の花火が打ち上げられた。それは秀助の仕業であり、鎮魂と復讐の入り混じった行動であった。翌日、隅田川で花火を打ち上げていた秀助は平蔵に捕縛された。秀助は自らを真秀と名乗り、供述は曖昧であったが罪を認め、源吾宛に鈴を託した。その後、六月二十一日、小塚原で火刑に処された。
出初式と再起
明和十年正月四日、出初式が挙行された。ぼろ鳶組は訓練披露、梯子乗り、木遣りに加え、子どもへの防火講座を実施した。新調の揃い衣装と勇壮な働きは観衆を魅了し、加賀鳶に並ぶ盛況を博した。国元から届いた文には、火喰鳥松永源吾、赤舵加持星十郎、谺彦弥、荒神山寅次郎、襤褸鳶鳥越新之助の名が番付に記され、羽州ぼろ鳶組の奮闘が称えられていた。
同シリーズ


同著者の別作品
イクサガミ



その他フィクション

Share this content:
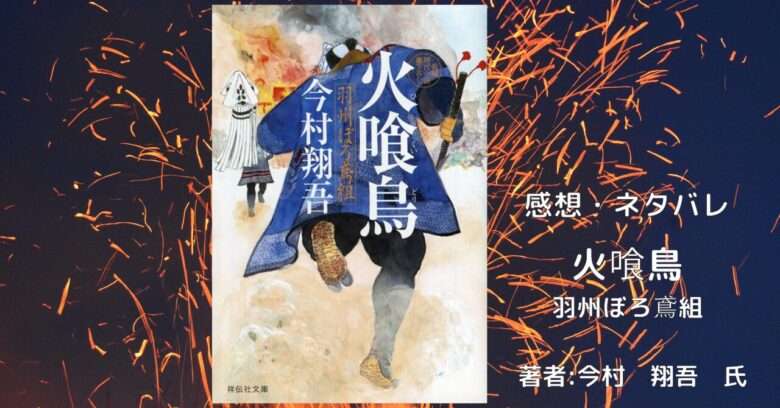

コメントを残す