物語の概要
ジャンル:
明治時代を舞台とした歴史時代小説かつバトルロワイヤルである。主人公らは「こどく」と呼ばれるデスゲームに巻き込まれ、東海道を巡る生存競争に挑む。金、命、誇りをかけた壮絶な戦いが展開される。
内容紹介:
明治11年、京都・天龍寺に“武技に優れた者”を対象に金十万円の機会を与えるという怪文書が掲示され、292人の刀の腕自慢が集まった。彼らは「こどく」と名付けられたゲームの参加者となり、点数を奪い合いながら東海道を東京へと向かうことを強いられる。主人公・嵯峨愁二郎は、家族のために参加し、命懸けの旅に巻き込まれた12歳の少女・双葉を守りつつ進むことになる。
主要キャラクター
- 嵯峨 愁二郎:本作の主人公。かつて剣客で、京八流の後継者の一人。家族を救うため大金を求めて「こどく」に参加する。奥義「武曲」の使い手であり、信念を胸に戦う剣士である。
- 香月 双葉:12歳の少女。母の病を治すために愁二郎と共に「こどく」を旅する。短剣を携え、聡明さと純粋さを併せ持つ存在である。
- 柘植 響陣:元伊賀同心で暗器使い。変装や方言の使い分けが得意で、ふたりと行動を共にしながら独自の視点を加える参謀的キャラクターである。
- カムイコチャ:アイヌ出身の青年戦士。神の子の名を冠し、弓矢の名手として双葉らを守る守護者的立場にある。
- 菊臣 右京:美形の剣士であり、正々堂々と戦う信念を重んじ、双葉を助ける際に誇りを示す理想的な武人である。
物語の特徴
本作の魅力は、剣豪たちが己の「信念」「誇り」「生の欲望」を胸に戦う「デスゲーム」形式の構造にある。単なるバトル小説ではなく、それぞれの動機が強烈に描かれ、敵対者であっても感情移入させる深い人間描写が光る。明治維新直後という武士が消えゆく時代背景が、刀を握る意味と生きる誇りを強調し、物語に重厚な説得力を与えている。
書籍情報
イクサガミ 天
著者:今村 翔吾 氏
レーベル:講談社文庫
ISBN:978-4065269862
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
斬れ。生き残れ。
デスゲーム×明治時代――大興奮の侍バトルロワイヤル開幕!
カバーイラスト/石田スイ(「東京喰種」「超人X」)
金か、命か、誇りか。
刀を握る理由は、何だ。
明治11年。深夜の京都、天龍寺。
「武技ニ優レタル者」に「金十万円ヲ得ル機会」を与えるとの怪文書によって、
腕に覚えがある292人が集められた。
告げられたのは、〈こどく〉という名の「遊び」の開始と、七つの奇妙な掟。
点数を集めながら、東海道を辿って東京を目指せという。
各自に配られた木札は、1枚につき1点を意味する。点数を稼ぐ手段は、ただ一つ――。
「奪い合うのです! その手段は問いません!」
剣客・嵯峨愁二郎は、命懸けの戦いに巻き込まれた12歳の少女・双葉を守りながら道を進むも、
強敵たちが立ちはだかる――。
感想
明治という時代を舞台にした、命がけの戦いが繰り広げられる物語である。幕末の動乱を生き抜いた者たちが、それぞれの思惑を胸に、大金を賭けた殺し合いに身を投じていく。そんなあらすじを聞いただけで、否が応でも胸が高鳴る。
物語の主人公、嵯峨愁二郎は、一子相伝の剣術を受け継ぐ剣士。彼は、義理の兄妹との殺し合いを強いられる運命から逃れ、幕末の京都で土佐藩の護衛として生き残った過去を持つ。医師の妻と子供と平穏に暮らしていた彼が、再び刀を握ることになったのは、コロリという病に侵された家族を救うためだった。医療費を稼ぐために、彼は胡散臭い「こどく」という名の騒動に飛び込んでいく。
私が特に心惹かれたのは、愁二郎の生き様である。彼は、剣の腕は確かだが、決して好戦的な人物ではない。家族を愛し、平穏な生活を願う、ごく普通の男なのだ。しかし、愛する者を守るため、彼は再び修羅の道へと足を踏み入れる。その姿は、読者の心を強く揺さぶる。
物語には、愁二郎以外にも、様々な背景を持つ人物が登場する。幕府の御家人、隠密、そして幕末の志士たちの残骸。彼らは皆、それぞれの過去を背負い、それぞれの目的のために戦う。金のため、誇りのため、そして生き残るため。彼らの思惑が交錯し、物語は予想もつかない方向へと進んでいく。
戦闘シーンは、息をのむほど迫力がある。刀と刀がぶつかり合う音、血しぶき、そして命のやり取り。作者の描写力によって、まるで自分がその場にいるかのような臨場感を味わえる。しかし、この物語の魅力は、単なる殺し合いだけではない。登場人物たちの人間ドラマも、見逃せない要素の一つだ。
特に、愁二郎と双葉の関係は、物語に深みを与えている。愁二郎は、双葉を妹のように思い、守り抜こうとする。一方、双葉もまた、愁二郎を頼り、彼と共に生き抜こうとする。二人の絆は、過酷な運命の中で、より一層強くなっていく。
『イクサガミ 天』は、単なる時代小説ではない。これは、生きることの意味、家族の愛、そして人間の強さを描いた物語である。読後、私は深い感動と、生きる勇気をもらった。この作品に出会えて、本当に良かったと思う。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
登場キャラクター
嵯峨愁二郎
流浪の浪人であり、武芸に優れた人物である。妻子を虎狼痢から救うために「こどく」に参加した。冷静かつ慎重な性格で、仲間や子供を守ろうとする責任感が強い。
・所属組織、地位や役職
特定の組織に属さず、元武士で浪人の立場。
・物語内での具体的な行動や成果
双葉を救出し協力関係を結んだ。響陣やカムイコチャと邂逅し、木札を集めながら関宿を突破した。尾鷲太郎を討ち取り、弥兵衛の協力で京を脱出した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
京八流の継承戦から逃亡した過去を持つ。蠱毒の進行とともに再び「刻舟」として剣を執る覚悟を固めた。
双葉
十二歳の少女で、父を失い母が病に倒れたため「こどく」に参加した。未熟ながらも武芸の基礎を学んでおり、気丈で強い意志を持つ。
・所属組織、地位や役職
旧亀山藩士の娘で、現在は参加者の一人。
・物語内での具体的な行動や成果
愁二郎に助けられ、以後は共に行動。剣術の稽古を受け、戦いへの覚悟を固めた。宮宿で三助に誘拐される。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
弱者から戦いに挑む覚悟を持つ存在へ変化しつつある。愁二郎にとって守るべき存在である。
響陣
謎めいた達人で、声色を自在に操る忍びの素養を持つ。軽妙な性格ながら計算深く、愁二郎に同盟を持ちかけた。
・所属組織、地位や役職
元伊賀同心とされる。
・物語内での具体的な行動や成果
愁二郎と双葉を救い、木札を譲与した。情報収集や変装を駆使して活動し、赤山・寛松・進次郎の処遇を検証する役割を担った。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
同盟者として愁二郎と双葉に影響を与える存在となった。
槐
蠱毒の主催側に属する人物で、参加者に競技の規則を示した。冷徹で威圧的な態度を見せ、黄金の仏像を提示して懸賞の真実性を示した。
・所属組織、地位や役職
蠱毒の主催者の一員。
・物語内での具体的な行動や成果
競技の掟を発表し、逃亡者を処刑させて参加者を威圧した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
権威を持つ立場として競技全体を統率している。
安藤神兵衛
京都府庁第四課の役人であり、撃剣の達人と称されていた。正義感を持ち、主催者を捕縛しようとした。
・所属組織、地位や役職
京都府庁第四課所属。
・物語内での具体的な行動や成果
天龍寺で槐に挑んだが、護衛の剣士に瞬時に斬殺された。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
参加者に主催者の圧倒的な力を示す犠牲となった。
カムイコチャ
アイヌの若き村長で「神の子」と呼ばれる弓の達人である。村の存続のため十万円の懸賞に望みを託した。
・所属組織、地位や役職
北海道のアイヌ村長。
・物語内での具体的な行動や成果
鈴鹿峠で愁二郎と邂逅し、矢の一撃で追手を倒した。木札を収集し、先行して進んだ。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
その弓技は愁二郎に神業と評され、強者の一人として認識された。
貫地谷無骨
幕末・維新の戦乱で恐れられた剣客であり、「乱斬り無骨」と呼ばれる狂気の浪人である。
・所属組織、地位や役職
特定の組織に属さない浪人。
・物語内での具体的な行動や成果
蠱毒の場で多数を斬殺し、愁二郎を宮宿で襲撃した。菊臣右京を斬殺し、首を晒した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
戦いそのものを楽しむ異常な存在として参加者の恐怖の中心となった。
菊臣右京
花山院家の家僕であり、軟弱に見せかけながら剣の秘伝を受け継いだ剣士である。正義感を持ち、無骨に挑んだ。
・所属組織、地位や役職
花山院家の家僕。
・物語内での具体的な行動や成果
双葉を救い、無骨と対峙した。太刀四十二カ条の奥義を放ったが斬殺された。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
志を貫いたが、花山院家の裏切りによって浪人となり、蠱毒で最期を迎えた。
三助
愁二郎の義弟で京八流の一人。耳に関わる奥義「緑存」を継いでいる。
・所属組織、地位や役職
京八流の一員。
・物語内での具体的な行動や成果
宮宿で双葉を誘拐し、愁二郎と対立した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
蠱毒に参加する義弟の一人として愁二郎の前に立ち塞がる存在となった。
彩八
愁二郎の義妹であり、京八流の一人である。女ながらも奥義「文曲」を受け継ぎ、愁二郎に深い憎しみを抱いている。
・所属組織、地位や役職
京八流の一員。
・物語内での具体的な行動や成果
鈴鹿峠で愁二郎と対峙し、文曲を駆使して戦った。愁二郎を「刻舟」を継がず逃げた卑怯者と非難した。戦いの最中に双葉が割って入り、一時的に停戦した。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
兄弟の生存と参加を告げ、四蔵や三助、甚六の存在を明らかにした。愁二郎にとって避けられない因縁の相手である。
化野四蔵
愁二郎の義弟で、京八流の一人である。冷徹で実力に優れ、異能の剣技を持つ。
・所属組織、地位や役職
京八流の一員。
・物語内での具体的な行動や成果
蠱毒に参加し、三人の刀を立て続けに折る技を見せた。強者として響陣からも名を挙げられた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
愁二郎にとっては過去の因縁を背負う義弟であり、必ず相まみえる存在と予感されている。
甚六
愁二郎の義弟であり、京八流の一人である。腕力に優れ、愁二郎からも警戒される存在である。
・所属組織、地位や役職
京八流の一員。
・物語内での具体的な行動や成果
物語内で直接の行動は描かれていないが、彩八の言葉により参加していることが示された。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
愁二郎の予想では必ず強敵となると見られている。
尾鷲太郎
三重県庁第四課の役人を名乗ったが、実際には偽者であった。武芸に優れた危険人物である。
・所属組織、地位や役職
三重県庁第四課を騙る偽警官。
・物語内での具体的な行動や成果
愁二郎と双葉を取り調べると偽り、弥兵衛を人質にして迫った。愁二郎の抜き打ちで右手を斬り落とされ、首を刺し貫かれて討たれた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
所持品から警官の制服と木札が見つかり、警察官すら蠱毒に参加している実態を示した。
弥兵衛
京の宿「熊屋」の主であり、愁二郎の旧知である。誠実で恩義を重んじる人物である。
・所属組織、地位や役職
京の宿「熊屋」の宿主。
・物語内での具体的な行動や成果
愁二郎と双葉を匿い、尾鷲太郎との戦闘でも助けとなった。使用人の通報を受け、裏口からの脱出を手助けした。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
過去に愁二郎に助けられた恩を語り、財布と餞別を託して別れた。
立川孝右衛門
旧加賀藩士であり、天龍寺で愁二郎と出会った。強欲で猜疑心の強い人物である。
・所属組織、地位や役職
旧加賀藩士。
・物語内での具体的な行動や成果
愁二郎と双葉に同行を願い出たが、渡月橋で抜き打ちを仕掛けた。愁二郎に見抜かれ、逃走して川へ転落し消息を絶った。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
裏切りによって愁二郎の警戒心を深めさせる役割を果たした。
番場
熊野出身の漁師で、裏では強盗も働いていた。残忍で粗暴な性格を持つ。
・所属組織、地位や役職
漁師であり強盗の常習者。
・物語内での具体的な行動や成果
七里の渡しで船を襲撃し、響陣と水中で戦った。最後は討たれて海に沈んだ。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
部下を従えて札を集めていたが、最期は敗北した。
赤山末酒
今治出身の医者であり、博打による借金を抱えていた。困窮の末に蠱毒へ参加した。
・所属組織、地位や役職
医者。
・物語内での具体的な行動や成果
宮宿で捕縛され、愁二郎と響陣の尋問を受けた。蠱毒に参加した理由を借金返済のためと語った。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
実験として警察に突き出され、掟破りが国家の庇護で通用するかを試す対象となった。
加本寛松
金貸しの一味であり、監視役として赤山に同行していた。金銭目的で冷酷な性格を持つ。
・所属組織、地位や役職
金貸しの手先。
・物語内での具体的な行動や成果
赤山を監視し、毒を利用して参加者を殺し札を奪う行動を取った。宮宿で捕らえられ、警察に引き渡された。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
札を持ったまま引き渡され、蠱毒主催者の処遇が試される対象となった。
狭山進次郎
御家人の子であり、父が営む居酒屋が虎狼痢で経営困難となり、借金返済のため参加した。
・所属組織、地位や役職
御家人の子。
・物語内での具体的な行動や成果
宮宿で捕らえられ、響陣と共に行動することとなった。札が一枚しかなく、通過条件を満たせないまま進ませる検証対象となった。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
札不足のまま進めるかを試す実験対象として扱われた。
志乃
愁二郎の妻であり、医術に優れた人物である。困窮しながらも地域の治療に尽力している。
・所属組織、地位や役職
医者(女医)。
・物語内での具体的な行動や成果
虎狼痢に苦しむ人々を無償で治療し、四十九人を救おうとした。適塾で緒方洪庵の門下として学んだ経歴を持つ。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
医術への情熱を持ち続け、愁二郎が「こどく」に参加する理由となった。
幻刀斎
京八流において逃亡者を狩る役割を持つ存在である。詳細は不明だが、圧倒的な力を備えているとされる。
・所属組織、地位や役職
京八流の関係者。
・物語内での具体的な行動や成果
愁二郎や四蔵の回想に登場し、逃亡者に抗う術がないほどの力を持つと語られた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
京八流の掟を背負う象徴的な存在として認識されている。
西郷
前年に死亡したとされるが、豊国新聞の噂により生存説が広まった人物である。
・所属組織、地位や役職
元薩摩藩士。
・物語内での具体的な行動や成果
直接の登場はないが、豊国新聞を通じて「同志を集めている」との憶測が流れた。
・地位の変化、昇進、影響力、特筆事項
豊国新聞の信憑性を高める一因となり、噂の象徴として存在している。
展開まとめ
序ノ章
豊国新聞の出現と不可解な噂
明治十一年二月、東京に正体不明の新聞「豊国新聞」が出回り、噂が広まった。この新聞は既に千八百六十七号と記され、長期発行されていたかのように見えたが、誰も存在を知らなかった。内容には、五月五日に京都天龍寺境内へ武技に優れた者を集め、金十万円を与えるという告知が記されていた。当時の巡査初任給から換算して二千年以上分に相当する金額であり、悪戯や政治的陰謀説が流れた。特に前年に死亡したとされる西郷が生存し、同志を集めているとの憶測も生まれた。
警察の回収と全国的な現象
翌日、東京市内に多数の警察官が動員され、新聞回収が行われたことが却って信憑性を高めた。この現象は同日に大阪、京都、名古屋、博多など全国各地で確認され、地方の小さな町にも同様に配布されていた。各地で警察や官吏が回収に動いたが、天龍寺に向かう者は多くなかった。
天龍寺への参加条件と障害
警察が警戒している状況で現地に向かえば検挙されるのは明らかであり、加えて「武技に優れた者」という条件を満たす者は少数であった。それでも参加する者は、警察の網を突破できるほどの武術の達人か、極度の困窮者に限られると考えられた。
壱ノ章 相克の幕開き
天龍寺到着と過去の歴史
嵯峨愁二郎が天龍寺へ着いたのは五月四日午後三時頃であった。寺は元治元年の禁門の変で焼失し、その後も度重なる再建を経てきたが、明治十年の上知令により境内地の大半を政府に没収されていた。境内の復興は未完であり、戦火や政策の影響が色濃く残っていた。
下見と二月の新聞騒動の回想
愁二郎は境内の様子を探ったが警戒する官憲の姿はなく、噂が虚偽である可能性を感じた。それでも二月に東京から広まった「豊国新聞」の怪文と十万円の懸賞話を思い出し、金策のため京都まで来ていた。夜になって再訪すると、総門周辺には灯りが焚かれ、境内へ向かう者たちがいた。
参加者たちと豊国新聞
境内の広場には多くの男女が集まり、大半が刀や槍などの武器を携えていた。そこで出会った旧加賀藩士の立川孝右衛門から、金沢でも豊国新聞が配布されていたと知る。さらに参加者の中には西洋人の姿も見られ、この催しが広域的に影響していることが明らかになった。
槐の登場と金仏像の提示
仏堂から現れた男・槐が十万円獲得の話を真実と断言し、別の堂に安置された黄金の大仏像を示した。金槌で指を折って内部も純金であることを証明し、集まった者たちをさらに引き込んだ。
競技「こどく」の発表と掟
槐は参加者に木札を配り、番号と首紐を付けさせたうえで、東京までの競争「こどく」の掟を七項目で示した。途中での離脱や内容の漏洩は禁止され、通過地点や必要点数が定められた。点は他者から奪うことで増やすと告げられ、その手段は問わないと明言した。
逃亡者の処刑と緊張の高まり
開始前に逃亡を試みた数名が総門付近で黒装束の男たちに斬殺され、二名だけが戻った。この出来事で参加者たちは事態の危険性を悟り、場は異様な緊張感に包まれた。槐は命を懸ける覚悟を迫り、残り時間と共に参加者たちの動揺を極限まで高めていった。
安藤神兵衛の登場と衝撃の最期
混乱の中、京都府庁第四課所属の安藤神兵衛が御堂に歩み出て槐を捕縛しようとした。安藤は撃剣で名を馳せた達人であったが、槐の側近の覆面剣士に瞬時に首を斬られ、参加者たちに圧倒的な実力差を見せつけた。この一件で抵抗の意志を失う者が続出し、場は恐怖に包まれた。
双葉との邂逅と救出
開始の合図と共に乱戦が勃発し、愁二郎は人混みの中で十二、三歳の少女・双葉を見つける。屈強な男に狙われていた彼女を救い出し、協力関係を結んだ。双葉には武芸の心得があるものの非力であり、愁二郎は彼女を守りながら札の獲得を目指すことを決意する。
響陣との遭遇と助力
札を狙う三人組に囲まれた愁二郎と双葉は、謎の達人・響陣の介入で危機を免れる。響陣は木札を譲り、適度な点数保持が狙われにくいと示唆して去っていった。愁二郎はこの助言から点数保持の戦略性を理解する。
老人剣士との接触
総門近くで老人剣士が仲間らしき二人を瞬殺する場面に遭遇する。老人は愁二郎との戦いを避け、札を確保して立ち去ったが、その剣技は常人離れしており、響陣や槐の護衛と並ぶ異能の存在であった。
総門突破と迂回路の選択
総門では覆面の番人が札を確認し、不足者は容赦なく討たれていた。愁二郎と双葉は必要な札を示して通過を許される。多数の参加者が桂川沿いから洛中を目指すであろう中、愁二郎は待ち伏せを避けるため桂川を南下し、松尾神社方面へ回り込む迂回路を選択し、双葉を守りながら東京への道を進み始めた。
孝右衛門との再会と裏切り
天龍寺を出て桂川方面へ向かう途中、愁二郎と双葉は旧加賀藩士の立川孝右衛門と遭遇した。孝右衛門は相打ちで手に入れた札を持ち、同行を懇願する。愁二郎は警戒しつつも双葉の視線を受け入れたが、渡月橋で孝右衛門が突如抜き打ちを仕掛けてくる。愁二郎は即座に防ぎ、双葉に警戒心を教えるための行動だったと悟らせた。孝右衛門は逃走を試みて川へ転落し、そのまま姿を消した。
休息場所の確保と弥兵衛との再会
愁二郎は双葉に腹を括るよう促し、夜の洛中を抜けて旧知の宿「熊屋」へ向かう。宿主・弥兵衛と十一年ぶりに再会し、事情を明かさずに匿いを頼む。二階奥の部屋で休息を取ることになり、双葉の身の上を聞く準備を整えた。
双葉の過去と参加の理由
双葉は丹波亀岡出身で、父・香月栄太郎は旧亀山藩士で天道流武芸指南役だった。維新後は巡査となり、西南戦争で警視隊として戦い、敵剣士との戦闘で戦死。遺骨もなく、家は困窮し、母も虎狼痢に罹患。治療に必要な砂糖と塩の高騰で生活は逼迫し、賞金目当てに「こどく」へ参加したと語った。
愁二郎の事情と共通の目的
愁二郎もまた、府中で女医を営む妻と子を虎狼痢から救うために参加していた。妻は無償で治療を行い、貯えは底を尽き、感染した家族と地域の四十九人を救うために資金を求めていることを明かした。二人は病と貧困という共通の理由を持っていた。
今後への備えと不安
関宿通過に必要な三点を満たすため、愁二郎は二点不足のまま第二関門へ向かうことになる。鈴鹿峠での待ち伏せや、夜間移動・野宿の必要性を考慮しつつ、休息と情報整理を優先した。夜明けが近づき、愁二郎は変わりゆく時代と、武術を駆使して戦う現実の矛盾を思いながら残り百二十九名の参加者を見据えた。
式ノ章 懐疑の鎖
薊屋での休息と弥兵衛との語らい
愁二郎は弥兵衛から食事を受け、短い再会の中で刀の時代の終焉や自らの過去を語った。浪人として土佐に身を寄せた経緯を明かしつつ、再び刀を握ることとなった現状を苦々しく思った。晒に包んで持ち歩く必要性を確認し、双葉には自らが旧武士であったことを告げた。
偽警官・尾鷲太郎との対峙
三重県庁第四課を名乗る尾鷲が踏み込み、愁二郎と双葉を取り調べようとした。だが素性に不審があり、愁二郎は即座に斬撃を防ぎ応戦する。弥兵衛を人質に取られるも果敢に反撃し、抜き打ちで尾鷲の右手を斬り落としたうえ、首を刺し貫き討ち果たした。尾鷲の所持品から警官の制服と札が見つかり、警察官すら「こどく」に加わっている事実が明らかとなった。
弥兵衛との別れと京の脱出
宿の使用人が外部に通報したため、愁二郎と双葉は弥兵衛の導きで裏口から脱出した。弥兵衛は過去に愁二郎へ助けられた恩を語り、財布と餞別を託した。二人は三条大橋を越え、東海道の起点から東京へ向け進み始めた。道中、愁二郎は自らの出自が鞍馬で師に拾われ育ったこと、八人の義兄弟と共に武術を学んだ過去を双葉に打ち明けた。その中に化野四蔵という兄弟が天龍寺にいたことを語り、敵として再会することを予感した。
響陣の再登場と同盟の提案
宿に現れた響陣は、二度目となる札を差し出し、東京以降を見据えた同盟を持ちかけた。愁二郎は疑念を抱きつつも双葉と相談し、三日後の四日市で返答することを約した。響陣は自らが元伊賀同心であり、声色を自在に操る特異な技を披露した。忍びの存在を告げるその姿は、過去の影を背負いながらも軽妙で人懐こさを纏っていた。
次なる道程と残り人数
札を手に入れた愁二郎と双葉は、第二関門を目指すためにさらに前進する覚悟を固めた。札のやり取りが命の奪い合いと結び付いている現実を痛感しつつ、二人は百十五名に減った参加者の中で生き延びる決意を新たにした。
参ノ章 修羅の峠
石部宿の騒動と女の刺客
草津宿を発った愁二郎と双葉は、石部宿で殺人事件の騒ぎに遭遇した。被害者は四十前後の武士風の男で、廃刀令違反の刀を帯びていた。犯人は二十歳前後の女で、風呂敷に偽装した小脇差で斬りかかったという。金銭ではなく木札を狙ったと見られ、戦い慣れした手口であった。
土山宿での稽古と双葉の実力
道中、愁二郎は双葉に剣術を試させた。父・栄太郎から護身の手ほどきを受けていたため基礎は出来ていたが、十二歳の娘では修羅場を生き延びるのは困難であった。双葉は家出同然で「こどく」に参加しており、その無謀さを愁二郎は痛感した。
鈴鹿峠での伏兵と武曲の発動
鈴鹿峠に差しかかると豪雨の中、矢の襲撃を受けた。さらに七人組の刺客が現れるが、愁二郎は武曲の足技を駆使して斬り伏せ、木札を奪った。仲間割れを誘うため一部を敢えて残し、混乱の隙に双葉と峠を突破した。
彩八との再会と継承の真実
峠で待ち受けていたのは義妹の彩八であり、京八流の奥義「文曲」を操っていた。愁二郎も「武曲」と一貫から託された「北辰」を用い応戦する。彩八は兄弟たちの現存を告げ、四蔵の他に三助・甚六も参加していることを明かした。継承戦から逃げた愁二郎への憎しみを吐露し、二人は斬り結ぶが、双葉が割って入り事態は一時停戦となった。
新たな追手と修羅の坂道
直後に弓を持った四人の刺客が現れ、彩八は森へと姿を消した。愁二郎と双葉は坂下宿を目指して逃走するが、背後から迫る追撃者により道は修羅場と化した。双葉を守るため、愁二郎は坂道を地獄の路のように感じながら走り続けた。残る参加者は百一名となった。
肆ノ章 北の狩人
アイヌの現状とカムイコチャの苦悩
北海道の雪深い大地で、若き村長カムイコチャは狩りに出ていた。彼は幼少より弓矢に秀で、六歳で鹿を射抜いた逸話を持つ「神の子」と呼ばれる存在であった。明治新政府の成立後、アイヌは土地を奪われ、風習や狩猟を禁じられていた。友であった隣村の長ウタリアンは抗い、村は壊滅した。戦わずに従ったカムイコチャは生き延びたが、選択の是非に悩み続けていた。和人の大尽に村を含む二十カ村を売られ、三万四千三百円で買い戻せと言われたが到底不可能な額であった。カムイコチャは希望を失いかけていたが、新聞の懸賞記事に十万円の記述を知り、参加を決意した。
弓の達人としての矜持
彼にとって狩猟は神への儀式であり、禁じられてもなお弓矢を手放さなかった。遠方からも彼の弓技を一目見ようと人が訪れるほど、その技は神業と称された。和人社会に生きる同胞シバウから天龍寺の知らせを聞いたカムイコチャは、村人の理解を得て雪原を後にした。
鈴鹿峠での邂逅
愁二郎と双葉が鈴鹿峠を越える途中、矢の襲撃を受ける。前方に現れたのはアイヌ装束の男カムイコチャであった。彼は追手の参加者を狙い撃ち、全て命中させて倒した。愁二郎は一時敵と誤解したが、彼は「子を守る者とは戦わぬ」と語り、木札を回収して去った。
神の子の名と余韻
名を問われた彼は「カムイコチャ」と名乗り、それが「神の子」を意味すると告げた。愁二郎はその矢技を神業と評し、これまでに出会った響陣、天龍寺の老人、彩八、化野四蔵に続く五人目の達人として彼を認識した。さらに彩八の言葉を思い出し、まだ他の義弟たちともいずれ相まみえることを予感しつつ、自らの選択と覚悟を問い直しながら歩みを進めた。
鈴鹿峠から関宿へ
愁二郎と双葉は鈴鹿峠を越え、坂下宿に到着した。峠でカムイコチャの襲撃を警戒したが姿は見えず、彼は既に十分な点数を得て先を急いでいると推測された。二人は関宿へ向かい、宿場町の混雑に警戒しながら進んだ。
木札の確認と交換
関宿で天龍寺の男と再会し、木札の確認を受けた。双葉の木札は朱印付きの木札と交換され、点数の管理方法が明らかとなった。さらに「蠱毒」とは大陸の呪術であり、参加者同士を競わせる仕組みだと説明された。東海道全体が蠱毒の壷に例えられ、参加者は蟲に相当することを理解した。
蠱毒の正体と目的
愁二郎は、この仕組みが単なる武芸者の殺し合いではなく、優れた武人を選び抜き、何らかの目的で利用する企図があると推測した。組織の正体や目的は依然不明だが、背後には巨大な権力が存在することは確実であった。二人は東京までの生存を最優先に進む決意を固めた。
秘密の会合と仕掛け
場面は変わり、政財界の有力者らが薄暗い洋室に集い、蠱毒の真意が語られた。彼らの目的は反乱の芽を摘むこと以上に、暗殺を行える武人を排除することにあった。政府に怨恨を抱く実力者を互いに殺し合わせることで、将来の脅威を根絶する狙いである。
仕掛けの追加と黒札
第三関門以降、最後に通過した者には全ての点を与えるという仕掛けが追加された。だが、その者は黒札を持たされ、全員に標的として伝えられる。これにより生存競争が一層激化するよう計画されていた。
貫地谷無骨の存在
平岸が報告した特筆すべき参加者は「貫地谷無骨」であった。彼は戊辰戦争や西南戦争に関わり、常軌を逸した斬殺者として恐れられた浪人である。銃を嫌い、白兵戦のみを好んで戦場に現れ、仲間すら斬った異常な人物であった。その無骨が蠱毒に参加しており、必ず争乱の中心になると見られていた。
結末
会合の首謀者は、無骨を含む旧時代の亡霊たちが互いに殺し合うことを望んでいた。残り参加者は九十一名となり、蠱毒はさらなる激化に向かって進んでいた。
伍ノ章 同盟
山宿からの出立と襲撃者
愁二郎と双葉は関宿を越え、一里半先の山宿で休息した。翌朝、庄野宿を過ぎる途中で股旅姿の刺客に襲われる。驚異的な脚力と武曲に似た戦法を操る遣い手だったが、愁二郎が斬り伏せた。だが木札は僅か二点しか持たず、さらに上位の怪物的な参加者が存在することを示唆していた。
菊臣右京との邂逅
合流した双葉は襲撃を受けており、美貌の剣士・菊臣右京に救われていた。右京は大太刀を自在に操り、正々堂々を信条とする異質の参加者であった。彼は双葉を助け、二人に「弱者を守れ」と忠告して立ち去った。愁二郎は彼を強者と認めつつ警戒心を残した。
死体の処理と主催者の影
直後、警官に扮した「処理部隊」が現れ、死体を袋に詰めて運び去るのを目撃する。主催者が大規模な人員を動員し、東海道全域を監視・処理している実態を悟り、その組織の強大さに戦慄した。
四日市宿での再会
夕刻、四日市宿の「鳥頭屋」で響陣と再会。彼は女に変装して潜伏していたことを明かし、愁二郎らと同盟を結ぶ交渉を始める。条件として響陣は「助けたい女がいる」と語り、愁二郎はその真剣さを認めて同盟を承諾した。
双葉の願いと浜松の策
双葉は「殺さずに東京へ行けないか」と願い出る。愁二郎と響陣は理想論としながらも、浜松までなら可能性があると計算した。浜松(十点)までに三十点を揃えれば、一人を東京へ進ませ、残る二人が脱落して無事かどうか確かめる策を練った。
情報交換と五人の強者
響陣は目撃した五人の強者を挙げた。
- 老剣士 ― 仕込み杖を操り、一瞬で二人を斬る達人。
- カムイコチャ ― 神業の弓術を誇るアイヌの戦士。
- 貫地谷無骨 ― 幕末に名を馳せた「乱斬り無骨」、狂気の剣客。
- 謎の剣士 ― 三人の刀を次々と折る異能の使い手。愁二郎の義弟・化野四蔵と判明。
- 愁二郎自身 ― 響陣が京で目撃した「刻舟」としての過去。
愁二郎は義弟との因縁を打ち明け、また自らの武が衰えていることを認めつつも、戦う覚悟を固めた。
愁二郎の語る強者たち
愁二郎は、響陣に問われて自らが知る強者たちを挙げた。
一人目は彩八で、女ながら京八流を継ぐ実力者であり、文曲を操る義妹であった。彼女は「刻舟」を継がず逃げた愁二郎を恨んでいた。
二人目は甚六で、元来は腕力に優れた義弟であったが、愁二郎はまだ姿を見ていない。
三人目は三助で、寡黙で冷徹な義弟。彼が参加しているなら必ず強敵となると愁二郎は推測した。
愁二郎の自己認識
愁二郎は、自分は既に衰えた浪人であり、彼らに比べれば過去の存在に過ぎないと述懐した。しかし双葉や妻子を救うため、再び「刻舟」として剣を執る覚悟を抱いていた。響陣はその言葉を受け、愁二郎を真の強者として認めた。
同盟の成立と行程の確認
三人は改めて同盟を結び、次の目標を浜松宿に定めた。愁二郎と双葉は三十点を揃えるため動き、響陣は情報収集と隠密行動を担当することで合意した。浜松で再び落ち合うことを約し、鳥頭屋を後にした。
双葉の決意
宿を出た後、双葉は愁二郎に「自分も斬る覚悟を持つ」と告げた。彼女は父の無念と母の病を背負い、無力な子供であることを拒絶した。愁二郎はその強さを認めつつも、彼女を守る決意を固めた。
参加者数の減少
この時点で残る参加者は八十三名となり、蠱毒はさらに苛烈さを増していた。愁二郎と双葉は同盟者を得ながらも、宿場ごとに襲い来る試練を予感し、東海道を進み続けた。
陸ノ章 京八流
京八流の概要と継承戦の仕組み
愁二郎は響陣と双葉に京八流について語った。源平の頃に鬼一法眼と関わる者が編んだとされる最古の剣術であり、必ず八人の継承者候補を用意して同じ修練を積ませる。ただし最後に一つだけ異なる奥義が与えられる。奥義は口伝で瞬時に伝授され、模倣は不可能である。継承戦は殺し合いであり、死ぬ直前に口伝される仕組みのため、実際に命を落とす事例も多かった。このため現継承者が健在のうちに次の継承戦が実施されてきた。
京八流と権力者との関係
京八流は七百年にわたり施政者に庇護されてきた。権力者に対しては一度だけ敵を討つと持ち掛け、拒めば自らがその命を奪うと脅してきたため、多くの施政者は受け入れた。鎌倉幕府から徳川幕府に至るまで庇護を受け、幕府から多額の扶持も得ていた。例外として足利義輝のみが排除を試みたが、結局京八流の継承者によって斬られたとされる。幕末には徳川家茂が薩長ら反幕府勢力の討伐を依頼したが、師は病で果たせず、継承戦によって新たな継承者に託すこととなった。
鞍馬山での継承戦前夜
愁二郎は十三年前、鞍馬山で兄弟姉妹と共に継承戦を告げられた。兄弟八人は動揺し、涙や怒りを見せた。特に四蔵は強く反発したが、師は掟として受け入れを迫った。兄弟たちはそれぞれの思いを抱え山を離れたが、幻刀斎という存在が逃亡者を狩る役割を担っていることも知らされ、逃げ場はないと悟らされた。四蔵は実際に幻刀斎と遭遇した経験を語り、その力を前に抗う術はないと断言した。最終的に兄弟たちは殺し合いを受け入れる決意をした。
愁二郎の逃亡とその後
愁二郎は第三の道として自ら一人逃亡することを選んだ。継承戦が中断されることで他の兄弟が生き延びられると考えたためである。継承戦開始の直前、山を降りて二度と戻らなかった。下界に出た愁二郎は江戸を目指したが、人々の気配の違いに圧倒され、やがて京へと身を寄せた。そこでは血生臭い者たちの中に紛れることで、幻刀斎の目を逃れることを試みた。
蠱毒の場と無骨の出現
一方、蠱毒の場には三百人近い者が集まり、説明役の槐が開始を告げた。参加者は互いに殺し合い、木札を奪い合う状況となった。貫地谷無骨はその場で冷静に周囲を観察し、強者を見抜いた。やがて隣にいた男の誘いを拒絶し、開始と同時に斬殺して木札を奪った。さらに二人の戦いに割って入り、瞬時に両者を斬り伏せて札を手に入れた。無骨は札集めを二の次とし、戦いそのものを楽しむように雑魚を次々と斬り捨て、強者との命のやり取りを求めて動き出した。
漆ノ章水陣
桑名宿への道と七里の渡し
愁二郎、響陣、双葉は四日市宿を出立し、桑名宿へ向かった。桑名は東海道屈指の宿場であり、次の宮宿へは「七里の渡し」と呼ばれる船で渡る必要があった。愁二郎は船旅の危険を避けて陸路を選ぼうとしたが、響陣は迅速に池鯉まで進むため海路を主張した。三人は協議の末、船を選んだ。桑名宿の賑わいに双葉は目を奪われ、愁二郎は幕末に斬った桑名藩士の記憶を思い出し、己の過去と家族への思いに沈んだ。
船旅と志乃の回想
船上で双葉は初めての船に酔い苦しんだ。愁二郎は妻・志乃の言葉を思い出しながら介抱し、彼女の医術への情熱や適塾での学びを語った。志乃は幼少から医術を志し、緒方洪庵の門下で学んだ経歴を持つ。その姿に双葉は感嘆し、いつか会いたいと願った。愁二郎は家族を救うため剣を再び取る覚悟を新たにした。
船上での襲撃
船には怪しい洋装の医者と従者が同乗していた。やがて近くの船が襲撃を仕掛け、三人の武装した男が迫った。愁二郎と響陣は迎撃し、一人は響陣の暗器により海へ落ち、もう一人は愁二郎に制圧された。首領格の色黒の男は強敵であり、響陣と水中で激闘となった。愁二郎は同時に医者と従者の攻撃を退け、従者を制圧し医者を捕縛した。
戦いの決着と番場の死
水中での戦いの末、響陣は首領格を討ち取って浮上した。首領は番場と名乗り、配下を従わせ札を集めていたことが従者の口から語られた。番場は海に沈み、従者の進次郎は捕縛された。医者の所持品から札が見つかり、番場の遺した札も合わせて十一点を獲得したことで、三人は合計二十五点を手に入れた。池鯉を突破する条件は満たしたが、浜松に必要な十点には未だ足りなかった。
戦いの余韻と時代の影
船頭や乗客は愁二郎らに感謝を述べ、侍の勇敢さを称えた。しかし愁二郎は、武士の時代はすでに終わったと考え、蠱毒に集う者たちの多くはその時代に取り残された者であると感じた。海に沈んだ番場にさえ憐憫を覚え、愁二郎は波間に残る航跡を見つめ続けた。
捌ノ章 雑踏
宮宿への到着と捕縛者の尋問
愁二郎らは宮宿に到着し、捕らえた赤山末酒、加本寛松、狭山進次郎を伴って旅籠に入った。響陣は静岡県庁の役人を装い、三人を尋問した。赤山は今治出身の医者で博打による借金を抱え、豊国新聞を見て参加したと語った。寛松は金貸しの一味で赤山の監視役であり、薬を利用して参加者を毒殺して札を奪っていた。進次郎は御家人の子で、父の居酒屋が虎狼痢の流行で立ち行かなくなり、借金返済のために参加したと明かした。番場は熊野出身の漁師で裏では強盗も働いていたと証言された。
三人を用いた検証の決定
双葉の提案を受け、愁二郎と響陣は蠱毒の「失格」とその処遇を確かめるため三人を利用することを決めた。赤山は札を奪って警察に突き出し、掟破りが国家の庇護で通用するかを検証する。寛松は札を持たせたまま警察に引き渡し、蠱毒主催者が失格と判断するかを確かめる。進次郎は札を一枚しか持たず池鯉宿を通過できない状況で響陣と共に進ませ、どの時点で失格とされるかを検証することになった。籤引きで役割が決まり、赤山が一人目、寛松が二人目、進次郎が三人目に定められた。
響陣の残留と別行動
響陣は捕らえた二人を警察に引き渡し、進次郎を連れて池鯉宿を目指すことを引き受けた。愁二郎と双葉は先に進み、池鯉宿で合流する段取りとなった。響陣は変装や声色を使い分ける技能から残留に適任とされた。愁二郎と双葉は宮宿を抜け、次の宿場を目指すこととなった。
人混みの中での再会と誘拐
宮宿は東海道最大の宿場であり、凄まじい人混みで賑わっていた。その中で愁二郎はかつて見た蠱毒の参加者を次々に認め、さらには長州藩の人斬り・貫地谷無骨の姿も発見した。愁二郎が警戒する中、双葉は突如として人混みで姿を消した。袖を切り取られていたことから、意図的に連れ去られたことが判明する。双葉を担ぐ男は三助であり、京八流の義弟で耳の奥義「緑存」を持つ者であった。
無骨の襲撃と右京の登場
双葉を追おうとする愁二郎の前に、無骨が立ち塞がった。無骨は人混みの中で無差別に人を斬り殺し、愁二郎を足止めしようとした。愁二郎は必死にかわしつつ追跡を試みたが、無骨の狂気は周囲の人々を犠牲にして迫った。その最中、無骨の前に菊臣右京が現れ、野太刀で斬撃を受け止めた。右京は愁二郎に双葉の追跡を託し、自ら無骨と対峙した。愁二郎は右京に感謝を告げ、三助を追って駆け出した。
玖ノ章 古の太刀
菊臣右京の素顔と評判
徳川の世、公家は困窮し、花山院家も七百石余りの禄しか持たなかった。家僕である菊臣右京は、細身で美貌と温厚な性格から人望を集めたが、武勇に乏しいと見られていた。新選組に絡まれた下女を助けた際も懇願で事を収め、優しさは評価されつつも頼りなさが指摘されていた。
姉小路襲撃事件と秘められた太刀
右京は主の命で姉小路公知の護衛に向かったが間に合わず、凶賊の襲撃に遭遇した。姉小路は重傷を負い、やがて絶命したが、右京は凶賊二人を討ち、田中新兵衛に傷を負わせて退けた。この戦いで右京の真の力が明らかとなった。花山院家には筆の秘伝と並び、秘された「太刀四十二カ条」が伝わっており、菊臣家が代々指南役を務めていた。右京は十一歳で全てを習得し、外では軟弱を装いながら、勤王のために太刀を振るっていた。
花山院隊と佐田秀の志
動乱の中、花山院家は倒幕への足場を求め、豊前宇佐で挙兵を準備していた佐田秀に接近した。佐田は純粋な勤王の志を抱き、右京もその真摯な姿に心を動かされた。二人は共に花山院隊を率い、挙兵後は証山に立て籠もった。だが、花山院家は長州藩の圧力を受け、裏で佐田らを切り捨てていた。
裏切りと惨劇
長州藩士との会談で、花山院隊は即刻解散を迫られた。反発する佐田らに襲撃が仕掛けられ、佐田は討たれた。右京は仲間を守ろうと太刀を抜き、多くを斬り伏せたが、結局花山院隊は壊滅した。花山院家は右京を見捨て、追放した。右京は佐田の志を裏切られた怒りと絶望を抱え、名誉回復を誓って京を離れた。
蠱毒への参加と決意
明治に入っても右京は汚名を雪ぐ道を探したが叶わず、豊国新聞に記された蠱毒の存在を知り、参加を決意した。悪意に満ちた場に吐き気を覚えながらも、己の正義を貫こうと誓ったのである。
貫地谷無骨との激突と最期
宮宿外で無骨と対峙した右京は、太刀四十二カ条の奥義「菊帝」を放ち、一撃で悪を討とうとした。だが戦いの末、無骨の手により斬り伏せられ、首を刎ねられた。無骨はその首を弄び、田に投げ捨てて立ち去った。かくして志を貫いた右京は果て、蠱毒の参加者は残り八十四人となった。
同シリーズ



その他フィクション

Share this content:
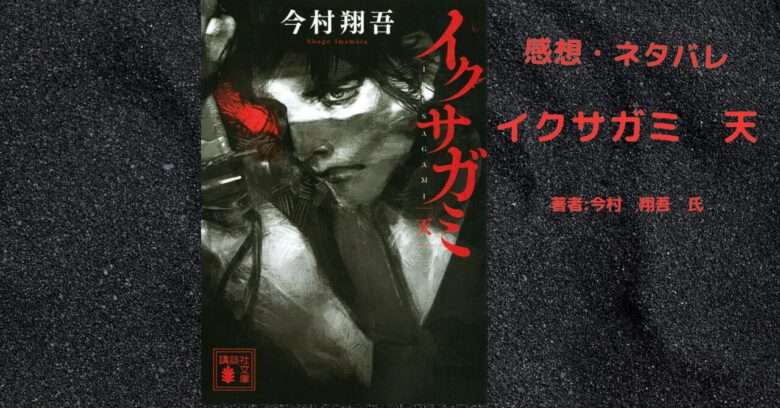

コメントを残す