物語の概要
本作は、仏ょも(ほとけょも)氏によるライトノベルシリーズ「極東救世主伝説」の第3巻である。ジャンルはSFアクションで、異形の機体を操る少年兵たちの戦いを描く。
物語は、魔物の襲撃を受けた都市を救い、極東ロシアの英雄となった少年・川上啓太が帰国するところから始まる。彼を待ち受けていたのは、壊滅的な被害を受けた国防軍と、軍学校での学園祭であった。学園祭ではAクラス全員による魔装機体での模擬戦が行われるが、啓太が搭乗するのは自身の愛機ではなく量産型の御影であった。さらに、ある任務が彼に与えられる。クラスメイトたちが刃を交える中、ついに英雄は人類の宿敵と対峙することになる 。
主要キャラクター
- 川上啓太:本作の主人公。前巻で極東ロシアの英雄となった少年兵。帰国後、軍学校での学園祭に参加し、量産型の機体「御影」に搭乗する。
- Aクラスのクラスメイトたち:啓太と共に学園祭の模擬戦に参加する。各自が魔装機体を操り、模擬戦を繰り広げる。
物語の特徴
- 学園祭と模擬戦:軍学校での学園祭を舞台に、Aクラス全員による魔装機体での模擬戦が描かれる。啓太は自身の愛機ではなく、量産型の御影に搭乗する。
- 新たな任務:啓太には新たな任務が与えられ、物語はさらに緊迫した展開を見せる。
- 人類の宿敵との対峙:クラスメイトたちが刃を交える中、啓太はついに人類の宿敵と対峙することになる
書籍情報
極東救世主伝説 3 少年、世界の敵と相対す。 ―軍学校襲撃編―
著者:仏ょも 氏
イラスト:黒銀 氏
出版社:KADOKAWA(カドカワBOOKS)
発売日:2025年5月10日
ISBN:9784040759203
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
あらすじ・内容
少年が自らの価値を証明するとき――人類の『敵』が現れる。
魔物の襲撃を受けた都市を救い、極東ロシアの英雄となった川上啓太。帰国した彼を待っていたのは、壊滅的な被害を受けた国防軍と、軍学校での学園祭だった。
学園祭ではAクラス全員による魔装機体での模擬戦が行われることになるものの、啓太が搭乗するのは自身の愛機ではなく量産型の御影に。さらにある任務が与えられて――?
クラスメイトたちが刃を交える中、ついに英雄は人類の宿敵と対峙する――!
感想
本作は、極東ロシアで英雄視された少年・川上啓太が、帰国後の軍学校で直面する理不尽と対峙する物語であった。
戦場という極限環境で鍛え上げられた彼が、平和ボケした組織内での決定に翻弄されながらも、己の矜持と戦術眼で人類の脅威に立ち向かう姿が描かれている。
矛盾だらけの軍内部と啓太の冷静な観察
本作でまず強く印象に残るのは、軍の上層部が見せる非現実的な対応である。
魔族が直接姿を現し、あからさまに新型機を要求してきたにもかかわらず、上層部は外交的な体裁を優先し、啓太に対して「武士道精神に則った一騎討ち」を命じるという暴挙に出た。
通常であれば敵の要求に応じることなく迅速に排除するべき事案であるにもかかわらず、その判断が下されなかった点は、現場視点では到底納得できるものではない。
読者としても思わず「うっかり流れ弾を司令室を撃ちたくなる」感情に共感させられる場面であった。
啓太の超然とした立場と、滑稽な学園内の対比
ロシアから「HENTAIする英雄」として称賛(ある意味で風評被害)を受けて帰国した啓太が、軍学校で文化祭の模擬戦からハブられ、乱入して来た魔族との一騎打ちに巻き込まれていく展開は、戦場と日常が強烈な対比を見せていた。
模擬戦では、明らかに啓太に実力で劣る同級生たちがプライドだけで突っかかってくる様子が滑稽であり、また、啓太が量産型機体という不利な条件で一騎打ちに挑まされる構図にも、彼が突出した存在であるがゆえの孤独が滲んでいた。
情報戦と戦術の冴え渡り――真価を発揮する狩人
最大の見どころは、魔族・アルバとの一騎討ちにおける啓太の戦術であった。
劣勢に見えた序盤戦は、すべて敵の挙動を観察・分析するための布石であった。
敵の防御特性や回避癖、魔力消費パターンまでを見抜いた上で、焼夷榴弾や機関砲を連動させた一撃で無力化する様は、もはや“狩り”であった。
戦いをゲームではなく現実として捉える啓太の冷徹さは、戦術家というより戦場の狩人であり、無駄なく確実に仕留める姿勢はベテランなゲーマーだな。
無能な組織への痛烈な批判と、読者のカタルシス
終盤で描かれる天皇による第一師団上層部への叱責は、溜飲を下げる展開であった。
啓太の命を軽視し、結果として学園祭を大混乱に導いた無責任な上層部に対して、「戦地へ行け」と勅命が下る場面は痛快であり、物語内における唯一の組織的な清算であった。
現場を知らぬ者の判断が現場を崩壊させる構図は、現実世界にも通じるものがあり、物語の奥行きを深めていた。
総評:英雄が問う「常識」の正体
本作は、主人公の英雄的活躍を描くだけでなく、彼が属する組織、社会、人間関係の矛盾をも鮮やかに描き出している。
戦術・技術・精神性のいずれにおいても規格外である啓太の姿を通じて、「英雄とは何か」「組織とは何か」を問い直す構造があり、単なる異能バトルにとどまらない深みがある。読後には、スカッとする爽快感と共に、痛烈な風刺がじわりと効いてくる読書体験が得られた。
最後までお読み頂きありがとうございます。
(PR)よろしければ上のサイトから購入して頂けると幸いです。
登場キャラクター
人族
日本皇国
第一師団
川上啓太
冷静沈着で状況判断に優れた少年兵である。第一師団所属の中尉でありながら、軍学校にも籍を置くという異例の立場にある。極東ロシア救出作戦における実績と、魔族討伐において新型機を駆って成果を上げたことから、軍上層部および皇族に重用されている。本人の意志とは無関係に象徴的存在として期待され、各勢力の政治的駆け引きにも巻き込まれている。
・所属:第一師団中尉、軍学校在籍〈兼任〉
・魔族アルバとの一騎討ちで勝利し、その力を上層部・魔族双方に認識された。
・魔族襲撃事件後、「教導大隊長」の地位を与えられ、軍の象徴として担ぎ上げられた。
久我静香
第一師団所属の教官であり、軍学校においては生徒たちの指導にあたる実務責任者である。実力主義と現場重視の姿勢を持ち、形式や階級よりも実務と信頼を優先する人物である。川上啓太の直属上官として行動を監視・補佐しつつ、軍内政治から彼を守る立場を担っている。啓太の能力と冷静さを高く評価し、実戦における判断力にも信頼を置いている。
・所属:第一師団軍学校教官〈兼任〉
・啓太の出撃を現場で調整・指揮し、護衛と統制の役割を担った。
・軍の無責任な上層部に対し不満を抱きつつ、現場重視の立場を堅持している。
第二師団
緒方勝利
第二師団の師団長を務める軍上層部の幹部である。冷静かつ現実主義的な判断を下す人物であり、形式よりも結果と実務を重視する姿勢を持つ。啓太の処遇や第一師団の無責任な命令体制に対し、明確な疑念と批判を示した。魔族との戦いを経て軍の再編が進む中、第一師団上層部の実戦投入や再教育を主導する提案を行い、戦場経験の欠如した上層部に現場の厳しさを自覚させる道筋を作った。
・所属:第二師団師団長
・魔族襲撃後の軍上層部の査問において第一師団への実戦派遣を提案した。
・軍の論理や建前を排し、現場の安全と実効性を重視する立場を貫いた。
第三師団
武藤沙織
第三師団に所属する軍学校の生徒である。模擬戦では首席の座にあり、戦術と実力の両面で他の生徒を圧倒していた。魔族との戦いに備えた警戒心も高く、実戦での適応力にも優れる。政治的な空気を敏感に読み取りつつ、自己を過信せず冷静に動くことができるタイプである。草薙型の個人戦では技量を発揮し、観衆と上層部双方から注目を集めた。
・所属:第三師団(軍学校所属)
・模擬戦での成績は常に上位で、戦術・実戦両面で高評価を得た。
・啓太の戦いに関する観察力も鋭く、周囲の状況把握に長けている。
小畑健次郎
第三師団に所属する軍学校生徒であり、模擬戦第一試合に出場した。笠原辰巳とともに茶番的な戦闘を演じ、観客受けは良かったものの、軍関係者からの評価は低かった。自己顕示欲が強く、試合の内容よりも自身の印象操作を優先する傾向が見られる。軍の模擬戦を娯楽として捉える姿勢が問題視された。
・所属:第三師団(軍学校所属)
・個人戦にて演出に偏った戦い方を見せ、評価を落とした。
・真面目に戦う生徒や上層部からの信頼は低いままである。
笠原辰巳
第三師団所属の軍学校生徒であり、小畑健次郎とペアを組んで試合に臨んだ。自らの実力を見せるよりも、観衆向けの演出を優先する方針に従った。小畑同様、模擬戦を自己表現の場と見なしていた節があり、軍人としての自覚には欠ける様子がうかがえる。
・所属:第三師団(軍学校所属)
・模擬戦第一試合で小畑に勝利を譲る演出を行った。
・上層部の評価を意識せず、軽薄な態度を取る場面が多い。
第五師団
橋本夏希
第五師団に所属する軍学校の生徒である。常に冷静な判断を心がけ、他者との衝突を避けながらも、自分の信じることには強い意志を持って行動する。綾瀬茉莉と行動を共にする場面が多く、互いに信頼関係を築いている。模擬戦では田口那奈と対戦し、実力差を認識しつつも真っ向から戦った。啓太の戦闘も冷静に観察し、正確な理解を示していた。
・所属:第五師団(軍学校所属)
・模擬戦では田口那奈と対戦し、敗北するも誠実な戦いぶりを見せた。
・啓太の戦術眼と力量にいち早く気づき、敬意を払っていた。
綾瀬茉莉
第五師団所属の軍学校生徒であり、橋本夏希と並んで実力者として知られる。情熱的で負けん気が強く、模擬戦においては自らを軽んじた第三師団の生徒に強い怒りを抱いた。そのため、試合では意趣返しの意図をもって挑戦し、実力を示すことに重点を置いた。実直な気性で、戦いを通じて自己を証明しようとする姿勢が見られる。
・所属:第五師団(軍学校所属)
・模擬戦で第三師団への強い対抗心を燃やし、全力で戦いに挑んだ。
・啓太の実力を早期に理解し、夏希と共にその戦い方を注視していた。
第六師団
五十谷翔子
第六師団に所属する軍学校生徒であり、常に論理的かつ合理的な行動をとる。啓太の実力と行動の意図を正確に読み取り、彼が情報収集に徹していたことを看破した数少ない人物である。状況を俯瞰し、必要な行動を冷静に選ぶ傾向が強く、仲間からの信頼も厚い。軍内の制度や指揮系統にも批判的な目を向けており、自らの立場で何ができるかを模索している。
・所属:第六師団(軍学校所属)
・模擬戦では福原巡嗣を破るなど、的確な戦術判断を示した。
・啓太の戦術眼を高く評価し、その危機を敏感に察知していた。
坂崎恵美
第六師団所属の軍学校生徒であり、五十谷翔子の付き人を務める。翔子に対して敬意を払い、補佐役として行動を共にする場面が多い。啓太の出撃や戦術に対する翔子の見解に理解を示し、冷静に状況を見守っていた。感情に流されず、翔子の方針を支えることで、集団内の安定に寄与する人物である。
・所属:第六師団(軍学校所属)
・五十谷翔子の意図や行動を補佐する立場で終始行動していた。
・啓太の戦闘分析にも同意し、戦況に対する理解を深めていた。
第七師団
藤田一成
第七師団に所属する軍学校生徒であり、模擬戦における第二席の実力者である。近接戦闘に長け、特に草薙型における機動力と白兵戦能力において他を圧倒する。模擬戦では首席の武藤沙織と対戦し、彼女との実力差に警戒しながらも、果敢に戦った。啓太が演じた情報収集戦術の意図を後から理解し、その有効性を認識した様子が描かれている。
・所属:第七師団(軍学校所属)
・模擬戦では武藤沙織と対戦し、互角の戦いを演じた。
・啓太の行動を観察し、彼の戦術が正確なものであったと理解した。
福原巡嗣
第七師団所属の軍学校生徒であり、模擬戦において五十谷翔子と対戦した。翔子に対する過小評価が見られ、実際の戦闘では奇襲を受けて敗北した。戦闘準備や警戒心に欠ける面があり、敵の出方を読む力において劣っていた。結果的に敗北を喫したが、その態度や対応から、模擬戦を軽視していた可能性がある。
・所属:第七師団(軍学校所属)
・模擬戦にて五十谷翔子と対戦し、不意打ちを受けて敗北した。
・戦術への対応力に欠け、情報分析の甘さが露呈した。
統合本部・上層部
浅香涼子
統合本部に所属する高官であり、上層部の意思決定に関与する立場にある。現場の実情や師団間の対立を把握した上で、第一師団上層部への勅命や再教育の執行に踏み切った。緒方勝利らの提案を受け入れる柔軟性を持ち、政治的判断と現実対応の両面において機能する調整役を担っている。
・所属:統合本部本部長
・魔族襲撃事件後、第一師団上層部の実戦派遣を決定した。
・緒方勝利の建言を受け、再教育策の実施に動いた。
最上重工関係
最上隆文
最上重工業における上級技術責任者であり、研究者として軍用機の開発および運用支援を行う人物である。川上啓太の操縦データを詳細に分析し、量産型機体の成長や最適化に強い関心を寄せている。軍の上層部や企業間の政治的綱引きに慎重な姿勢を取りつつ、合理性と技術革新を優先する立場を崩していない。
・所属:最上重工業主任研究者
・啓太の量産型機運用データを解析し、技術的成果を評価した。
・機体の処遇や管理権を巡る軍との交渉にも関与した。
最上重工業
軍事機体の開発・整備を担当する大手企業である。量産型機体や新型草薙型の研究・製造を手掛け、戦術と技術の両面から軍と連携している。啓太が搭乗した機体の成長ログや戦闘データの管理を巡り、軍上層部と運用権限をめぐる議論の対象となった。
・所属:日本皇国主要軍需企業
・草薙型量産機および新型機の設計・開発を担っている。
・啓太の実戦データの取得に深く関与し、所有権を主張した。
その他日本皇国関係者
川上優菜
川上啓太の妹であり、皇族関係者と接点を持つ人物である。政治的価値や象徴性を帯びた啓太の立場に影響を及ぼす可能性があり、その存在は物語の裏面においても無視できない。直接的な戦闘や指揮には関与しないが、啓太の精神的背景を構成する重要な存在である。
・所属:民間(日本皇国)
・川上啓太の肉親として登場し、その内面にも影響を与えている。
・軍や政治関係者にとって啓太を扱う際の一因となる存在である。
極東ロシア大公国関係者
イェレナ
極東ロシア大公国の上級貴族であり、外交および軍事上の交渉に関与する立場を持つ。川上啓太に対して強い信頼と感謝の念を抱いており、その交流が国際的な信頼関係の構築に寄与している。極東ロシアと日本皇国の政治的橋渡し役としても機能する。
・所属:極東ロシア大公国貴族
・啓太の極東ロシア救出作戦に感謝し、外交関係の促進に貢献した。
・啓太との信頼関係は、両国間の交流に良好な影響を与えている。
アレクセイ
極東ロシアにおける軍関係者であり、啓太や日本皇国軍との協力関係にある。イェレナとは旧知の仲であり、戦術行動や軍事的判断において支援を行う立場を担った。啓太の実力と人間性に一定の信頼を寄せ、交流の中で日本皇国軍の在り方を理解しようとしていた。
・所属:極東ロシア大公国軍人
・極東ロシア救出作戦に協力し、啓太らと共同で行動した。
・軍事的な信頼関係の構築に貢献し、友好的な関係を保った。
魔族
ルフィナ
魔族本陣において高い地位を占める知性派の魔族であり、戦略・情報収集・分析に長けている。アルバの暴走を静観しつつ、英雄と新型機体の性能を詳細に観察した。啓太の戦術や戦闘結果を高く評価し、魔族側の今後の作戦に反映すべく、王への報告を行った。過度な感情に左右されることなく、冷徹な計算に基づいて戦局を捉える傾向が強い。
・所属:魔族本陣(上級魔族)
・アルバの戦闘を通じて啓太と新型機体の情報を収集・分析した。
・今後の戦術として、英雄の存在を前提に魔物の投入戦略を再構築する方針を提案した。
魔族の王
魔族の頂点に立つ支配者であり、闘争そのものを価値あるものとみなす思想を持つ存在である。人類との対立を単なる侵略ではなく、「進化の促進」として捉え、英雄のような存在が現れることを歓迎している。ルフィナの報告を受け、今後の戦略方針として、英雄の存在を刺激材料とした戦場形成を支持した。
・所属:魔族本陣(王)
・啓太と新型機体の存在に着目し、「闘争の質」向上を目指す方針を承認した。
・単なる勝利よりも、魔族と人類の拮抗によって生まれる緊張と成長を重視している。
アルバ
戦闘部隊に所属する鬼型魔物の操縦者であり、前線での一騎討ちを好む戦闘狂の気質を持つ。啓太と対峙した際には独断で出撃し、命令に反して戦闘を開始した。機動性と近接戦闘に優れるが、戦術的な思考に欠けており、啓太の緻密な分析と罠に翻弄された。結果として、頭部と胴体を貫かれて完全に沈黙させられた。
・所属:魔族戦闘部隊
・啓太との戦闘において、魔族側の敗北を喫した。
・無断出撃により評価を下げ、魔族本陣からも見限られる存在となった。
展開まとめ
プロローグ
悪魔との長き戦争と共生派の台頭
西暦2056年、人類は悪魔とその配下である魔族や魔物と110年以上も戦争を続けていた。当初は団結していた人類も、長期戦に疲弊し、一部には共存を模索する「共生派」が登場した。彼らは悪魔に交渉の余地があると信じ、論理的根拠を掲げて融和を主張した。しかし、実際には共生を試みた者の多くが戻らず、悪魔側にとって人類は労働力か餌でしかなかった。共生派は、魔族に情報や物資を提供する裏切者として扱われ、その努力も見返りのないまま利用されるに過ぎなかった。
ルフィナの疑念と情報空白
魔族の上位存在であるルフィナは、「HENTAIする英雄」として名が広まった存在が日本の学生であるという報告を受け、まず語感への誤解を正し安堵した。しかし、それ以上に彼女が注目したのは、英雄が千体もの魔物を強化外骨格で殲滅したという戦果であった。この兵器が存在するならば、なぜ以前の戦闘で甚大な被害が出たのかと疑念を抱いた。仮に新兵器であるなら、極東ロシアでの使用が初であっても、開発段階で情報が出回らないのは不自然であった。
情報遮断の矛盾と共生派への不信
ルフィナは、量産型という形式が存在する以上、元となる機体の情報があって然るべきと推察した。しかし、下半身が獣型という特異な構造を持つ機体についての事前情報は皆無であった。第一次防衛戦での活躍という事後報告はあったが、それ以外の記録は存在せず、これは共生派の情報統制とは相反する現象であった。なぜなら共生派は、魔族の機嫌を損ねぬよう情報を積極的に提供する性質を持ち、隠匿の動機がないはずであった。
ルフィナの行動決断と日本への派遣
共生派は日本の軍部にも存在していたが、今回の情報漏れの不自然さにルフィナは違和感を募らせた。情報が漏れなかったこと自体が異常であり、ルフィナは現地の報告者や共生派を信用できないと判断した。使える部下もおらず、結局、自身が直接現地に赴く決断を下した。敵地に無策で向かうつもりはなく、日本側が情報を開示すると聞いた以上、訪問は無駄にはならないと見込んだ。視線の先には「学園祭のお知らせ」と書かれた紙があった。
一章 学園祭での任務
軍学校における学園祭の意義
啓太が所属する軍学校では、民間校とは異なり部活動や娯楽は存在せず、生存率向上を最優先とした厳格な教育が施されていた。その中で、数少ない例外的行事として学園祭が実施される理由は、軍が民間の理解と協力を必要としているからである。学園祭は広報活動としての意味を持ち、生徒にとっては正規の任務として認識されていた。そのため、訓練内容も演舞風に調整され、行事への情熱は本物であった。
啓太の不参加命令とその理由
啓太は学園祭に参加しないよう命じられた。彼はその理由を疑問視したが、担任と五十谷の説明により、啓太の立場が一般生徒とは大きく異なることが明かされた。彼は第一師団所属の中尉であり、同盟国からの叙勲も受けた存在であるため、他の生徒が彼に嫌がらせをする余地は皆無であった。また、啓太が保有する軍事機密や新兵器関連の情報の重要性から、彼を敵対勢力に晒すわけにはいかず、学園祭では目立たない任務に就くこととなった。
九州戦線の被害と啓太の戦力的価値
啓太が任務から外された背景には、九州戦線の壊滅的損害があった。第二師団が壊滅し、第六・第八師団も被害を受けた現在、啓太が操縦できる試作機の稼働が唯一の即応戦力である以上、彼をいつでも動かせるよう待機させることが軍の最優先事項となった。量産型の機士がまだ戦力として不十分であることもあり、啓太の存在は不可欠であった。
広報的価値と安全保障の狭間
啓太は軍における貴重な広告塔でもあったが、過剰な注目を浴びることで敵対勢力から狙われる危険性も高まっていた。そのため、広報活動の前線に立たせることは避けられ、演舞用シミュレーターの操縦など間接的な任務に限定された。この配慮は、啓太が軍にとって極めて重要な資源であることの証左であった。
お目付け役としての五十谷の立場
啓太は自らがなぜ五十谷から説明を受けたのかを疑問に思ったが、担任と五十谷の言によって、彼女が啓太の「お目付け役」として任命されていたことが明かされた。この任命は軍としての判断であり、啓太が拒否する余地は存在しなかった。彼は心中で抗議の念を抱きつつも、それが軍の決定である以上、受け入れざるを得なかった。
二章 待機中の訓練も立派な仕事
訓練内容の変化と草薙型の適性評価
啓太は学園祭に向けた準備から外され、シミュレーターによる訓練を日々行っていた。五十谷翔子との模擬戦においては、草薙型を使用し、初期データかつ魔晶の魔力が使用できない条件下での戦闘に臨んだ。しかし、彼は五戦全敗と実力差を明確に突きつけられた。魔力依存の戦闘スタイルに慣れていた彼にとって、魔力の使えない状況は大きな制約であり、全ての動作に遅延が生じていた。
草薙型と強化外骨格の相性の違い
啓太は草薙型を身体の延長として扱うことが難しく、動きと思考にズレが生じるという認識に至った。一方で、強化外骨格においては思考と動作が直結し、操作に違和感がなかった。そのため、五十谷との戦闘でも強化外骨格を使用した際は勝利することができた。五十谷はこの点を認め、以後の訓練では強化外骨格の使用を提案した。
上層部の判断と啓太の立場
最上と担任教官も、啓太が草薙型より強化外骨格に適していると判断し、その変更を許可した。軍としても、啓太の持つ混合型試作一号機や強化外骨格に関するデータを取得する必要があり、運用と戦力の両面からも有益であった。啓太自身も、自身の戦力評価や得られる成果からその提案を受け入れた。
啓太の戦果と英雄視の矛盾
啓太は極東ロシアで一〇〇〇体以上の魔物を相手に強化外骨格で突撃し、要人救助と民間人の救出を成し遂げていた。しかしその戦果にもかかわらず「HENTAIする英雄」と揶揄される扱いに不満を抱いていた。啓太はそのような過剰な評価と引き留め策を避けるべく、国外への渡航を控える意向を示した。
模擬戦による評価と静香の観察
啓太と五十谷の訓練は、久我静香の目に留まり、両者の能力が高く評価された。特に啓太は草薙型と混合型の両方を短期間で操作できる適応力と、過酷な状況下でも任務を遂行できる精神性を兼ね備えており、その異常性が明確になった。静香は啓太の存在によって学徒動員が回避された現状を把握し、啓太が国家防衛の象徴として機能していることを認識した。
学徒動員の回避と啓太の代替不能性
軍は大攻勢により甚大な被害を受けたが、啓太の存在により、第二師団は学徒動員を見送った。これは啓太一人によって戦局を維持できるという判断と、学生たちが啓太の戦果を誤認し、士気の暴走を起こすことを懸念した結果であった。軍部内でも啓太への嫉妬による誤射などを懸念する声があり、慎重な対応が求められていた。
五十谷翔子の立場と価値
静香は啓太と唯一対等に会話し、訓練をこなせる五十谷の存在を高く評価していた。五十谷は啓太と模擬戦を重ねることで操縦技術を向上させており、情報収集能力や対人関係でも軍内で貴重な人材であった。特に啓太との間に信頼関係を築ける者が少ない中、五十谷の存在は啓太との連携において不可欠とされていた。
模擬戦の成果と強化外骨格への評価
啓太との模擬戦を終えた五十谷翔子は、得られた成果に満足していた。草薙型を使った戦闘での勝利、量産型と試作機の違いの把握、市街地での強化外骨格との交戦データなど、情報面でも実戦面でも収穫は大きかったと評価していた。加えて、この訓練が無料で実施されたことも、彼女の満足感を高める一因となった。
恵美の誤解と翔子の価値観
付き人である坂崎恵美は、翔子が啓太に恋愛感情を抱いているのではないかと推測していたが、翔子の目的はあくまで家と師団の利益であり、得た情報を再建に活用することであった。翔子にとっては恋愛よりも職務と家柄が優先されていた。
情報収集者・橋本夏希の訪問
翔子が帰宅しようとしたところ、第六師団のクラスメイトである橋本夏希が現れ、情報交換を持ちかけてきた。夏希の目的は、啓太に関する情報および、最上重工業製の新型強化外骨格の性能に関する情報の入手であった。特に第五師団が市街戦に適した兵器を求めていたため、その興味は強かった。
第五師団の焦りと啓太への関心
啓太が極東ロシアで得た戦果と、現地との繋がりによって評価を高めていたことは、第五師団にとって脅威と映っていた。彼らは従来の砲撃型兵器に限界を感じており、啓太が用いた強化外骨格を新たな選択肢として注目していた。夏希の情報収集はその流れの一環であった。
翔子の交渉戦術と優位性の維持
翔子は夏希の申し出を即座に受け入れず、自らの情報価値を明確に認識していた。啓太からの情報は直接では活用しにくいため、翔子のような仲介者の存在が不可欠であるという状況を理解し、それを交渉材料とした。最終的に「貸し一つ」という条件で情報提供に応じる姿勢を見せ、夏希もそれを受け入れた。
学生としての成長と恵美の内省
この一連のやり取りを見た恵美は、翔子の対応の成熟ぶりに感心していた。以前の翔子であれば取引を無自覚に壊していた可能性もあったが、現在は交渉術を用い、感情と職務を分けて行動できるようになっていた。
三章 優菜からの情報提供
優菜の警戒と転入生への思惑
九月一日、優菜は新学期の開始とともに、極東ロシアから転入してきた兄妹──イェレナとアレクセイ──に注目した。彼女は、兄啓太に接近する有象無象を防ぐ盾として、この二人を戦略的に利用しようと考えていた。第二師団の後ろ盾を失った今、優菜は外交官の娘であるイェレナたちの外的立場を活用して、啓太への干渉を制限しようとしていたのである。
転入生との交渉と失敗
優菜は転入生に対して過剰とも言える牽制を行ったが、それが彼らに強い恐怖を与えてしまった。日本特有の含みや空気を察する文化を前提とした態度が誤解を招いた結果である。付き人の亜矢の助言により、彼女たちは上層部の指示を仰いで行動する存在であり、性急な交渉は逆効果であると優菜は理解した。最終的に優菜は交渉を保留し、今後の対応を転入生たちに委ねることにした。
夕食の会話と兄妹の関係
夜、優菜は啓太と夕食を共にし、転入生の件を報告した。兄妹の会話はまるで夫婦のような和やかさを見せていた。啓太は優菜の負担を減らそうと外食を選ぶことが多くなっていたが、優菜はそれでも兄と過ごす時間や家事を喜びとして受け入れていた。二人は互いに相手を思いやり、穏やかな関係を保っていた。
転入の目的に対する啓太の分析
優菜からの報告を受けた啓太は、極東ロシアからの転入生の存在に違和感を覚えた。自身に接近するための者である可能性は高いが、それにしては日本の軍関係者が集う学校という選択は不自然であった。啓太は、これは極東ロシアの一部勢力による私的な行動か、もしくは日本との関係を悪化させるための挑発、あるいは共生派による工作の可能性を指摘した。
共生派と敵対者の可能性
啓太は、転入生が敵対勢力の尖兵である可能性も否定しなかった。特に魔族との共存を図る共生派にとって、啓太は最大の障害となる存在である。啓太は、自身ではなく妹の優菜を狙うことで接近を図っていると分析し、彼女に対する防衛意識を強めた。また、貴族であっても共生派と通じている可能性があることから、貴族という肩書きが信用に値しないことを理解していた。
妹への信頼と怒り
啓太は、優菜との関係が生活の基盤であることを改めて実感し、彼女が満ち足りた表情で日々を過ごしていることに安堵した。しかしその一方で、自身の妹に不審な意図で接近した者たちに対しては強い怒りを抱き、必ず報復すると心に誓った。
担任との情報共有と懸念の共有
啓太は前日の妹・優菜との会話内容を担任に報告し、担任も同様の懸念を抱いていたことが判明した。担任は外交絡みの問題ゆえ強硬策を避けると述べつつも、極東ロシアからの転入手続きを認可した国内関係者に疑念を抱き、協力者の摘発を進める姿勢を見せた。啓太は妹の安全確保を求め、第一師団の縄張り内での護衛配置が可能かを問うたが、それに対して担任は無料で護衛を手配する旨を約束した。
静香の戦略と護衛配置の成功
第一師団所属の久我静香は、啓太の要請により護衛を自然な形で配置する機会を得て、内心で成功を喜んでいた。啓太が警戒心の強い性格であることから、静香は恩着せがましくなく護衛を付けることを重視していたため、啓太自身からの依頼は理想的な展開であった。これにより、軍としての責務を果たすと同時に啓太の信頼を損なうことなく任務を遂行できた。
学園祭での啓太の任務と量産型の搭乗
学園祭に関して、啓太は表舞台には立たず、量産型機体を用いて模擬戦に参加することを命じられた。これは機密保持と量産型の性能信頼度向上を狙ったものであり、啓太の操縦技術を以てすれば十分な成果を期待できると判断された。静香は啓太に草薙型を使用する他のAクラス生徒との模擬戦を命じ、量産型の有用性を内外に証明させようとしていた。
機士戦の概要と軍の思惑
学園祭で行われる機士戦には個人戦と団体戦が存在するが、今年は軍の損耗と学徒動員の可能性を踏まえて団体戦が中止された。草薙型の機士による個人戦は実施されるが、啓太には特別に量産型での参加が求められた。これは観客向けというよりも軍内部の評価に関わるもので、量産型の性能が本当に実戦向きであるかを示す役割があった。
軍内部での量産型評価と過去の実戦
前回の戦闘で量産型は大型魔物への一斉砲撃命令を拒否したことで、実戦における信頼を失っていた。芝野准将は命令違反を不問としたが、技術者たちは「最適化」として評価しつつも、量産型の火力低下と機体縮小という不本意な進化を招いていた。これにより、量産型は研究対象にはなっても即戦力とは見なされず、啓太による実績の再構築が必要とされていた。
エキシビションマッチと啓太への期待
啓太は学園祭でのエキシビションマッチにおいて、量産型で草薙型に搭乗するAクラス生徒9名全員と戦い、圧倒的勝利を収めるよう命じられた。これは軍として量産型の信頼性を再構築するための試みであり、啓太の操縦技術に大きく依存する内容であった。啓太はその無茶な命令に苦笑しつつも、軍人として任務を遂行する決意を固めた。
四章 機士戦(前編)
学園祭と機士戦に集まる注目
十月中旬、軍学校では学園祭が開催され、例年通りの来客数が予想された。団体戦の中止にもかかわらず注目が集まった理由は、極東ロシアで英雄視された川上啓太の存在と、彼が操る新型機体の公開であった。さらに、啓太の出場を狙う共生派の動向に警戒し、軍は彼を囮として情報収集・摘発の機会とすべく行動を開始していた。
共生派への警戒と各師団の動き
第一師団を中心に、各師団にも協力命令が下され、武藤沙織の実家を含む一部の家系は積極的に協力を申し出ていた。だが、第三師団はかつての失態により信頼を失っており、その再建計画も凍結されていた。翔子たちは、騒動を起こす第三師団の男子生徒たちに冷笑を向けていた。
組み合わせに対する不満と第三師団の厚顔無恥
個人戦の組み合わせに不満を抱いた第三師団の生徒たちは、場違いな場所で係員に大声を上げ、周囲の失笑を買っていた。彼らは一回戦の組み合わせが第三師団同士になったことに不満を表し、それを「陰謀」とまで主張した。そもそも彼らは派閥の体面を保つため、対戦相手の変更を周囲に頼み込み、認められた立場であったにもかかわらず、後出しで更なる優遇を求めていた。
茉莉と夏希の怒りと反撃の意思
第十席の綾瀬茉莉と第七席の橋本夏希は、第三師団の身勝手さに強い憤りを抱いていた。茉莉は第一試合が啓太の不参加で不戦勝となり、第二試合で小畑健次郎と対戦することになったことから、彼を叩き潰す決意を固めた。茉莉は補欠である自分を軽視する彼らに対し、「補欠の怖さ」を思い知らせると内心で宣言していた。
第一試合の茶番と観客の困惑
個人戦第一試合は、小畑健次郎と笠原辰巳によるものであったが、内容は明らかな茶番であった。笠原がわざと苦戦を装い、小畑に勝利を譲る寸劇を演じたことにより、戦闘としての緊張感は欠如していた。観客は楽しんでいたが、関係者やクラスメイトたちは冷ややかな目でそれを見ていた。啓太もまた、自身がそのような茶番に巻き込まれずに済んだことに安堵していた。
第二試合に挑む夏希と田口の決意
第二試合では、第六席の田口那奈と第七席の橋本夏希が対決することになった。入試の席次に第三師団が介入したとされ、実力に見合わぬ評価を受けた彼女たちは、互いに本気で相手を打ち破る覚悟を固めていた。直前の茶番試合とは異なり、真剣勝負の空気がそこには漂っていた。
五章 機士戦(後編)
第二試合の勝敗と実力差
第二試合では、田口那奈が橋本夏希を下して勝利した。橋本も技量を持つ機士ではあったが、田口の得意とする近接戦闘においては一枚上であり、ナギナタによる優位性を発揮した。結果として、観戦者には技術の差が明瞭に映る内容となり、軍関係者にとっては意義深い試合であった。
五十谷翔子と福原の対戦
第三試合では五十谷翔子と福原が対戦した。五十谷は事前に福原の戦法を想定し、三二mm対物ライフルによる射撃戦術を選択した。この武器選択は、啓太の戦いから得た知見をもとに最適化されたものであり、機動力と制圧力を両立した戦法であった。福原は五十谷の奇襲に対応できず、胴体部に一撃を受けて敗北した。
五十谷の装備選択と意図
五十谷が採用した三二mmライフルは、従来の四〇mm機関砲と比較して機動性を保ちつつ射撃可能な装備であった。反動の少なさと単発性が特徴で、複数戦や不意打ちに向いていた。彼女はこれを実戦的な選択として評価し、「一体倒すなら四〇mmだが、複数相手なら三二mmが最良」と判断していた。
藤田との対戦を控える武藤の構想
第四試合では、首席の武藤沙織と次席の藤田一成が対戦した。藤田は近接戦闘に秀でていたが、武藤は射撃技能と戦術眼に優れていた。事前に五十谷の戦法を見ていた両者は、互いに手の内を読んで牽制しあい、試合序盤は一進一退の緊張状態が続いた。
戦況の読み合いと心理戦
武藤は第三師団への悪印象を払拭しつつ勝利することを狙っていた。一方の藤田は、五十谷との戦いを受けて対物ライフルの危険性を強く意識し、下手な動きをすれば敗北する可能性を自覚していた。両者は迂闊に動けない状況となり、会場には異様な緊張が広がっていた。
観客の混乱と突然の侵入者
試合が膠着する中、観客席から突如として殺気を帯びた怒声が響いた。それは明らかに闘技とは無関係の第三者の声であり、武藤と藤田の集中を削ぐに十分なものであった。直後、モニターに現れたのは草薙型にも似た巨大な鬼型の魔物であり、会場は混乱に包まれた。
六章 魔族
魔族の出現と場の混乱
学園祭中の個人戦会場に、鬼型の魔物を従えた魔族が出現した。魔族が理性ある発言を行ったことで、関係者らは魔物との違いを理解し、ただの突発事件ではないと認識した。指揮官であるボスは混乱の中で学生たちに撤退の許可を出し、魔族との直接戦闘を避ける方針を取った。
魔族の目的と啓太の推論
啓太は冷静に魔族の行動目的を考察し、観客や来賓を狙う様子がないことから、真の目的が新型機体にあると推測した。魔族が「英雄」と名指ししたことにより、狙いが自分自身、あるいは新型機体の性能評価であることが明白となった。
上層部の命令と現場の反発
静香は啓太を出撃させるよう命じられるが、上層部からの命令は「魔族に奇襲をせず、正面から堂々と一騎討ちすること」とされていた。その背景には軍上層部の政治的な思惑と、武人気質を誤解した浪漫主義的な理屈があった。現場の静香や校長の忠明らは、その非現実的な命令に失望しつつも、民間人の安全を優先するため命令に従う決断を下した。
魔族との一騎討ちと啓太の苦戦
啓太は命令を受けて出撃し、魔族「アルバ」との一騎討ちに臨んだ。新型機を駆る啓太は遠距離戦闘を得意としていたが、アリーナという狭い空間では不利を強いられた。アルバは近接戦闘に特化しており、威力と速度の双方で高い能力を持っていた。
命令への憤りと静香たちの沈黙
啓太は政治的配慮のために無理な戦いを強いられたことに怒りを覚え、軍の上層部を「政治屋」と非難した。静香や周囲の教官たちはその発言を咎めず、むしろ同意の沈黙で応じた。彼らもまた、軍上層部が啓太を無駄に危険へ晒したことに対して強い不満を抱いていた。
組織の腐敗と危機感
静香と忠明は、軍組織が第三師団と同様に現実を見失っていると感じ、深刻な危機意識を抱いた。特に、戦場を知らぬ者たちの意向で命令が下される状況に、軍の効率性と倫理観が失われつつあることを痛感していた。
啓太の劣勢と支援の決意
啓太は徹甲弾や機関砲による遠距離攻撃で魔族に応戦したが、アルバはそれらを容易に回避・防御してみせた。見た目には啓太が優勢に見えたが、実際には彼が追い詰められていた。静香はこの状況を見て救援の出撃を決意し、広幡校長もそれを了承した。
幕間 魔族の視点から 一
魔族アルバの暴走とルフィナの観察
鬼型魔物に搭乗して出現した魔族アルバは、本来なら戦闘に出る予定のなかったタイミングで一騎討ちを仕掛けた。彼の背後にいた上級魔族ルフィナは、彼を捨て駒とみなしており、命令違反で戦闘を始めたことにも特に関与しようとしなかった。一方で、新型機体と啓太の性能を間近で観察できたことには一定の成果を認めていた。
魔族側の戦術と新型機の弱点
ルフィナの視点から、新型の持つ各武装は確かに強力ではあるが、当たらなければ意味がなく、また魔力を使いこなす魔族に対しては直撃以外の効果が薄いと判断された。加えて、近接戦闘能力の低さ、狭いアリーナでの遠距離型の不利といった要素から、現時点での戦況は新型にとって著しく不利と評価された。
新型の反撃とアルバの対応
啓太は両手で異なる武器を操る技術を見せ、機関砲と榴弾を組み合わせた攻撃を仕掛けたが、アルバは冷静にそれを回避し、再び優勢を維持した。ルフィナは新型の多機能性と用心深さを評価しつつも、戦況を決定づけるには至らないと判断し、今後の情報収集と戦力配備計画へ意識を移行した。
援軍の不在と日本側の意図
ルフィナは、新型を援護する兵士が現れないことに違和感を覚え、日本側の政治的意図──あるいは英雄殺しすら視野に入れた策謀──を疑った。戦闘の趨勢は既に決しており、これ以上の戦いは啓太にとって致命的な結果を招くと予測していた。
静香の焦りと介入寸前の事態
モニター越しに戦闘を見守っていた静香と関係者は、啓太の劣勢を認識し、救援の決断を下そうとしていた。しかしそのとき、啓太の呟きがマイクを通じて全体に届き、戦況が反転する兆しを見せ始めた。
英雄の覚醒と狩りの始まり
啓太はこれまでの戦いをすべて観察と分析に費やしており、アルバの戦術、行動、反応の癖を把握し終えていた。敵の情報を収集し尽くした上で、いよいよ自らが主導する“狩り”に移行すると宣言したことで、彼の本領が明らかとなった。
七章 量産型の真価
制限された条件と啓太の戦略転換
啓太は遠距離狙撃の禁止命令を受けた時点で苦戦を覚悟していた。そもそも量産型の機体は遠距離制圧を目的に設計されており、その主戦力を封じられた状況では明らかに不利であった。火力・防御力・機動力すべてにおいて劣る量産型での戦いを前に、啓太は速攻を捨て、情報収集と持久戦に切り替えるという判断を下した。
アルバの防御と啓太の観察
戦闘の中で啓太は、アルバの攻撃パターンと防御方法に意図的に情報を収集する動きを見せていた。攻撃の隙や回避の癖、防御の傾向に加え、装甲の反応や回避時の動きなどを逐一記録し、全体像を把握していった。四〇mm機関砲を正面からの盾でしか防がないというアルバの行動から、啓太はその防御範囲の限定性を突き止めていた。
魔族装甲と弱点の分析
啓太はさらに、八八mm滑腔砲や八〇mm焼夷榴弾に対するアルバの反応から、魔族の耐性と限界を推定した。徹甲弾を回避する様子から、防げない威力であると見抜き、また焼夷榴弾に対して距離を取るという行動から、熱と爆風には魔力で完全対処できない可能性を導き出した。
覚悟を決めた啓太の反撃開始
十分な情報収集を終えた啓太は、自らの気配を変化させて反撃に転じた。それを察知したアルバは興奮しつつも、戦況が変化することを予期できなかった。啓太は焼夷榴弾による罠と機関砲の連撃を連動させ、アルバに確実なダメージを与えていった。
回復能力と戦術的効果
アルバの操る鬼体は魔力による自己修復機能を備えていたが、啓太はそれすら観察の材料とし、魔力枯渇による戦力低下を見越した戦術を構築していた。防御に魔力を回すことで回復効率が落ちること、回復速度が限定的であることを見抜いた啓太は、正面からの圧力と高速移動によって優位を確立していった。
魔族の切り札と即時無力化
追い詰められたアルバは鬼体の力を最大限に引き出す魔族の奥の手を発動した。だが、それすらも啓太の想定の範囲内であった。変身の隙を逃さず、八八mm滑腔砲による徹甲弾を頭部と胴体に正確に命中させ、アルバを一撃で無力化した。
勝利の確定と冷徹な止め
啓太はさらに追撃を加え、アルバの体を完全に破壊したうえで行動不能を確認し、冷静に「対象、沈黙しました」と報告を行った。その徹底した対応は、彼が戦術家としてだけでなく、実戦における冷徹な狩人としての資質を備えていたことを証明するものであった。
幕間 クラスメイトの視点から
控室の待機命令と生徒たちの認識
魔族乱入の最中、Aクラスの学生たちは静香から「控室で待機。ただし機体搭乗は禁止」という命令を受けていた。五十谷翔子と田口那奈は、この命令が学生の暴走や混乱を未然に防ぐ意図であることを理解しており、軍が学生を実戦に投入するほど愚かではないと冷静に判断していた。
啓太の戦いと観察者たちの疑念
啓太の戦いをモニター越しに見守る翔子と那奈は、彼の動きが意図的に抑えられていると感じていた。射撃のタイミングや機動、接近戦の回避などが不自然に見え、啓太が意図的に「手を抜いている」という結論に至った。一方で、彼が戦闘で手を抜く合理的な理由が見当たらず、彼の行動意図に対する疑問が残った。
夏希と茉莉の反論と量産型の操作性
橋本夏希と綾瀬茉莉は、量産型の操縦が難しいことを実地経験から理解しており、啓太が手を抜いているとは考えなかった。翔子は、啓太が量産型を最も使いこなせる存在であり、軍内でも比肩する者がいないと主張したが、夏希と茉莉が注目したのはその事実ではなく、「啓太が魔族に勝てるかどうか」であった。
モニター越しの観察と勝利の確信
翔子と那奈は啓太が手を抜いている根拠として、魔族にあえて防御や回避をさせたり、加減を見せたりしていたことを挙げた。そして啓太が本気になった瞬間、場の空気が一変し、全員が「彼は勝つ」と確信するに至った。その直後、啓太は魔族を瞬時に沈黙させ、勝利を収めた。
戦術の分析と巧妙な罠
啓太は魔族が接近戦に誘導されるよう誘い、焼夷榴弾や機関砲を活用して巧みに罠を仕掛けていた。魔力で熱や砲撃を防ぐには溜めが必要であり、その隙を突くことで致命打を与えていた。また、戦場を縦横無尽に動きながらワイヤーアンカーによる緩急を活用し、魔族の対応を困難にさせていた。
一騎討ちを巡る疑念と軍の判断
啓太の実力と戦術は高く評価されたが、そもそも啓太を出撃させた軍上層部の判断には多くの疑問が残った。魔族が啓太を名指しで挑発したことは理解できるが、その挑発に対して啓太を出す必要性は本来なかったはずである。量産型の性能も把握しきれていない状況で、啓太を危険な一騎討ちに投入することは、軍の行動としては不自然であった。
上層部の不可解な決定に対する困惑
軍組織として当然なすべきは、敵の狙いを隠し、戦術的に優位を取ることであった。しかし、第一師団の上層部は啓太をあえて最初から出撃させ、しかも量産型という不利な条件で戦わせた。翔子と那奈は、この行動に合理的な説明が付けられず、「上層部は何を考えていたのか」と首を捻るしかなかった。
上層部の判断への放棄と割り切り
翔子は第一師団上層部の思惑について考察を続けていたが、最終的にそれを考えること自体を放棄した。彼女は、得られるものがなく責任も取れない以上、自分たちが深入りすべき問題ではないと結論づけた。那奈もそれに同意し、自分たちは士官ではなく学生であることを確認し、必要であれば啓太から話を聞けばよいと考えを切り替えた。
学園祭の中止とその影響
魔族の襲撃という前代未聞の事態が発生したことで、学園祭の中止は既定路線となった。討伐は完了していたが、目的が啓太であるかどうかの確証が持てず、また他の魔族の存在が否定できない以上、警備体制の見直しと民間人の安全確保が優先された。第一師団の上層部では、対処を巡る会議が紛糾していることが予想された。
夏希と茉莉の再始動と翔子の計画
長らく無言だった夏希と茉莉が会話に復帰したことで、翔子は情報の共有が済んだことを内心で歓迎した。啓太の戦いを観た上で、翔子はある目的を果たすために、三人を巻き込む構想を抱いた。特に田口那奈に関しては、自身と同様の考えを持っていると判断していたが、夏希や茉莉に対しては半ば諦観を込めて起用せざるを得ないと感じていた。
翔子の決断と新たな行動の始まり
那奈からの問いかけにより、翔子はついに自身の考えを語り出す決意を固めた。学園祭の中止を前提とした新たな行動指針のもと、翔子は目の前の三人を巻き込んで動き出す覚悟を決めた。彼女はそれが情報収集や分析において必要な一歩であると認識していた。
八章 後始末
帰還報告と魔族の死体に対する関心
魔族を討伐した啓太は関係者の待つハンガーに戻り、上司と研究者である最上に報告を行った。最上は死体の有無に関心を示したが、啓太は「遺体は残っておらず、鬼体と融合した痕跡しかない」と回答した。このやり取りから最上の研究意図が明白となり、啓太は驚かずとも、自身が同類視されていることに不快感を覚えていた。
過剰攻撃の理由と政治的配慮
最上は「止めを刺すには一撃でよかったのではないか」と問い、啓太の選択に疑問を呈した。これに対し啓太は、「復活や共生派による混乱、魔族の支援行動の可能性を排除するために完全処理が必要であった」と説明した。軍のボスもその判断を支持し、「来賓や観客の命には代えられない」と反論材料を提示した。政治的配慮から啓太の戦法を非難する声があることを暗示されたが、啓太はそれに備える姿勢を見せた。
量産型の処遇を巡る議論
啓太は討伐に使用した量産型機体の扱いについて、初期化の是非を上層部に確認した。最上は「軍内で『自分に預けるか』『軍工廠で管理するか』で意見が割れている」と説明し、成長と最適化を経た機体を今後どのように運用するかが決定していないと語った。魔力と経験値が蓄積された機体の価値は高く、成長後の挙動データが必要とされていた。
問題視されたデータの異常性
最上は啓太の操縦データが他の機士の成長モデルになり得ないと指摘した。現行の訓練段階を無視するレベルの高度な操作であり、啓太の動作は他の機士には参考にならないという評価であった。それでも「目標や理想像としては意義がある」とされ、成長・最適化の前にデータ取得が必要と結論づけられた。
軍内政治と機体管理の綱引き
軍は機体の管理において、最上に預けた場合の独占リスクを懸念していた。最上自身も「自分の所有物でない機体を優先して整備する意義はない」と断言し、研究成果が他社に流れることへの抵抗感を示した。軍内では、財閥系企業に配慮すべきとの従来方針と、国防優先の新しい判断基準とが対立していた。
現状の結論と任務の優先順位
現状、啓太が搭乗した量産型は成長・最適化を保留とし、処遇は上層部の決定待ちとされた。啓太と最上は、当面は試作一号機や強化外骨格の任務を優先すべきと判断し、量産型は放置して問題ないという結論に達した。軍の方針が定まるまでは、無用な責任を避けるためにも関与しない方が賢明とされた。
九章 リザルト的なお話
学園祭の中止と上層部への非難
魔族の堂々たる襲撃により、軍学校の学園祭は即時中止となった。政府要人や多数の民間人、若き軍人候補が集う首都での事件は、世論とマスコミの目にも晒され、第一師団上層部は世間から厳しい叱責を受ける結果となった。特に杜撰で無気力な会議内容は記録として残り、査問の対象となった。
第二師団の困惑と啓太の戦闘報告
第二師団の緒方勝利らは学園祭に参加しておらず、魔族出現と啓太による討伐の報は終了後に知らされた。その短時間での事態展開に驚愕しつつ、現地からの続報を求めた結果、啓太の投入を決定した第一師団の命令系統に対し激しい疑念と怒りを抱いた。
一騎討ちへの疑問と統合本部の査問
啓太の一騎討ちという判断に対しては「最悪の状況なら啓太は死んでいた」との評価がなされ、指揮官として当然の危機管理を怠ったとする非難が高まった。久我静香が問い質した際も、第一師団の上層部は「負けたなら仕方がない」と無責任な態度を示し、緒方らの怒りを買うに至った。
皇族による叱責と第一師団への勅命
第一師団の上層部が皇族・貴族で構成されているため本来査問は困難であったが、今回は皇族上位の怒りが明確に示され、前例にない厳罰が下された。「一騎討ち」「卑怯」「子供を使う」などの判断に対する怒声が飛び、首都で恥を晒したとして責任を問われた。
第一師団上層部への懲罰と戦地派遣の決定
皇族からは「再び戦場に出て魔物と戦え」という勅命が下り、第一師団は実戦経験の欠如を解消すべく、再教育を命じられた。これに対して第一師団は反発したが、「平和ボケした者に何が護れるか」と一蹴された。
配置と受け入れを巡る交渉と対策
第二師団を始めとした現地師団は第一師団の受け入れを拒否し、緒方は「三分割し交代で海外遠征させる」案を提示した。現地の戦場では上層部の干渉が邪魔になるため、観戦武官としての個人派遣が検討され、指揮系統を崩さぬよう配慮された。
総意としての提案と浅香の受諾
浅香本部長は緒方の提案を受け、勅命実行に向けて動くことを決意した。この提案は、中央の無能な上層部に現場の厳しさを教えることを目的としており、各方面の意図と一致した。さらに、第三師団の政策課を巻き込むことで、データ取得と前線支援の両立も図られた。
川上啓太への新たな任務と称号
一連の事件を受け、啓太の能力と結果が改めて評価され、「初期状態の量産型でも運用次第で魔族を討てる」との実証がなされた。これにより、啓太は「教導大隊の発足と大隊長への就任」という新たな肩書を与えられ、十六歳にして軍の象徴たる責任を背負うこととなった。
幕間 魔族の視点から 二
ルフィナの報告と新たな戦略
アルバの暴走による混乱の中、ルフィナは大陸に帰還し、魔族の【王】に英雄と新型機体に関する調査結果と今後の戦略を報告した。英雄がいる場合といない場合の被害差異を分析し、今後は英雄の配備先を把握・誘導した上で魔物を投入する戦術を提案した。この提案は、王にとっても有効と評価された。
魔族側の情報把握と価値観
ルフィナは日本側の機密情報として「新型機をまともに扱えるのは現時点では英雄のみ」であることも掴んでいた。魔族はアルバの死に対し特段の感情を抱かず、むしろ戦闘中に隙を晒した彼に呆れ、逆に容赦なく止めを刺した英雄を高く評価していた。これは魔族全体に共通する価値観であり、情より実力を重んじる文化が背景にあった。
新型機の評価と戦場変化への期待
新型機が持つ火力と英雄の運用によって、戦場の様相が変化しつつあることをルフィナは指摘した。特に、砲撃性能が大型魔物二体分に匹敵するという点が重視され、今後は魔物の投入数もそれに応じて調整される方針となった。戦場の停滞を打破し、魔族側の創意工夫や緊張感を促す好機と捉えられていた。
闘争の価値と悪魔の意図
魔族の支配者である悪魔が求めているのは単なる侵略ではなく、人間と魔族との「闘争」であった。従来の一方的な狩りではなく、緊張感と工夫が伴う戦場を形成することが目的とされていた。そのため、圧倒的な差による惰性の戦いを見直す機運が魔族内部にも芽生え始めていた。
ニンゲン側への警戒と二〇年後の展望
ルフィナと王は、現時点では英雄と新型機の脅威は限定的であると判断していたが、将来的な人類側の進化には警戒を怠らなかった。とりわけ、第二次救世主計画のように偶発的な英雄誕生を基にした技術飛躍の再来を懸念し、二〇年後を一つの目安に動向を注視する必要があると見做していた。
魔族側の方針決定と育成方針
王とルフィナは、今後の方針として魔族たちの能力強化と戦闘訓練の徹底を指示した。特に、アルバの敗北を教訓とし、下級魔族に危機感と発奮材料を与えることで成長を促す方針を打ち出した。生き残るに値しない者は淘汰されるという厳しい競争原理が貫かれた。
英雄に対する様子見と接触禁止令
魔族側は、当面の間、川上啓太への接触、暗殺、脅迫などを一切禁じると正式に通達する方針を決めた。これは英雄の戦力を見極めるための「様子見」期間とされ、その間に不用意な行動を取る者が出ないよう厳命された。ただし、この方針には裏の動機として、ルフィナ自身が不利な前線配置を避けたいという個人的思惑も含まれていた。
川上啓太への一方的な恨み
英雄である啓太は、自身の意思とは無関係に魔族を葬ったことで、魔族たちから一方的な恨みを買う存在となっていた。戦いの中で結果を出した啓太に対し、魔族社会全体が「脅威」としての認識を強めつつあり、今後も標的として注視され続けることが予想された。
同シリーズ




その他フィクション

Share this content:
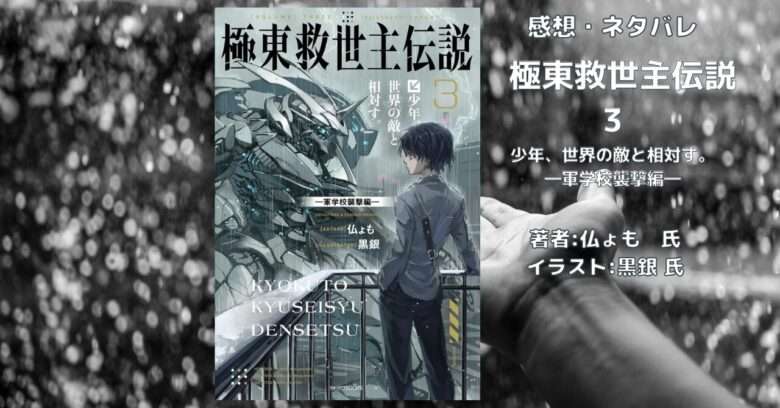

コメントを残す